常微分方程式はいつでも解を明示的に求められるとは限りませんが,解けることがよく知られている常微分方程式もいくつかあり,そのような常微分方程式を解けるようになっておくことは大切です.
解ける常微分方程式の中でも1階線形はよく現れるもののひとつです.
また,変形を施すことで1階線形に帰着するベルヌーイの微分方程式と呼ばれる常微分方程式の解法も併せて解説します.
この記事では
- 1階線形の常微分方程式とその解法
- 具体的に1階線形の常微分方程式を解く
- ベルヌーイの微分方程式は1階線形に帰着させて解ける
を順に解説します.
1階線形の常微分方程式とその解法
$a$, $b$を既知の関数とします.未知関数$y$,変数$x$の
\begin{align*}y'(x)+a(x)y(x)=b(x)\end{align*}
の形をした常微分方程式を1階線形といいます.$y(x)$, $y'(x)$について1次式なので「線形」と呼ばれています.
一般に
\begin{align*}y^{(n)}(x)+a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x)+\dots+a_1(x)y'(x)+a_0(x)y(x)=b(x)\end{align*}
の形をした常微分方程式を(高階)線形といいます.
1階線形の常微分方程式の具体例
例えば,次の常微分方程式はいずれも1階線形です.
- $y'(x)-3y(x)=3$
- $y'(x)-2xy(x)=x$
- $y'(x)+\frac{2xy(x)}{x^2+1}=4x$
のちに実際にこれらの微分方程式を解きますが,まずは一般的な解法を見ておきましょう.
1階線形の常微分方程式の解法
ここでは1階線形の常微分方程式$y'(x)+a(x)y(x)=b(x)$の解き方を解説します.ただし,関数$a$, $b$はともに連続であるとします.
関数$a$は連続なので原始関数をもちますから,関数$a$の原始関数のひとつを任意にとって$p(x)$とします.微分方程式の両辺に$e^{p(x)}$をかけると
\begin{align*}e^{p(x)}(y'(x)+a(x)y(x))=e^{p(x)}b(x)\end{align*}
です.この左辺は
\begin{align*}&e^{p(x)}(y'(x)+a(x)y(x))
\\&=e^{p(x)}y'(x)+e^{p(x)}a(x)y(x)
\\&=(e^{p(x)}y(x))’\end{align*}
とまとめることができるので,
\begin{align*}(e^{p(x)}y(x))’=e^{p(x)}b(x)\end{align*}
が成り立ちます.よって,両辺を積分して$e^{p(x)}$で割れば解$y(x)$が得られますね($e^{p(x)}b(x)$は連続なので原始関数が存在します).
具体的に1階線形の常微分方程式を解く
ここで,上で挙げた3つの常微分方程式を解きましょう.
具体例1:$y'(x)-3y(x)=3$を解く
常微分方程式$y'(x)-3y(x)=3$を解け.
$a(x)\equiv-3$, $b(x)\equiv3$の1階線形です.$a(x)$の原始関数$-3x$がとれるので,両辺に$e^{-3x}$をかけて左辺をまとめましょう.
$-3x$は$y(x)$の係数$-3$の原始関数のひとつだから,常微分方程式の両辺に$e^{-3x}$をかけて
\begin{align*}&e^{-3x}y'(x)-3e^{-3x}y(x)=3e^{-3x}
\\&\iff (e^{-3x}y(x))’=3e^{-3x}\end{align*}
だから
\begin{align*}&e^{-3x}y(x)=-e^{-3x}+C
\\&\iff y(x)=-1+Ce^{3x}\end{align*}
と解ける.ただし,$C$は任意定数である.
具体例2:$y'(x)-2xy(x)=x$を解く
常微分方程式$y'(x)-2xy(x)=x$を解け.
$a(x)=-2x$, $b(x)=x$の1階線形です.$a(x)$の原始関数$-x^2$がとれるので,両辺に$e^{-x^2}$をかけて左辺をまとめましょう.
$-x^2$は$y(x)$の係数$-2x$の原始関数のひとつだから,常微分方程式の両辺に$e^{-x^2}$をかけて
\begin{align*}&e^{-x^2}y'(x)-2xe^{-x^2}y(x)=xe^{-x^2}
\\&\iff \bra{e^{-x^2}y(x)}’=xe^{-x^2}\end{align*}
だから
\begin{align*}&e^{-x^2}y(x)=-\frac{1}{2}e^{-x^2}+C
\\&\iff y(x)=-\frac{1}{2}+Ce^{x^2}\end{align*}
と解ける.ただし,$C$は任意定数である.
具体例3:$y'(x)+\frac{2xy(x)}{x^2+1}=4x$を解く
常微分方程式$y'(x)+\frac{2xy(x)}{x^2+1}=4x$を解け.
$a(x)=\frac{2x}{x^2+1}$, $b(x)=4x$の1階線形です.
$\log{(x^2+1)}$は$y(x)$の係数$\frac{2x}{x^2+1}$の原始関数のひとつだから,常微分方程式の両辺に
\begin{align*}e^{\log{(x^2+1)}}=x^2+1\end{align*}
をかけて
\begin{align*}&(x^2+1)y'(x)+2xy(x)=4x(x^2+1)
\\&\iff \bra{(x^2+1)y(x)}’=4x^3+4x\end{align*}
だから
\begin{align*}&(x^2+1)y(x)=x^4+2x^2+C
\\&\iff y(x)=\frac{x^4+2x^2+C}{x^2+1}\end{align*}
と解ける.ただし,$C$は任意定数である.
ベルヌーイの微分方程式は1階線形に帰着させて解ける
$\gamma\neq0,1$を実数とします.未知関数$y$,変数$x$の
\begin{align*}y'(x)+a(x)y(x)=b(x)y(x)^\gamma\end{align*}
の形をした常微分方程式をベルヌーイの微分方程式といいます.形としては1階線形$y'(x)+a(x)y(x)=b(x)$の右辺に$y(x)^\gamma$がかけられたものですね.
$\gamma=0$のときは1階線形そのもので,$\gamma=1$のときは右辺を移項すれば1階線形なので,最初の$\gamma\neq0,1$の条件は1階線形でないための条件です.
ベルヌーイの微分方程式の解法
$\gamma>0$のときは,$y(x)\equiv0$がひとつの解となります.
一方,定数関数解$y(x)\equiv0$でない解$y(x)$は値0をとらないので,$u(x)=y(x)^{1-\gamma}$と新しい関数$u$をおくことができ,未知関数$u$の1階線形の常微分方程式に帰着させることができます.
理論にこだわらない場合はあまり気にする必要はありませんが,初期値問題の解の一意存在が成り立つときは定数関数解$y(x)\equiv0$でない解$y(x)$は値0をとりません.
実際,$u(x)=y(x)^{1-\gamma}$より$y(x)=u(x)^{1/(1-\gamma)}$で,この両辺を$x$で微分すると
\begin{align*}y'(x)=\frac{1}{1-\gamma}u(x)^{\gamma/(1-\gamma)}u'(x)\end{align*}
なので,ベルヌーイの微分方程式は
\begin{align*}&y'(x)+a(x)y(x)=b(x)y(x)^\gamma
\\&\iff\frac{1}{1-\gamma}u(x)^{\gamma/(1-\gamma)}u'(x)+a(x)u(x)^{1/(1-\gamma)}=b(x)u(x)^{\gamma/(1-\gamma)}
\\&\iff\frac{1}{1-\gamma}u'(x)+a(x)u(x)=b(x)\end{align*}
と未知関数$u$の1階線形の常微分方程式に帰着しますね.
$\gamma<0$のときは,解$y(x)$は値0をとり得ない(正の値しかとり得ない)ので,$\gamma>0$のときと同様に$u(x)=y(x)^{1-\gamma}$とくことで1階線形の常微分方程式に帰着します.
具体例1:$y'(x)-2xy(x)=xy(x)^2$を解く
常微分方程式$y'(x)-2xy(x)=xy(x)^2$を解け.
ベルヌーイの微分方程式$y'(x)+a(x)y(x)=b(x)y(x)^\gamma$の$\gamma$が$\gamma=2$のベルヌーイの常微分方程式なので,新しい未知関数$u$を
\begin{align*}u(x)=y(x)^{1-2}=y(x)^{-1}\end{align*}
とおけば1階線形に帰着します.ただし,値0をとる解$y(x)$は逆数をとれないので注意が必要です.
問題の常微分方程式は$y'(x)=2xy(x)+xy(x)^2$と変形でき,この右辺は$x,y$について連続かつ$y$について局所リプシッツ連続なので,任意の初期値問題に対して解が一意に存在する.よって,異なる解$y(x)$は同じ$x$で同じ値をとらないことに注意する.
$y(x)\equiv0$は解のひとつなので,初期値問題の解の一意性より,この定数関数解$y(x)\equiv0$以外の解は値0をとらない.以下,$y(x)\equiv0$でない解$y(x)$を考える.
未知関数$u$を$u(x)=y(x)^{-1}$で定めると,$u(x)y(x)=1$なので両辺を$x$で微分して$u'(x)y(x)+u(x)y'(x)=0$だから,
\begin{align*}y'(x)=-\frac{u'(x)y(x)}{u(x)}=-\frac{u'(x)}{u(x)^2}\end{align*}
が成り立つ.よって,常微分方程式は
\begin{align*}&-\frac{u'(x)}{u(x)^2}-\frac{2x}{u(x)}=\frac{x}{u(x)^2}
\\&\iff u'(x)+2xu(x)=-x\end{align*}
と変形できる.$x^2$は$u(x)$の係数$2x$の原始関数のひとつだから,常微分方程式の両辺に$e^{x^2}$をかけて
\begin{align*}&e^{x^2}u'(x)+2xe^{x^2}u(x)=-xe^{x^2}
\\&\iff \bra{e^{x^2}u(x)}’=-xe^{x^2}\end{align*}
だから
\begin{align*}&e^{x^2}u(x)=-\frac{1}{2}e^{x^2}+C
\\&\iff u(x)=-\frac{1}{2}+Ce^{-x^2}
\\&\iff y(x)=\frac{2}{2Ce^{-x^2}-1}\end{align*}
と解ける.ただし,$C$は任意定数である.以上より,解は
\begin{align*}y(x)\equiv0,\quad
y(x)=\frac{2}{2Ce^{-x^2}-1}\end{align*}
である.
途中の$u'(x)+2xu(x)=-x$が1階線形の常微分方程式になっているのがポイントですね.
問題の常微分方程式は$y'(x)=x(2y(x)+y(x)^2)$と変形でき,変数分離形として解くこともできます.
具体例2:$y'(x)-3xy(x)=xy(x)\sqrt{y(x)}$を解く
常微分方程式$y'(x)-3xy(x)=xy(x)\sqrt{y(x)}$を解け.
ベルヌーイの微分方程式$y'(x)+a(x)y(x)=b(x)y(x)^\gamma$の$\gamma$が整数である必要はありません.この問題は$\gamma=\frac{3}{2}$の場合ですから,
\begin{align*}u(x)=y(x)^{1-\frac{3}{2}}=y(x)^{-1/2}\end{align*}
とおけば1階線形に帰着します.ただし,今回も値0をとる解$y(x)$は逆数をとれないので注意が必要です.
問題の常微分方程式は$y'(x)=3xy(x)+xy(x)\sqrt{y(x)}$と変形でき,この右辺は$x,y$について連続かつ$y$について局所リプシッツ連続なので,任意の初期値問題に対して解が一意に存在する.よって,異なる解$y(x)$は同じ$x$で同じ値をとらないことに注意する.
$y(x)\equiv0$は解のひとつなので,初期値問題の解の一意性より,この定数関数解$y(x)\equiv0$以外の解は値0をとらない.以下,$y(x)\equiv0$でない解$y(x)$を考える.
未知関数$u$を$u(x)=y(x)^{-1/2}$で定めると,$u(x)y(x)^{1/2}=1$なので両辺を$x$で微分して
\begin{align*}u'(x)y(x)^{1/2}+\frac{1}{2}u(x)y(x)^{-1/2}y'(x)=0\end{align*}
だから,
\begin{align*}y'(x)=-\frac{2u'(x)y(x)^{1/2}}{u(x)y(x)^{-1/2}}=-\frac{2u'(x)}{u(x)^3}\end{align*}
が成り立つ.よって,常微分方程式は
\begin{align*}&-\frac{2u'(x)}{u(x)^3}-\frac{3x}{u(x)^2}=\frac{x}{u(x)^3}
\\&\iff u'(x)+\frac{3}{2}xu(x)=-\frac{1}{2}x\end{align*}
と変形できる.$\frac{3}{4}x^2$は$u(x)$の係数$\frac{3}{2}x$の原始関数のひとつだから,常微分方程式の両辺に$e^{3x^2/4}$をかけて
\begin{align*}&e^{3x^2/4}u'(x)+\frac{3}{2}xe^{3x^2/4}u(x)=-\frac{1}{2}xe^{3x^2/4}
\\&\iff \bra{e^{3x^2/4}u(x)}’=-\frac{1}{2}xe^{3x^2/4}\end{align*}
だから
\begin{align*}&e^{3x^2/4}u(x)=-\frac{1}{3}e^{3x^2/4}+C
\\&\iff u(x)=-\frac{1}{3}+Ce^{-3x^2/4}
\\&\iff y(x)=\frac{9}{(3Ce^{-3x^2/4}-1)^2}\end{align*}
と解ける.ただし,$C$は任意定数である.以上より,解は
\begin{align*}y(x)\equiv0,\quad
y(x)=\frac{9}{(3Ce^{-3x^2/4}-1)^2}\end{align*}
である.
途中の$u'(x)+\frac{3}{2}xu(x)=-\frac{1}{2}x$が1階線形の常微分方程式になっているのがポイントですね.
問題の常微分方程式は$y'(x)=xy(x)(3+\sqrt{y(x)})$と変形でき,変数分離形として解くこともできますが,具体例1と違い少々積分が面倒です.
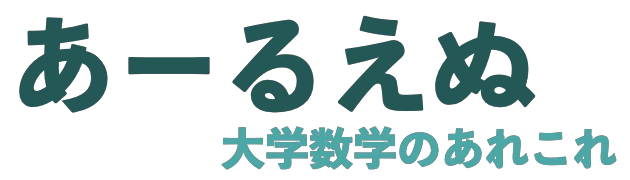

コメント