数学では,等号$=$や合同$\equiv$のように「2つの対象の関係」を表すものを二項関係子といい,プラス+や$\sum$のように「いくつかの対象の演算」を表すものを演算子といいます.
この記事では,$\LaTeX$で
- 矢印
- 二項関係子
- 二項演算子
- 大型演算子
を出力するコマンドを紹介します.
なお,この記事では以下のように amssymbパッケージを用います.
|
1 2 3 4 5 6 |
\documentclass{jsarticle} \usepackage{amssymb} \begin{document} \end{document} |
矢印
矢印の$\LaTeX$コマンドを紹介します.
基本の矢印
| コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
|---|---|---|---|
| \rightarrow,\longrightarrow | $\rightarrow,\longrightarrow$ | \Rightarrow,\Longrightarrow | $\Rightarrow,\Longrightarrow$ |
| \leftarrow,\longleftarrow | $\leftarrow,\longleftarrow$ | \Leftarrow,\Longleftarrow | $\Leftarrow,\Longleftarrow$ |
| \leftrightarrow,\longleftrightarrow | $\leftrightarrow,\longleftrightarrow$ | \Leftrightarrow,\Longleftrightarrow | $\Leftrightarrow,\Longleftrightarrow$ |
| \downarrow,\Downarrow | $\downarrow,\Downarrow$ | \uparrow,\Uparrow | $\uparrow,\Uparrow$ |
| \updownarrow,\Updownarrow | $\updownarrow,\Updownarrow$ | \nearrow,\searrow | $\nearrow,\searrow$ |
| \swarrow,\nwarrow | $\swarrow,\nwarrow$ | \leftleftarrows,\rightrightarrows | $\leftleftarrows,\rightrightarrows$ |
| \upuparrows,\downdownarrows | $\upuparrows,\downdownarrows$ | \leftrightarrows,\rightleftarrows | $\leftrightarrows,\rightleftarrows$ |
| \rightharpoonup,\leftharpoonup | $\rightharpoonup,\leftharpoonup$ | \rightharpoondown,\leftharpoondown | $\rightharpoondown,\leftharpoondown$ |
| \upharpoonright,\upharpoonleft | $\upharpoonright,\upharpoonleft$ | \downharpoonright,\downharpoonleft | $\downharpoonright,\downharpoonleft$ |
| \rightleftharpoons,\leftrightharpoons | $\rightleftharpoons,\leftrightharpoons$ | \hookrightarrow,\hookleftarrow | $\hookrightarrow,\hookleftarrow$ |
| \mapsto,\longmapsto | $\mapsto,\longmapsto$ | \iff | $\iff$ |
斜めの矢印の \nearrow,\searrow,\swarrow,\nwarrowについて, e,w,s,nはそれぞれeast(東), west(西), south(南), north(北)の頭文字を表していますね.
同値を表す \Longleftrightarrowと \iffでは矢印の左右の隙間の幅が異なります.例えば,
- P\Longleftrightarrow Qで出力すると$P\Longleftrightarrow Q$
- P\iff Qで出力すると$P\iff Q$
と少しだけ \iffの方が矢印の左右の隙間が広いです.
矢印の上下に文字を置く
矢印の上に文字を置きたいときは \stackrelまたは \oversetを,矢印の下に文字を置きたいときは \undersetを用います.例えば,
- \stackrel{\mathrm{def.}}{\iff}または \overset{\mathrm{def.}}{\iff}で出力すると$\overset{\mathrm{def.}}{\iff}$
- \underset{\mathrm{def.}}{\iff}で出力すると$\underset{\mathrm{def.}}{\iff}$
となります.
また, amsmathパッケージを用いると,矢印の上下に文字を置くことができる次の矢印のコマンドも使えます.
| コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
|---|---|---|---|
| \xrightarrow[down]{up} | $\xrightarrow[down]{up}$ | \xleftarrow[down]{up} | $\xleftarrow[down]{up}$ |
二項関係子
二項関係子の$\LaTeX$コマンドを紹介します.
| コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
|---|---|---|---|
| =,\equiv,\approx,\neq | $=,\equiv,\approx,\neq$ | \risingdotseq,\fallingdotseq | $\risingdotseq,\fallingdotseq$ |
| <,\le,\leq,\leqq | $<,\le,\leq,\leqq$ | >,\ge,\geq,\geqq | $>,\ge,\geq,\geqq$ |
| \leqslant,\geqslant | $\leqslant,\geqslant$ | \lessgtr,\gtrless | $\lessgtr,\gtrless$ |
| \lesseqgtr,\gtreqless | $\lesseqgtr,\gtreqless$ | \lesseqqgtr,\gtreqqless | $\lesseqqgtr,\gtreqqless$ |
| \ll,\lll | $\ll,\lll$ | \gg,\ggg | $\gg,\ggg$ |
| \subset,\Subset | $\subset,\Subset$ | \supset,\Supset | $\supset,\Supset$ |
| \subseteq,\subseteqq | $\subseteq,\subseteqq$ | \supseteq,\supseteqq | $\supseteq,\supseteqq$ |
| \subsetneq,\subsetneqq | $\subsetneq,\subsetneqq$ | \supsetneq,\supsetneqq | $\supsetneq,\supsetneqq$ |
| \in,\ni,\notin | $\in,\ni,\notin$ | \sim,\backsim,\nsim | $\sim,\backsim,\nsim$ |
| \simeq,\backsimeq,\cong | $\simeq,\backsimeq,\cong$ | \parallel | $\parallel$ |
\leと \leqはどちらでも同じで, \geと \geqもどちらでも同じです.
また,否定の演算子が用意されていない場合は \notを用います.例えば, \not\subsetで出力すると$\not\subset$となります.
演算子
最後に二項演算子・大型演算子の$\LaTeX$コマンドを紹介します.
二項演算子
2つの対象に対する演算子を,とくに二項演算子といいます.
| コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
|---|---|---|---|
| +,-,\pm,\mp | $+,-,\pm,\mp$ | \times,\div | $\times,\div$ |
| \cdot,\circ,\ast,\star,\bullet | $\cdot,\circ,\ast,\star,\bullet$ | \cup,\cap | $\cup,\cap$ |
| \setminus | $\setminus$ | \triangle | $\triangle$ |
| \oplus,\otimes | $\oplus,\otimes$ | \vee,\wedge | $\vee,\wedge$ |
なお,差集合を表すためにバックスラッシュ \backslashを用いるのは適切ではなく,差集合を表す場合は \setminusを用います.例えば,
- A\setminus Bで出力すると$A\setminus B$
- A\backslash Bで出力すると$A\backslash B$
と少しだけ \setminusの方が左右の隙間が広いです.
大型演算子
複数のものを同時に演算する場合には大型演算子が用いられます.
| コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
|---|---|---|---|
| \sum,\prod | $\sum,\prod$ | \bigcup,\bigcap | $\bigcup,\bigcap$ |
| \bigvee,\bigwedge | $\bigvee,\bigwedge$ | \bigotimes,\bigoplus | $\bigotimes,\bigoplus$ |
| \int | $\int$ | \oint | $\oint$ |
積分は演算子ではありませんが,同様に出力されるのでここで紹介しました.
また, amsmathパッケージを用いると, \iint,\iiintで$\iint,\iiint$が出力できます.
大型演算子の大きさや添え字の位置は変えることができます.
| コマンド | 表示 | コマンド | 表示 |
|---|---|---|---|
| \textstyle\sum_{k=1}^{n} | $\textstyle\sum_{k=1}^{n}$ | \textstyle\sum\limits_{k=1}^{n} | $\textstyle\sum\limits_{k=1}^{n}$ |
| \displaystyle\sum_{k=1}^{n} | $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}$ | \displaystyle\sum\nolimits_{k=1}^{n} | $\displaystyle\sum\nolimits_{k=1}^{n}$ |
文中で \$ \$で囲む場合は指定しなくても \textstyleの仕様になり, \begin{align} \end{align}などで囲んで別行立てする場合は指定しなくても \displaystyleの仕様になります.
また,添え字の位置は
- \textstyleではデフォルトで横に来る
- \displaystyleではデフォルトで上下に来る
ので,
- \textstyleで上下に置きたいときは \limits
- \displaystyleで横に置きたいときは \nolimits
を用いればいいわけですね.
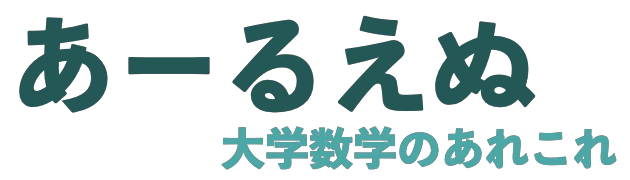
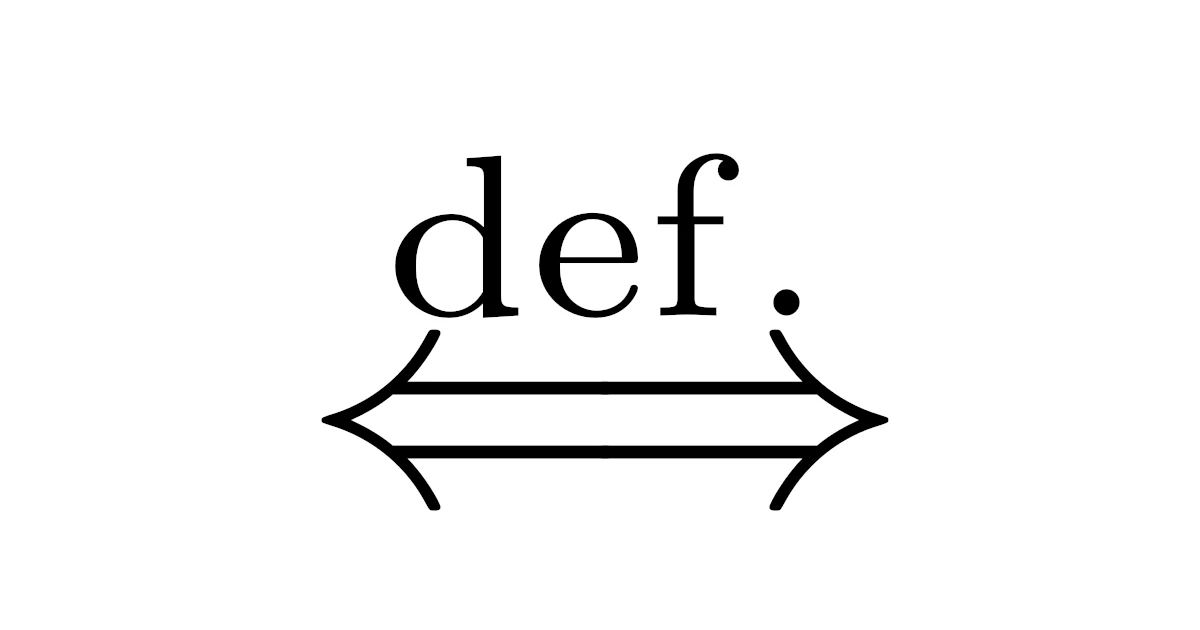

コメント