2025年度の東京大学 数理科学研究科の大学院入試問題の専門科目Aの解答の方針と解答例です.
問題は7題あり,必答問題は第1・2問で,残りの第3〜7問から2問を選択して解答します.試験時間は3時間です.この記事では,第1〜7問について解説しています.
ただし,公式に採点基準などは発表されていないため,本稿の解答が必ずしも正解になるとは限りません.ご注意ください.
また,十分注意して解答を作成していますが,論理の飛躍・誤りが残っている場合があります.
なお,最近の過去問は東京大学の数理科学研究科のホームページから入手できます.
第1問:微分積分学
- 実数$x\ge1$に対し,広義積分\begin{align*}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{x+y}\,dy\end{align*}が収束することを示せ.
- (1)の広義積分の値を$f(x)$と書く.次の極限が有限値として存在するような実数$a_0$, $a_1$, $a_2$を求め,その極限値を求めよ.\begin{align*}\lim_{x\to\infty}x^3\bra{f(x)-a_0-\frac{a_1}{x}-\frac{a_2}{x^2}}\end{align*}
(1)の広義積分で定まる関数$f(x)$の$x\to\infty$での漸近展開を求める問題です.
解答の方針とポイント
ディリクレ積分$\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{y}\,dy$を連想させる問題ですが,実際にディリクレ積分が収束することを示すのと同じ方法で解くことができます.
ディリクレ積分が収束することの証明
ディリクレ積分が
\begin{align*}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{y}\,dy=\frac{\pi}{2}\end{align*}
と収束することはよく知られていますが,収束することを示すだけであれば次のように簡単に証明することができます.
$(0,1]$上で$\frac{\sin{y}}{y}$は一様連続だから$\int_{0}^{1}\frac{\sin{y}}{y}\,dy$は有限の値に収束します.また,任意の$R>0$に対して,
\begin{align*}\int_{1}^{R}\frac{\sin{y}}{y}\,dy=\bra{\cos{1}-\frac{\cos{R}}{R}}-\int_{1}^{R}\frac{\cos{y}}{y^2}\,dy\end{align*}
であり,
\begin{align*}\int_{1}^{\infty}\abs{\frac{\cos{y}}{y^2}}\,dy\le\int_{1}^{\infty}\frac{1}{y^2}\,dy=1<\infty\end{align*}
だから,$\int_{1}^{\infty}\frac{\cos{y}}{y^2}\,dy$は絶対収束するので収束します.よって,ディリクレ積分は収束します.
部分積分により$\sin$の振動と$\frac{1}{y}$の減衰を取り出す
上記のディリクレ積分の収束の議論で重要なのは$[1,\infty)$で部分積分を用いているところです.
広義積分$\int_{1}^{\infty}\frac{\sin{y}}{y}\,dy$で,$\sin$がない広義積分$\int_{1}^{\infty}\frac{1}{y}\,dy$は発散しますし,減衰$\frac{1}{y}$がない広義積分$\int_{1}^{\infty}\sin{y}\,dy$も発散します.
つまり,広義積分$\int_{1}^{\infty}\frac{\sin{y}}{y}\,dy$が収束するのは,$\frac{1}{y}$による減衰と$\sin$による振動で正負が打ち消しあっていることが理由で,これらの効果を取り出したいわけです.
そこで,部分積分(積の微分公式)を用いることで$\sin{y}$の導関数(振動)を含んだ項が得られ,また$\frac{1}{y}$が受け取った微分により減衰を稼いだ項$\frac{\sin{y}}{y^2}$の積分も得られ,広義積分$\int_{1}^{\infty}\frac{\sin{y}}{y}\,dy$が収束するわけですね.
以上の原理と同様に,本問の広義積分
\begin{align*}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{x+y}\,dy\end{align*}
にも繰り返し部分積分を施し,振動の効果を取り出し減衰も稼ぐことで$x\to\infty$の漸近展開が得られ解くことができそうですね.
東京大学の数理科学研究科の大学院入試では部分積分により解ける問題が頻出しているので意識しておくとよいでしょう.
解答例
(1)の解答
任意の$R>0$に対して,部分積分により
\begin{align*}\int_{0}^{R}\frac{\sin{y}}{x+y}\,dy
&=\brc{\frac{-\cos{y}}{x+y}}_{0}^{R}-\int_{0}^{R}\frac{\cos{y}}{(x+y)^2}\,dy
\\&=\bra{\frac{1}{x}-\frac{\cos{R}}{x+R}}-\int_{0}^{R}\frac{\cos{y}}{(x+y)^2}\,dy\end{align*}
であり,$\lim\limits_{R\to\infty}\bra{\frac{1}{x}-\frac{\cos{R}}{x+R}}=\frac{1}{x}$である.また,
\begin{align*}&\int_{0}^{\infty}\abs{\frac{\cos{y}}{(x+y)^2}}\,dy
\le\int_{0}^{\infty}\frac{1}{(x+y)^2}\,dy
\\&=\brc{-\frac{1}{x+y}}_{0}^{\infty}=\frac{1}{x}<\infty\end{align*}
なので,$\int_{0}^{\infty}\frac{\cos{y}}{(x+y)^2}\,dy$は絶対収束するから収束する.よって,$\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{x+y}\,dy$は
\begin{align*}\frac{1}{x}-\int_{0}^{\infty}\frac{\cos{y}}{(x+y)^2}\,dy\end{align*}
に収束する.
(2)の解答
(1)と同様に部分積分により
\begin{align*}\int_{0}^{\infty}\frac{\cos{y}}{(x+y)^2}\,dy&=\brc{\frac{\sin{y}}{(x+y)^2}}_{0}^{\infty}+2\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{(x+y)^3}\,dy
\\&=2\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{(x+y)^3}\,dy,
\\\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{(x+y)^3}\,dy&=\brc{\frac{-\cos{y}}{(x+y)^3}}_{0}^{\infty}-3\int_{0}^{\infty}\frac{\cos{y}}{(x+y)^4}\,dy
\\&=\frac{1}{x^3}-3\int_{0}^{\infty}\frac{\cos{y}}{(x+y)^4}\,dy,
\\\int_{0}^{\infty}\frac{\cos{y}}{(x+y)^4}\,dy&=\brc{\frac{\sin{y}}{(x+y)^4}}_{0}^{\infty}+4\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{(x+y)^5}\,dy
\\&=4\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{(x+y)^5}\,dy\end{align*}
であり,
\begin{align*}\abs{\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{y}}{(x+y)^5}\,dy}
&\le\int_{0}^{\infty}\abs{\frac{\sin{y}}{(x+y)^5}}\,dy
\\&\le\int_{0}^{\infty}\frac{1}{(x+y)^5}\,dy=\frac{1}{4x^4}\end{align*}
だから,$f(x)$の漸近展開
\begin{align*}&f(x)=\frac{1}{x}-\frac{2}{x^3}+o\bra{\frac{1}{x^3}}&(x\to\infty)\end{align*}
が得られる.よって,$a_0=0$, $a_1=1$, $a_2=0$のとき,
\begin{align*}\lim_{x\to\infty}x^3\bra{f(x)-a_0-\frac{a_1}{x}-\frac{a_2}{x^2}}=-2\end{align*}
と収束する.
第2問:線形代数学
$a$を実数とし,4次正方行列$A$とベクトル$\m{z}\in\R^4$を次で定める.
\begin{align*}&A=\pmat{0&1&0&0\\0&0&1&0\\2&0&0&0\\0&0&0&2a},&\m{z}=\pmat{0\\0\\1\\1}.\end{align*}
線型写像$f:\R^4\to\R^4$を任意の$\m{x}\in\R^4$に対し
\begin{align*}f(\m{x})=A\m{x}\end{align*}
と定める.ユークリッド空間$\R^4$において$\m{z}$と直交するベクトル全体のなす$\R^4$の部分空間を$V$とし,$p:\R^4\to V$を$\R^4$から$V$の上への直交射影とする.さらに,$f$の$V$への制限を$f_V:V\to\R^4$と書き,$g=p\circ f_V$とおく.以下の問に答えよ.
- $V$上の線型変換$g$の特性多項式を求めよ.
- $V$のある基底に対する$g$の表現行列が対角行列となるような$a$を全て求めよ.
線形写像の表現行列と対角化を考える問題です.
解答の方針とポイント
線形写像の表現行列と特性多項式(固有多項式)周りの定義が理解できていれば,定義に従って計算すれば解けます.
線形写像の表現行列
同じ体上の線形空間$U,V\neq\{0\}$と,それぞれの基底$\mathcal{B}_U=(\m{u}_1,\m{u}_2,\dots,\m{u}_n)$, $\mathcal{B}_V=(\m{v}_1,\m{v}_2,\dots,\m{v}_m)$を考える.このとき,$m\times n$行列$A$が線形写像$f:U\to V$の$\mathcal{B}_U$, $\mathcal{B}_V$に関する表現行列であるとは
\begin{align*}[f(\m{u}_1),f(\m{u}_2),\dots,f(\m{u}_n)]=[\m{v}_1,\m{v}_2,\dots,\m{v}_m]A\end{align*}
が(形式的に)成り立つことをいう.
$U=V$で$\mathcal{B}_U=\mathcal{B}_V$のときは,単に「$\mathcal{B}_U$に関する表現行列」と言います.
$\mathcal{B}_U$をなす各ベクトルを$f$で移してできるベクトルを,$\mathcal{B}_V$をなすベクトルの線形結合で書いたときの係数をまとめたものが,$f:U\to V$の$\mathcal{B}_U$, $\mathcal{B}_V$に関する表現行列ですね.
線形写像の固有多項式(特性多項式)
一般に線形写像は同じでも異なる基底に関する表現行列は同じとは限りません.しかし,基底の取り換え行列を考えると全ての表現行列が相似であることが分かり,どの表現行列の固有多項式(特性多項式)も等しいものになります.
同じ体上の線形空間$U,V\neq\{0\}$と線形写像$f:U\to V$を考え,$U$の基底$\mathcal{B}_U$, $\mathcal{B}’_U$と,$V$の基底$\mathcal{B}_V$, $\mathcal{B}’_V$をとる.このとき,$\mathcal{B}_U$, $\mathcal{B}_V$に関する表現行列$A$の固有多項式と,$\mathcal{B}’_U$, $\mathcal{B}’_V$に関する表現行列$B$の固有多項式は等しい.
この補題により,次の定義がwell-definedとなりますね.
同じ体上の線形空間$U$, $V$を考える.線形写像$f:U\to V$の任意の表現行列$A$に対して,$A$の固有多項式(特性多項式)を$f$の固有多項式(特性多項式)という.
よって,本問(1)では$V$の基底を好きにとって表現行列を考え,その固有多項式を求めれば良いわけですね.
また,全ての表現行列は相似なので,本問(2)では(1)でとった表現行列が対角化可能であるための$a$の必要十分条件を求めればよいですね.
解答例
$g$の特性多項式を$\phi_g$とする.
(1)の解答
$\anb{\cdot,\cdot}$, $\nor{\cdot}$をそれぞれ$\R^4$上の標準内積,標準ノルムとする.$\m{n}=\frac{\m{z}}{\nor{\m{z}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\m{z}$とする.
$\m{c}=\sbmat{0\\0\\1\\-1}\in\R^4$とし,$\m{e}_i\in\R^4$を第$i$成分のみ1で他の成分が0のベクトルとする($i=1,2,3,4$).$V$の基底$\mathcal{B}=\bra{\m{e}_1,\m{e}_2,\m{c}}$をとる.
\begin{align*}&p(\m{e}_3)=\m{e}_3-\anb{\m{e}_3,\m{n}}\m{n}=\frac{1}{2}\m{c},
\\&p(\m{e}_4)=\m{e}_4-\anb{\m{e}_4,\m{n}}\m{n}=-\frac{1}{2}\m{c}\end{align*}
なので,
\begin{align*}&g(\m{e}_1)=p(A\m{e}_1)=p(2\m{e}_3)=\m{c},
\\&g(\m{e}_2)=p(A\m{e}_2)=p(\m{e}_1)=\m{e}_1,
\\&g(\m{c})=p(A\m{c})=p(\m{e}_2-2a\m{e}_4)=\m{e}_2+a\m{c}\end{align*}
なので,
\begin{align*}&[g(\m{e}_1),g(\m{e}_2),g(\m{c})]=[\m{e}_1,\m{e}_2,\m{c}]\bmat{0&1&0\\0&0&1\\1&0&a}\end{align*}
だから,$g$の$\mathcal{B}$に関する表現行列は$G:=\bmat{0&1&0\\0&0&1\\1&0&a}$である.よって,$g$の特性多項式$\phi_g$は
\begin{align*}\phi_g(x)&=|xI_3-G|=\vmat{x&-1&0\\0&x&-1\\-1&0&x-a}
\\&=x^2(x-a)-1=x^3-ax^2-1\end{align*}
である.
(2)の解答
一般に,どの基底に関する表現行列も互いに相似なので,求める$a$は実正則行列により$G$が対角化可能であるような$a$に一致する.$\phi_g$の導関数は
\begin{align*}\phi’_g(x)=3x^2-2ax=x(3x-2a)\end{align*}
なので,$x=0,\frac{2a}{3}$で$\phi_g(x)$の増減が切り替わることに注意する.$G$が異なる3つの実固有値をもつときは対角化可能だから,
\begin{align*}\phi_g(0)\phi_g\bra{\frac{2a}{3}}<0
&\iff-1\bra{\frac{8a^3}{27}-\frac{4a^3}{9}-1}<0
\\&\iff a<-\frac{3}{\sqrt[3]{4}}\end{align*}
のときは$G$は対角化可能である.
一方,$a=-\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$のときは,$\phi_g\bra{\frac{2a}{3}}=0$だから$\frac{2a}{3}$が重複度2の固有値で,
\begin{align*}\rank{\bra{G-\frac{2a}{3}I_3}}=\rank{\bmat{-2a/3&1&0\\0&-2a/3&1\\1&0&a/3}}\ge2\end{align*}
より$\rank{\bra{G-\frac{2a}{3}I_3}}\neq1$だから,対角化不可能である.また,$a>-\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$のときは,$\phi_g(0)=-1$かつ$\phi_g\bra{\frac{2a}{3}}<0$より実固有値は1個のみでその重複度は1だから対角化不可能である.
以上より,$a<-\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$を満たす$a$が求める全ての$a$である.
第3問:微分積分学
整数$n\ge1$に対して関数$f_n:\R\to\R$および$g_n:\R^3\to\R$をそれぞれ
\begin{align*}&f_1(x)=\sin{x},\quad f_{n+1}(x)=\sin{\bigl(f_n(x)\bigr)},
\\&g_n(x,y,z)=\frac{1}{n}\log{(e^{nx}+e^{ny}+e^{nz})}\end{align*}
と定める.以下の問に答えよ.
- 関数列$\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$が$\R$上一様収束するか否かを判定し,一様収束する場合には極限関数$f(x)$を求めよ.
- 関数列$\{g_n(x,y,z)\}_{n=1}^{\infty}$が$\R^3$上一様収束するか否かを判定し,一様収束する場合には極限関数$g(x,y,z)$を求めよ.
関数列が一様収束するかどうかを示す問題です.
解答の方針とポイント
一様収束するためには各点収束しないといけませんから,どちらの問題も1点がどのように遷移していくかを観察することが大切です.
漸化式がある場合の収束の証明
まずは本問(1)を考えましょう.任意の$x\in\R$に対して,$0\le|f_1(x)|=|\sin{x}|\le1$です.$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$で$\sin$は単調増加で,$1<\frac{\pi}{2}$なので
\begin{align*}|f_2(x)|=|\sin{(\sin{x})}|\le\sin{1}\end{align*}
となります.帰納的に$n\ge2$で$|f_n(x)|\le f_n(1)$となることが分かり,$f_n$が$\sin$個の合成ですから$f_n(1)$は0に収束するので,関数列$\{f_n\}$が0に一様収束することが見てとれますね.
しかし,$x\approx0$では$\sin{x}\approx x$なので,0に近付くほど減衰が弱くなり単純な評価で示すのは少々面倒です.
代わりに関数列$\{f_n\}$に関する漸化式があるので,この場合は先に収束を示し,漸化式を用いて極限を求めるという手法が有効ですね.今回は各点について単調減少ですから,単調有界実数列の収束定理を用いて収束を示すことができますね.
指数関数の収束の強さ
例えば,
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\frac{3^n+2^n}{3^n}=\lim_{n\to\infty}\bra{1+\bra{\frac{2}{3}}^n}=1\end{align*}
なので,$n$が十分大きければ$3^n+2^n\approx 3^n$です.すなわち,底が1以上の指数関数を比較すると,底が大きい方が強く発散することが分かります.
同様に,任意の$x,y,z\in\R^3$に対して,$n$が十分大きければ
\begin{align*}e^{nx}+e^{ny}+e^{nz}\approx\max\{e^{nx},e^{ny},e^{nz}\}\end{align*}
となり,
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}g_n(x,y,z)=\max\{x,y,z\}\end{align*}
が成り立つことが見てとれますね.
解答例
(1)の解答
一般に,任意の$t\in\R$に対して$|\sin{t}|\le|t|$が成り立つことに注意する.$M_n:=\sup\limits_{x\in\R}|f_n(x)|$とおく.
任意の$n\in\{1,2,\dots\}$に対して$|f_n(x)|\le1$だから,$1<\frac{\pi}{2}$より$0\le t\le1$において$\sin{t}$が単調増加であることと併せて,
\begin{align*}|f_{n+1}(x)|=\abs{\sin{\bigl(f_n(x)\bigr)}}\le\sin{M_n}\le M_n\end{align*}
が成り立つ.よって,両辺で$x\in\R$に関して上限をとり$M_{n+1}\le M_n$が成り立つので,$\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$は単調減少である.さらに,各$M_n$は非負だから,単調有界実数列の収束定理より極限$M:=\lim\limits_{n\to\infty}M_n$が存在する.
また,$|f_{n+1}(x)|\le\sin{M_n}$の両辺で$x\in\R$に関して上限をとり$M_{n+1}\le\sin{M_n}$が成り立つので,さらに両辺で極限をとって$M\le\sin{M}$が成り立つ.
この不等式を満たす$M\in\R$は$M=0$に限るから,関数列$\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$は恒等的に値0をとる定数関数に一様収束する.
(2)の解答
任意の$(x,y,z)$に対して,
\begin{align*}e^{\max\{nx,ny,nz\}}\le e^{nx}+e^{ny}+e^{nz}\le3e^{\max\{nx,ny,nz\}}\end{align*}
だから
\begin{align*}\max\{x,y,z\}\le g_n(x,y,z)\le\max\{x,y,z\}+\frac{1}{n}\log{3}\end{align*}
である.よって,任意の$(x,y,z)\in\R^3$に対して
\begin{align*}|g_n(x,y,z)-\max\{x,y,z\}|
&=g_n(x,y,z)-\max\{x,y,z\}
\\&\le\frac{1}{n}\log{3}\xrightarrow[]{n\to\infty}0\end{align*}
が成り立つから,関数列$\{g_n(x,y,z)\}_{n=1}^{\infty}$は$\max\{x,y,z\}$に一様収束する.
第4問:線形代数学(加群)
$V$を実線型空間,$V’$を$V$の部分線型空間とする.実線型空間$W$に対し,$B(V,W)$を$V\times V$から$W$への対称双線型写像全体の集合,すなわち
\begin{align*}B(V,W)=\Bigl\{f:V\times V\to W \Big| &\text{$f$は双線型かつ}
\\&\text{すべての$x,y\in V$に対し$f(x,y)=f(y,x)$}\Bigr\}\end{align*}
とする.また,$B(V,W)$の部分集合$A(V,V’,W)$を
\begin{align*}A(V,V’,W)=\Bigl\{f\in B(V,W)\Big|\text{$x\in V$, $y\in V’$ならば$f(x+y,y)=f(y,x)$}\Bigr\}\end{align*}
により定める.さらに,一般に,実線型空間$W_1$, $W_2$に対し
\begin{align*}L(W_1,W_2)=\Bigl\{f:W_1\to W_2\Big|\text{$f$は線型写像}\Bigr\}\end{align*}
とおく.以下の問に答えよ.
- 実線型空間$S$と$A(V,V’,S)$の元$g$の組$(S,g)$であって,次の条件を満たすものが存在することを示せ:
任意の実線型空間$W$に対し,写像\begin{align*}&g^*:L(S,W)\to A(V,V’,W),&f\mapsto g^*(f)=f\circ g\end{align*}は全単射である.
- $V$が有限次元であるとし,$\dim{V}=n$, $\dim{V’}=m$とする.$\dim{S}$を求めよ.
問題の見た目は線形代数学ですが,本質的には加群(テンソル積)の問題です.
解答の方針とポイント
$A(V,V’,W)$が何なのかを捉えることが大事です.また,$B(V,W)$はテンソル積の普遍性を用いて$L(\cdot,W)$の形に同型に書き直すことで道筋が見えます.
$f\in A(V,V’,W)$は$V’\times V’$を0にする$B(V,W)$の元
$f\in A(V,V’,W)$は$f\in B(V,W)$なので対称かつ双線形ですから,任意の$x\in V$, $y\in V’$に対して
\begin{align*}f(x+y,y)=f(y,x)\iff f(y,y)=0\end{align*}
が成り立ちます.さらに,任意の$x,y\in V’$に対して,
\begin{align*}2f(x,y)=f(x+y,x+y)-f(x,x)-f(y,y)=0\end{align*}
なので,$f$は$V’$の2元を与えると0となることが分かります.逆に,このような$f$は$A(V,V’,W)$に属することも分かるので,
\begin{align*}A(V,V’,W)=\Bigl\{f\in B(V,W)\Big|\text{$x,y\in V’$ならば$f(x,y)=0$}\Bigr\}\end{align*}
と分かります.よって,写像$\rho:B(V,W)\to B(V’,W)$を$\rho(b)=b|_{V’\times V’}$で定めると,$A(V,V’,W)=\Ker{\rho}$が成り立ちますね.
$B(V,W)$と$B(V’,W)$での議論を$L(\cdot,W)$での議論にしたい
本問(1)はうまく$S$と$g\in A(V,V’,S)$をとり,任意の実線型空間$W$に対して,
- 線形写像$f:S\to W$($f\in L(S,W)$)
- 任意の$x,y\in V’$に対して$b(x,y)=0$を満たす対称双線形$b:V\times V\to W$($b\in A(V,V’,W)$)
を$f\circ g=b$と全単射に対応させる問題です.そこで,同型
\begin{align*}\Phi_V:B(V,W)\to L(\widetilde{V},W),\quad
\Phi_{V’}:B(V’,W)\to L(\widetilde{V’},W)\end{align*}
が成り立つ$\widetilde{V}$と$\widetilde{V’}$を見つけることができれば,$\rho$に対応する$\rho’:L(\widetilde{V},W)\to L(\widetilde{V’},W)$をとると
\begin{align*}A(V,V’,W)=\Ker{\rho}\cong\Ker{\rho’}\cong L(\widetilde{V}/\widetilde{V’},W)\end{align*}
となり,$S=\widetilde{V}/\widetilde{V’}$ととれば良さそうですね.
すなわち,$S$を見つけるために$B(V,W)\to B(V’,W)$の議論を全て$L(V,W)\to L(V’,W)$に移して考えるわけですね.
$B(V,W)\cong L(\widetilde{V},W)$となる$\widetilde{V}$を見つける
$\phi:V\times V\to V\otimes V$をテンソル積の普遍性による双線形とすると,任意の$b\in B(V,W)$に対して,ある$b’\in L(V\otimes V,W)$が一意に存在して$b’\circ\phi=b$が成り立つので,
\begin{align*}B(V,W)\cong\Bigl\{f\in L(V\otimes V\to W) \Big| \text{すべての$x,y\in V$に対し$f(x\otimes y)=f(y\otimes x)$}\Bigr\}\end{align*}
が成り立ちます.さらに,$V\otimes V$を
\begin{align*}I_2(V)=\operatorname{span}\set{x\otimes y-y\otimes x}{x,y\in V}\end{align*}
で割れば,$x\otimes y,y\otimes x\in V\otimes V$は同一視され
\begin{align*}B(V,W)\cong L((V\otimes V)/I_2(V),W)\end{align*}
が成り立ちます.$V’$についても,同様に$I_2(V’)$を定義すれば$B(V’,W)\cong L((V’\otimes V’)/I_2(V’),W)$が成り立ちます.
実はこの$(V\otimes V)/I_2(V)$は$V$の対称2次テンソル(対称代数の2次成分)と呼ばれるものです.
そこで,$\mathrm{Sym}^2(V):=(V\otimes V)/I_2(V)$, $\mathrm{Sym}^2(V’):=(V\otimes V’)/I_2(V’)$とおけば,以下の可換図式が得られますね.
よって,$\iota^*:\mathrm{Sym}^2(V’)\to\mathrm{Sym}^2(V)$を包含写像$V’\to V$から誘導される自然な準同型(線形写像)とすると,
\begin{align*}\Ker{\rho’}&=\set{F\in L(\mathrm{Sym}^2(V),W)}{F|_{\iota^*(\mathrm{Sym}^2(V’))}=0}
\\&\cong L(\mathrm{Sym}^2(V)/\iota^*(\mathrm{Sym}^2(V’)),W)\end{align*}
が成り立ち,$S=\mathrm{Sym}^2(V)/\iota^*(\mathrm{Sym}^2(V’))$とおけばよいですね.
さらに任意の$f_*\in A(V,V’,W)$に対して,ある$f\in L(S,W)$が一意に存在して,$f_*=f\circ\pi’\circ\pi\circ\phi$と対応するので,$g=\pi’\circ\pi\circ\phi$とおけばよいですね.
解答例
実線形空間($\R$加群)$U$に対して,$U$の対称2次テンソルを$\mathrm{Sym}^2(U)$と表す:
\begin{align*}&I_2(U)=\operatorname{span}\set{x\otimes y-y\otimes x}{x,y\in U},
\\&\mathrm{Sym}^2(U)=(U\otimes U)/I_2(U).\end{align*}
また,$x,y\in U$に対して$\mathrm{Sym}^2(U)$における$x\otimes y\in U\otimes U$の同値類を$x\odot y$で表す.
(1)の解答
- $\phi:V\times V\to V\otimes V$をテンソル積の普遍性による双線形
- $\pi:V\otimes V\to\mathrm{Sym}^2(V)$を自然な準同型(線形写像)
- $\iota:V’\times V’\to V\times V$を包含写像とし,$\iota^*:\mathrm{Sym}^2(V’)\to\mathrm{Sym}^2(V)$を$\iota$から誘導される自然な準同型(線形写像)
- $\pi’:\mathrm{Sym}^2(V)\to\mathrm{Sym}^2(V)/\iota^*(\mathrm{Sym}^2(V’))$を自然な準同型(線形写像)
とする.このとき,
\begin{align*}S=\mathrm{Sym}^2(V)/\iota^*(\mathrm{Sym}^2(V’)),\quad
g=\pi’\circ\pi\circ\phi\end{align*}
とおくと,求める組$(S,g)$となる.このことを以下で示す.
ステップ1:同型$L(\mathrm{Sym}^2(U),W)\cong B(U,W)$を示す.
任意に実線形空間($\R$加群)$U$をとり,
- $\phi_U:U\times U\to U\otimes U$をテンソル積の普遍性による双線形
- $\pi_U:U\otimes U\to\mathrm{Sym}^2(U)$を自然な準同型(線形写像)
とする.任意の$f\in L(\mathrm{Sym}^2(U),W)$に対して,$\phi_U$は双線形,$\pi_U$は線形だから
\begin{align*}f\circ\pi\circ\phi_U\in B(U,W)\end{align*}
である.よって,写像
\begin{align*}\Phi_U:L(\mathrm{Sym}^2(U),W)\to B(U,W);f\mapsto f\circ\pi_U\circ\phi_U\end{align*}
が定義できる.任意の$f_1,f_2\in L(\mathrm{Sym}^2(U),W)$と$k,\ell\in\R$に対して,
\begin{align*}\Phi_U(kf_1+\ell f_2)&=(kf_1+\ell f_2)\circ\pi_U\circ\phi_U
\\&=k(f_1\circ\pi_U\circ\phi_U)+\ell(f_2\circ\pi_U\circ\phi_U)
\\&=k\Phi_U(f_1)+\ell\Phi_U(f_2)\end{align*}
だから$\Phi_U$は線形である.また,任意の$b\in B(U,W)$に対して,テンソル積の普遍性より$b=b^{\prime}\circ\phi_U$を満たす$b’\in L(U\otimes U,W)$が一意に存在する.さらに,$b$の対称性より任意の$x,y\in U$に対して
\begin{align*}b^{\prime}(x\otimes y-y\otimes x)&=b^{\prime}\circ\phi_U(x,y)-b^{\prime}\circ\phi_U(y,x)
\\&=b(x,y)-b(y,x)=0\end{align*}
だから$\Ker{\pi_U}=I_2(U)\subset\Ker{b’}$が成り立つので,$b^{\prime}=b^{\prime\prime}\circ\pi_U$を満たす$b^{\prime\prime}\in L(\mathrm{Sym}^2(U),W)$が一意に存在する.
したがって,写像$\Phi_U(b^{\prime\prime})=b$となる$b^{\prime\prime}\in L(\mathrm{Sym}^2(U),W)$が一意に存在するから,$\Phi_U$は全単射である.よって,同型
\begin{align*}L(\mathrm{Sym}^2(U),W)\cong B(U,W)\end{align*}
が従う.
ステップ2:$A(V,V’,W)$を書き換える.
任意に$f\in A(V,V’,W)$をとると,任意の$z\in V’$に対して
\begin{align*}f(z,z)=f(0+z,z)-f(0,z)=f(z,0)-f(0,z)=0\end{align*}
が成り立つから,任意の$x,y\in V’$に対して
\begin{align*}2f(x,y)=f(x+y,x+y)-f(x,x)-f(y,y)=0\end{align*}
が成り立つ.一方,任意の$x,y\in V’$に対して$f(x,y)=0$を満たす任意の$f\in B(V,W)$をとると,任意の$x\in V$, $y\in V’$に対して
\begin{align*}f(x+y,y)=f(x,y)+f(y,y)=f(y,x)\end{align*}
である.よって,
\begin{align*}A(V,V’,W)=\Bigl\{f\in B(V,W)\Big|\text{$x,y\in V’$ならば$f(x,y)=0$}\Bigr\}\end{align*}
が成り立つ.そこで,写像$\rho:B(V,W)\to B(V’,W)$を$\rho(b)=b|_{V’\times V’}$で定めると,$A(V,V’,W)=\Ker{\rho}$が成り立つ.
ステップ3:$g\in A(V,V’,S)$で$g^*$が全単射であることを示す.
$g=\pi’\circ\pi\circ\phi$は双線形で,任意の$x,y\in V’$に対して
\begin{align*}g(x,y)=\pi’\circ\pi(x\otimes y)=\pi'(x\odot y)=0\end{align*}
なので,$g\in A(V,V’,S)$が成り立つ.
また,写像$\rho’:L(\mathrm{Sym}^2(V),W)\to L(\mathrm{Sym}^2(V’),W)$を$\rho’=\Phi_{V’}^{-1}\circ\rho\circ\Phi_V$とおくと,ステップ1より同型
\begin{align*}\Ker{\rho}\cong\Ker{\rho’}\end{align*}
が成り立つ.また,ステップ2より$A(V,V’,W)=\Ker{\rho}$であり,
\begin{align*}\Ker{\rho’}&=\set{F\in L(\mathrm{Sym}^2(V),W)}{F|_{\iota^*(\mathrm{Sym}^2(V’))}=0}
\\&\cong L(S,W)\end{align*}
だから,$A(V,V’,W)\cong L(S,W)$が成り立つ.以上の構成により,任意の$f_*\in A(V,V’,W)$に対して,ある$f\in L(S,W)$が一意に存在して,$f_*=f\circ\pi’\circ\pi\circ\phi$だから,
\begin{align*}g^*(f)=f\circ g=f\circ\pi’\circ\pi\circ\phi=f_*\end{align*}
が成り立つから,$g^*$は全単射である.
(2)の解答
(1)の記号を踏襲する.$W=\R$とすると,(1)と次元定理を併せて
\begin{align*}\dim{S}&=\dim{L(S,\R)}=\dim{A(V,V’,\R)}=\dim{\Ker{\rho}}
\\&=\dim{B(V,\R)}-\dim{\Ima{\rho}}=\dim{B(V,\R)}-\dim{B(V’,\R)}\end{align*}
が成り立つ.$V\neq\{0\}$とし,$V$の基底$(\m{v}_1,\dots,\m{v}_n)$をひとつとると,$f\in B(V,\R)$は対称双線形だから$f(\m{v}_i,\m{v}_j)$($1\le i\le j\le n$)の値を決めればただ一つに定まるので,
\begin{align*}\dim{B(V,\R)}=\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}\end{align*}
である.同様に$\dim{B(V’,\R)}=\frac{m(m+1)}{2}$だから,
\begin{align*}\dim{S}=\frac{n(n+1)-m(m+1)}{2}\quad\dots(*)\end{align*}
を得る.一方,$V=\{0\}$なら$\dim{B(V,\R)}=\dim{B(V’,\R)}=0$だから$\dim{S}=0$であり,$n=m=0$なので,この場合は$(*)$に含まれる.
第5問:位相空間論
$X$, $Y$を位相空間とし,$f:X\to Y$を次の条件(a), (b)をともに満たす写像とする.
- $f$は単射である.
- $X$の任意のコンパクト部分集合$K$に対し,その像$f(K)$は$Y$のコンパクト部分集合である.
以下の問に答えよ.
- このような$X$, $Y$と$f$であって,$f$が連続でない例を挙げよ.
- $X$と$Y$がともに距離空間であるならば$f$は連続であることを示せ.
一般の連続写像がコンパクト集合をコンパクト集合に移すことはよく知られています.本問(2)は距離空間上の単射なら逆が成り立つことを示す問題です.
解答の方針とポイント
(1)では$X$, $Y$が距離空間にとると(2)より$f$が連続となってしまうので,$X$, $Y$の少なくとも一方は距離空間でない位相を考える必要があります.(2)ではコンパクト空間と距離空間に関する写像の性質を使うことで解けます.
位相空間上のコンパクト集合
位相空間$X$に対して,$A\subset X$がコンパクトであるとは,$A$の任意の開被覆から$A$の有限被覆がとれることをいう.
「$A$の任意の開被覆から有限被覆がとれる」とは,言い換えると,$A\subset\bigcup\limits_{\lambda\in\Lambda}O_\lambda$を満たす$\{O_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$に対して,ある$\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n\in\Lambda$が存在して$A\subset\bigcup\limits_{i=1}^{n}O_{\lambda_i}$が成り立つことをいいますね.
$X$が有限集合であれば,$X$がどんな位相が備わっていても,任意の$A\subset X$の開被覆はそもそも必ず有限被覆なので$A$はコンパクトになりますね.
一般に$X$の位相が弱く$Y$の位相が強いほど写像$f:X\to Y$は連続になりやすいのですから,有限集合でそのような例を考えれば(1)が解けそうですね.
また,位相空間$X$に対して,$X$全体がコンパクトであるとき,位相空間$X$をコンパクト空間といい,次が成り立ちますね.
コンパクト空間$X$に対して,任意の閉集合$A\subset X$はコンパクトである.
ハウスドルフ空間とコンパクト集合(コンパクト空間)
ユークリッド空間上ではコンパクトであることと有界閉であることは同値でした(ハイネ-ボレルの定理)が,任意の位相空間で類似のことが成り立つわけではなくある程度の分離公理を満たしていないとコンパクト集合は閉ですらありません.
このコンパクト集合の閉性について,位相空間がハウスドルフであれば(第2分離公理を満たしていれば)次が成り立ちますね.
位相空間$X$がハウスドルフなら,$X$の任意のコンパクト部分集合は閉集合である.
距離空間はハウスドルフ空間なので,距離空間上のコンパクト部分集合は閉集合です.
したがって,コンパクト空間$X$がハウスドルフなら,$X$の部分集合が閉であることとコンパクトであることは同値ですね.
また,この定理とコンパクト集合の連続像がコンパクトであることを併せて,次の系が得られることも当たり前にしておきましょう.
コンパクト空間$X$とハウスドルフ空間$Y$に対して,連続写像$f:X\to Y$は閉写像である.
この系の有用な点は,$f$が全単射なら逆写像$f^{-1}$が(存在して)連続となるところです.そのため,この系は連続写像の逆写像が連続であることを示す際にも使えることを意識しておくとよいでしょう.
距離空間上の連続写像
距離空間上の写像の連続性は点列の収束を用いて,次のように特徴付けることもできますね.
距離空間$X$, $Y$と写像$f:X\to Y$に対して,次は同値である
- $f$は連続である
- 任意の$a\in X$と$a$に収束する$X$上の任意の点列$\{x_n\}$に対して,$Y$上の点列$\{f(x_n)\}$が$f(a)$に収束する
写像が点列の収束を保存することと,$f$が連続であることは同値というわけですね.
よって,本問(2)では任意の$a\in X$と$a$に収束する任意の点列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset X$をとり,点列$\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}\subset Y$が$f(a)$に収束することを示せばよいですね.
任意の$a\in X$と$a$に収束する任意の点列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset X$に対して,
\begin{align*}K:=\{a\}\cup\set{x_n}{n=1,2,\dots}\end{align*}
は$X$のコンパクト部分集合ですから,問題の仮定(b)より$f(K)$もコンパクトです.
さらに,$K$と$f(K)$をそれぞれ$X$と$Y$の部分位相空間とすると,$f$の終集合を$f(K)$に制限した$g:K\to f(K);x\mapsto f(x)$は仮定(a)より全単射かつ閉写像ですから,逆写像$g^{-1}$が存在して連続と分かります.
よって,上でみた系により$g$の連続性が分かり,$f$の連続性が得られますね.
解答例
(1)の解答
$X=Y=\{1,2\}$, $f$を恒等写像とし,$X$に密着位相,$Y$に離散位相を導入すると,$f$は(a), (b)の条件を満たすが連続でない.
実際,$f(1)\neq f(2)$より$f$は単射だから(a)が成り立ち,$Y$は有限集合だから$Y$の任意の部分集合はコンパクト部分集合なので(b)が成り立つ.
また,$\{1\}\subset Y$は開であるが,その$f$による引き戻し$f^{-1}(\{1\})=\{1\}\subset X$は開でないから,$f$は連続でない.
(2)の解答
$X$の距離を$d$とする.任意に$a\in X$をとる.$a$に収束する$X$上の任意の点列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$をとり,
\begin{align*}K:=\{a\}\cup\set{x_n}{n=1,2,\dots}\end{align*}
とおく.ここで,$K$の任意の開被覆$\{O_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$をとる.ある$\lambda_a\in\Lambda$が存在して,$a\in O_{\lambda_a}$が成り立ち,$O_{\lambda_a}$は開だから,ある$\epsilon>0$が存在して
\begin{align*}\set{x\in X}{d(a,x)<\epsilon}\subset O_{\lambda_a}\end{align*}
が成り立つ.$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$だから,ある$N\in\N$が存在して,$n>N$なら$d(a,x_n)<\epsilon$が成り立つ.また,任意の$i\in\{1,2,\dots,N\}$に対して,ある$\lambda_i\in\Lambda$が存在して$x_i\in O_{\lambda_i}$が成り立つ.
このとき,$\{O_{\lambda_a}\}\cup\set{O_{\lambda_i}}{i=1,2,\dots,N}$は$K$の有限被覆だから,$K$はコンパクトである.
ここで,$K$と$f(K)$はそれぞれ$X$と$Y$の部分位相空間と考える.このとき,仮定(b)より$f(K)$もコンパクトである.$K$も$f(K)$のコンパクト空間でハウスドルフ(距離空間)なので,部分集合が閉であることとコンパクトであることが同値であることに注意する.
写像$g:K\to f(K);x\mapsto f(x)$をとる.仮定(a)より$g$は全単射なので逆写像$g^{-1}$が存在する.任意のコンパクト(閉)集合$A\subset K$に対して,仮定(b)より$g(A)$はコンパクト(閉)だから$g^{-1}$は連続である.
よって,$g^{-1}$はコンパクト空間$f(K)$から距離空間(ハウスドルフ空間)$K$への閉写像だから,$g$は連続と分かり
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\lim_{n\to\infty}g(x_n)=g(a)=f(a)\end{align*}
が成り立つ.これより,$f$は$a$で連続なので,$a$の任意性より$f$は$X$上連続である.
第6問:複素解析学
$\Delta=\set{z\in\C}{|z|<1}$を複素平面内の単位円板とする.$z\in\Delta$の実数値関数
\begin{align*}v(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{\cos{t}-2}{4\cos{t}-5}\cdot\frac{-2r\sin{(t-\theta)}}{1+r^2-2r\cos{(t-\theta)}}\,dt\end{align*}
を考える.ただし,$z=re^{i\theta}$($0\le r<1$, $0\le\theta<2\pi$)の表示を用いた.以下の問に答えよ.
- $z\in\Delta$, $0\le t<2\pi$とする.$\dfrac{e^{it}+z}{e^{it}-z}$の虚部は\begin{align*}\frac{-2r\sin{(t-\theta)}}{1+r^2-2r\cos{(t-\theta)}}\end{align*}であることを示せ.
- $\C$上の有理型関数$f(z)$で,$\Delta$上で$f(z)$の虚部が$v(z)$となるものを一つ求めよ.
与えられた実数値関数$v$に対して,$\operatorname{Im}{f}=v$となる有理型関数$f$を見つける問題です.
解答の方針とポイント
(1)は計算すれば解けます.(2)は積分の形から$\C$上の単位円周上の複素積分に書き換える方針が見えます.
$[0,2\pi]$上の積分を円周上の複素積分に変換する
(1)より
\begin{align*}v(z)&=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{\cos{t}-2}{4\cos{t}-5}\cdot\bra{\operatorname{Im}\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}}\,dt
\\&=\operatorname{Im}\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{\cos{t}-2}{4\cos{t}-5}\cdot\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}\,dt\end{align*}
となるので,積分
\begin{align*}I(z):=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{\cos{t}-2}{4\cos{t}-5}\cdot\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}\,dt\end{align*}
を計算して有理型関数になれば,それが求める関数$f$ですね.
さて,複素関数$F$と$\alpha\in\C$, $r>0$に対して,複素積分$\int_{0}^{2\pi}F(\alpha+re^{it})\,dt$を$\zeta=\alpha+re^{it}$とおいて
\begin{align*}\int_{0}^{2\pi}F(\alpha+re^{it})\,dt
=\int_{\{|\zeta-\alpha|=r\}}\frac{F(\zeta)}{i(\zeta-\alpha)}\,d\zeta\end{align*}
と書き換えることはよくありますね.$I(z)$は$\zeta=e^{it}$とおけば
\begin{align*}I(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\Delta}\frac{(\zeta^2-4\zeta+1)(\zeta+z)}{2\zeta(2\zeta-1)(\zeta-2)(\zeta-z)}\,d\zeta\end{align*}
となります.
留数定理により円周上の複素積分が計算できる
いま$I(z)$の積分の被積分関数は単位円周$\partial\Delta$上で連続で,単位円内部$\Delta$では0と1/2と$z$を極としてもち($z\neq0,\frac{1}{2}$のとき),これらの点を除いた領域上では正則ですね.このような場合は留数定理が使えます.
[留数定理]領域$D$内に有限個の点$\alpha_{1},\dots,\alpha_n$があり,$D$内の閉曲線$C$がこれらの点を内部に含むとする.このとき,領域$D\setminus\{\alpha_{1},\dots,\alpha_n\}$上の正則関数$f$に対して
\begin{align*}\int_{C}f(z)\,dz=2\pi i\mathrm{Res}(f,\alpha_{1})+\dots+2\pi i\mathrm{Res}(f,\alpha_n)\end{align*}
が成り立つ.ただし,$C$の向きは正方向とする.
よって,被積分関数の0と1/2と$z$での留数を求めて併せれば$I(z)$が得られますね.
ただし,$z=0,\frac{1}{2}$のときは2位の極が現れるので議論を分ける必要がありますが,$I$は$\Delta$上連続なので$z=0,\frac{1}{2}$の場合をわざわざ計算する必要はありませんね.
解答例
(1)の解答
分母と分子に$e^{it}-z$の複素共役をかけて
\begin{align*}\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}
&=\frac{(e^{it}+z)(e^{-it}-\overline{z})}{|e^{it}-z|^2}
\\&=\frac{1-\overline{z}e^{it}+ze^{-it}-|z|^2}{|e^{it}-z|^2}\end{align*}
である.分母は
\begin{align*}|e^{it}-z|^2&=|e^{it}|^2+|z|^2-2\operatorname{Re}\overline{z}e^{it}
\\&=1^2+r^2-2r\operatorname{Re}e^{i(t-\theta)}
\\&=1+r^2-2r\cos{(t-\theta)}\end{align*}
であり,分子の虚部は
\begin{align*}\operatorname{Im}(ze^{-it}-\overline{z}e^{it})
&=\operatorname{Im}\bra{r(e^{-i(t-\theta)}-e^{i(t-\theta)})}
\\&=-2r\sin{(t-\theta)}\end{align*}
である.よって,
\begin{align*}\operatorname{Im}\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}=\frac{-2r\sin{(t-\theta)}}{1+r^2-2r\cos{(t-\theta)}}\end{align*}
を得る.
(2)の解答
単位円周$\partial\Delta$の向きを正方向で定める.任意の$z\in\Delta$に対して,
\begin{align*}I(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{\cos{t}-2}{4\cos{t}-5}\cdot\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}\,dt\end{align*}
とおくと,(1)より
\begin{align*}v(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{\cos{t}-2}{4\cos{t}-5}\cdot\bra{\operatorname{Im}\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}}\,dt
=\operatorname{Im}I(z)\end{align*}
が成り立つ.ここで,$\zeta=e^{it}$とおくと,$\frac{d\zeta}{dt}=i\zeta$であり,
\begin{align*}\frac{\cos{t}-2}{4\cos{t}-5}
&=\frac{\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}-2}{4\cdot\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}-5}
=\frac{\zeta+\overline{\zeta}-4}{2(2\zeta+2\overline{\zeta}-5)}
\\&=\frac{\zeta^2-4\zeta+1}{2(2\zeta^2-5\zeta+2)}
=\frac{\zeta^2-4\zeta+1}{2(2\zeta-1)(\zeta-2)}\end{align*}
である.よって,
\begin{align*}I(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\Delta}\frac{(\zeta^2-4\zeta+1)(\zeta+z)}{2\zeta(2\zeta-1)(\zeta-2)(\zeta-z)}\,d\zeta\end{align*}
となる.この被積分関数を$F$とする.$F$は$\partial\Delta$上連続である.
$z\neq0,\frac{1}{2}$のとき,$F$は$\Delta$上に極0と1/2と$z$をもち,
\begin{align*}&\mathrm{Res}(F,0)=\lim_{\zeta\to0}\zeta F(\zeta)
\\&=\frac{(0-0+1)(0+z)}{2(0-1)(0-2)(0-z)}=-\frac{1}{4},
\\&\mathrm{Res}\bra{F,\frac{1}{2}}=\lim_{\zeta\to\frac{1}{2}}\bra{\zeta-\frac{1}{2}}F(\zeta)
\\&=\frac{(\frac{1}{4}-2+1)(\frac{1}{2}+z)}{2\cdot2\cdot\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-2)(\frac{1}{2}-z)}=\frac{1+2z}{4(1-2z)}
\\&\mathrm{Res}(F,z)=\lim_{\zeta\to z}(\zeta-z)F(\zeta)
\\&=\frac{(z^2-4z+1)\cdot2z}{2z(2z-1)(z-2)}=\frac{z^2-4z+1}{(2z-1)(z-2)}\end{align*}
なので,留数定理より
\begin{align*}I(z)&=-\frac{1}{4}+\frac{1+2z}{4(1-2z)}+\frac{z^2-4z+1}{(2z-1)(z-2)}
\\&=-\frac{1}{4}-\frac{-(1+2z)(z-2)+4(z^2-4z+1)}{4(2z-1)(z-2)}
\\&=-\frac{1}{4}+\frac{2z^2-13z+6}{4(2z-1)(z-2)}=-\frac{1}{4}+\frac{z-6}{4(z-2)}
\\&=-\frac{1}{z-2}=\frac{1}{2-z}\end{align*}
を得る.$\frac{1}{2-z}$は$\Delta$上正則なので,一致の定理より任意の$z\in\Delta$に対して$I(z)=\frac{1}{2-z}$が成り立つ.
以上より,$\Delta$上で虚部が$v(z)$となる有理型関数$f$として
\begin{align*}f(z)=I(z)=\frac{1}{2-z}\end{align*}
が挙げられる.
補足(ポアソン核とコーシー核)
$r\in(0,1)$をパラメーターとする関数
\begin{align*}P_r:[0,2\pi]\to\C;\theta\mapsto\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}r^{|n|}e^{in\theta}\end{align*}
はポアソン核と呼ばれ,この級数で$n\ge0$のみ考えてできる関数
\begin{align*}C_r:[0,2\pi]\to\C;\theta\mapsto\frac{1}{2\pi}\sum_{n=0}^{\infty}r^{n}e^{in\theta}\end{align*}
はコーシー核と呼ばれます.コーシー核について
\begin{align*}2C_r-\frac{1}{2\pi}=\frac{2}{2\pi(1-re^{i\theta})}-\frac{1}{2\pi}=\frac{1+re^{i\theta}}{2\pi(1-re^{i\theta})}\end{align*}
となるので,$2C_r-\frac{1}{2\pi}$と,$[0,2\pi]$上で定義された関数$g$の合成積は
\begin{align*}\bra{2C_r-\frac{1}{2\pi}}*g(\theta)&=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{1+re^{i(\theta-t)}}{1-re^{i(\theta-t)}}g(t)\,dt
\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{e^{it}+re^{i\theta}}{e^{it}-re^{i\theta}}g(t)\,dt\end{align*}
となり,$g(t)=\frac{\cos{t}-2}{4\cos{t}-5}$としたものが本問題の$f$ですね.
$z\in\Delta$は$z=re^{i\theta}$と表せることに注意してください.
ポアソン核$P_r$との合成積はポアソン積分と呼ばれており,$g\in L^p(0,2\pi)$($p\in[1,\infty)$)の合成積$P_r*g$は
\begin{align*}\lim_{r\to1-0}\|P_r*g-g\|_{L^p(0,2\pi)}=0\end{align*}
を満たします.すなわち,ポアソン積分$P_r*g$はもとの関数$g$の$L^p$における近似になっているわけですね.
一方,コーシー核$C_r$との合成積$C_r*g$は,コーシー核の定義から推察されるように$g$のフーリエ係数の$n\ge0$の部分だけを近似するものになっており,これはポアソン積分$P_r*g$の「正則部分」だけを取り出すものになります.よって,$\bra{2C_r-\frac{1}{2\pi}}*g$も正則関数となります.
実際,得られた有理型関数$f:\Delta\to\C$は$\Delta$上の正則関数になっていますね.
ポアソン積分について,詳しくは例えば以下の文献を参照してください.
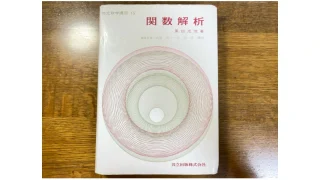
第7問:微分方程式
正の実数全体の集合上で定義された実数値$C^1$級関数$y(x)$で,微分方程式
\begin{align*}y’=\frac{y^2}{x}+y-\frac{1}{x}\quad(x>0)\end{align*}
を満たすものを考える.
- $w(x)=y(x)-(1-x)$とおく.$w(x)$の満たす微分方程式を導け.
- (1)で求めた微分方程式を解くことにより,$y(x)$をすべて求めよ.
- $\limsup\limits_{x\to\infty}|y(x)|<\infty$となる$y(x)$をすべて求めよ.
常微分方程式を解き,$|y(x)|$の$x\to\infty$での上極限が発散しない条件を求める問題です.
解答の方針とポイント
(1)は単に置き換えればよく,これで$w$のベルヌーイの微分方程式となるので(2)が解けます.(3)は解の形から単純に極限が計算できるので解けます.
1階線形常微分方程式の解法
未知関数$u$,変数$x$で$u'(x)+a(x)u(x)=b(x)$の形をした微分方程式を1階線形常微分方程式といいます.
関数$p$を関数$a$の原始関数の1つとするとき,微分方程式の両辺に$e^{p(x)}$をかけることで
\begin{align*}&e^{p(x)}u'(x)+e^{p(t)}a(x)u(x)=e^{p(x)}b(x)
\\&\iff\bra{e^{p(x)}u(x)}’=e^{p(x)}b(x)
\iff e^{p(x)}u(x)=\int e^{p(x)}b(x)\,dx
\\&\iff u(x)=e^{-p(x)}\int e^{p(x)}b(x)\,dx\end{align*}
と解けます.
積分因子$e^{p(t)}$をかけて左辺を完全微分形にして解いたということもできますね.
ベルヌーイの微分方程式は1階線形に帰着させる
2以上の整数$n$に対して,未知関数$w$,変数$x$で$w'(x)+a(x)w(x)=b(x)w(x)^n$の形をした微分方程式をベルヌーイの微分方程式といいます.
($w\neq0$のとき)この常微分方程式は$u=w^{1-n}$とおくことで,1階線形常微分方程式に帰着します.実際,$w’=\frac{u’w^n}{1-n}$, $w=uw^n$なので
\begin{align*}&\frac{u'(x)w(x)^n}{1-n}+a(x)u(x)w(x)^n=b(x)w(x)^n
\\&\iff \frac{u'(x)}{1-n}+a(x)u(x)=b(x)\end{align*}
となりますね.よって,このあと1階線形常微分方程式の解法で解が得られますね.
解答例
(1)の解答
$y(x)=w(x)+1-x$なので,
\begin{align*}&w’-1=\frac{w^2+1+x^2+2w-2x-2xw}{x}+(w+1-x)-\frac{1}{x}
\\&\iff w’=\frac{w^2+2w-xw}{x}
\iff w’=\frac{w(w+2-x)}{x}\end{align*}
を得る.
(2)の解答
$w\equiv0$のとき(1)の微分方程式は両辺とも0となるので,$w\equiv0$は解である.
以下,$w\not\equiv0$とする.(1)の微分方程式の右辺は$w$について局所的にリプシッツ連続だから,解の一意性より任意の$x>0$に対して$w(x)\neq0$である.
$u=\frac{1}{w}$とおくと,(1)の微分方程式は
\begin{align*}&-\frac{u’}{u^2}=\frac{\frac{1}{u}(\frac{1}{u}+2-x)}{x}
\\&\iff u’+\bra{\frac{2}{x}-1}u=-\frac{1}{x}\end{align*}
である.両辺に$x^2e^{-x}$をかけて
\begin{align*}&x^2e^{-x}u’+(2-x)xe^{-x}u=-xe^{-x}
\\&\iff(x^2e^{-x}u)’=-xe^{-x}\end{align*}
が成り立つから,両辺を$x$で積分して
\begin{align*}&x^2e^{-x}u=(x+1)e^{-x}+C
\\&\iff u=\frac{x+1+Ce^x}{x^2}\end{align*}
を得る($C\in\R$は任意定数).以上より,$y(x)=\frac{1}{u(x)}+1-x$と併せて,
\begin{align*}y(x)=1-x,\ \frac{x^2}{x+1+Ce^x}+1-x\end{align*}
が解である.
(3)の解答
$y(x)=1-x$のとき,$\lim\limits_{x\to\infty}|y(x)|=\infty$となり条件を満たさない.以下,$y(x)=\frac{x^2}{x+1+Ce^x}+1-x$とする.
$C\neq0$のとき,$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x+1+Ce^x}=0$なので,
\begin{align*}|y(x)|&=\abs{\frac{x^2}{x+1+Ce^x}+1-x}
\\&\ge|1-x|-\abs{\frac{x^2}{x+1+Ce^x}}\xrightarrow[]{x\to\infty}\infty\end{align*}
となり条件を満たさない.$C=0$のとき,
\begin{align*}y(x)&=\frac{x^2}{x+1}+1-x=\bra{x-1+\frac{1}{x+1}}+1-x
\\&=\frac{1}{x+1}\xrightarrow[]{x\to\infty}0\end{align*}
となり条件を満たす.
以上より,求める解は$y(x)=\frac{1}{x+1}$である.
参考文献
基礎を固めるために私が実際に使ったオススメの入試問題集を挙げておきます.
詳解と演習大学院入試問題〈数学〉
[海老原円,太田雅人 共著/数理工学社]
理工系の修士課程への大学院入試問題集ですが,基礎〜標準的な問題が広く大学での数学の基礎が復習できる総合問題集として利用することができます.
実際,まえがきにも「単なる入試問題の解説にとどまらず,それを通じて,数学に関する読者の素養の質を高めることにある」と書かれているように,必ずしも大学院入試を受験しない一般の学習者にとっても学びやすい問題集です.また,構成が読みやすいのも個人的には嬉しいポイントです.
第1章 数え上げと整数
第2章 線形代数
第3章 微積分
第4章 微分方程式
第5章 複素解析
第6章 ベクトル解析
第7章 ラプラス変換
第8章 フーリエ変換
第9章 確率
一方で,問題数はそれほど多くないので,多くの問題を解きたい方には次の問題集もオススメです.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|詳解と演習 大学院入試問題(数理工学社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.
演習 大学院入試問題
[姫野俊一,陳啓浩 共著/サイエンス社]
上記の問題集とは対称的に問題数が多く,まえがきに「修士の基礎数学の問題の範囲は,ほぼ本書中に網羅されている」と書かれているように,広い分野から問題が豊富に掲載されています.
全2巻で,
1巻第1編 線形代数
1巻第2編 微分・積分学
1巻第3編 微分方程式
2巻第4編 ラプラス変換,フーリエ変換,特殊関数,変分法
2巻第5編 複素関数論
2巻第6編 確率・統計
が扱われています.
地道にきちんと地に足つけた考え方で解ける問題が多く,確かな「腕力」がつくテキストです.入試では基本問題は確実に解けることが大切なので,その意味で試験への対応力が養われると思います.
なお,私自身は受験生時代に計算力があまり高くなかったので,この本の問題で訓練したのを覚えています.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|演習 大学院入試問題[数学](サイエンス社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.
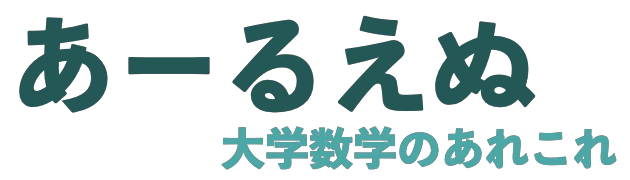
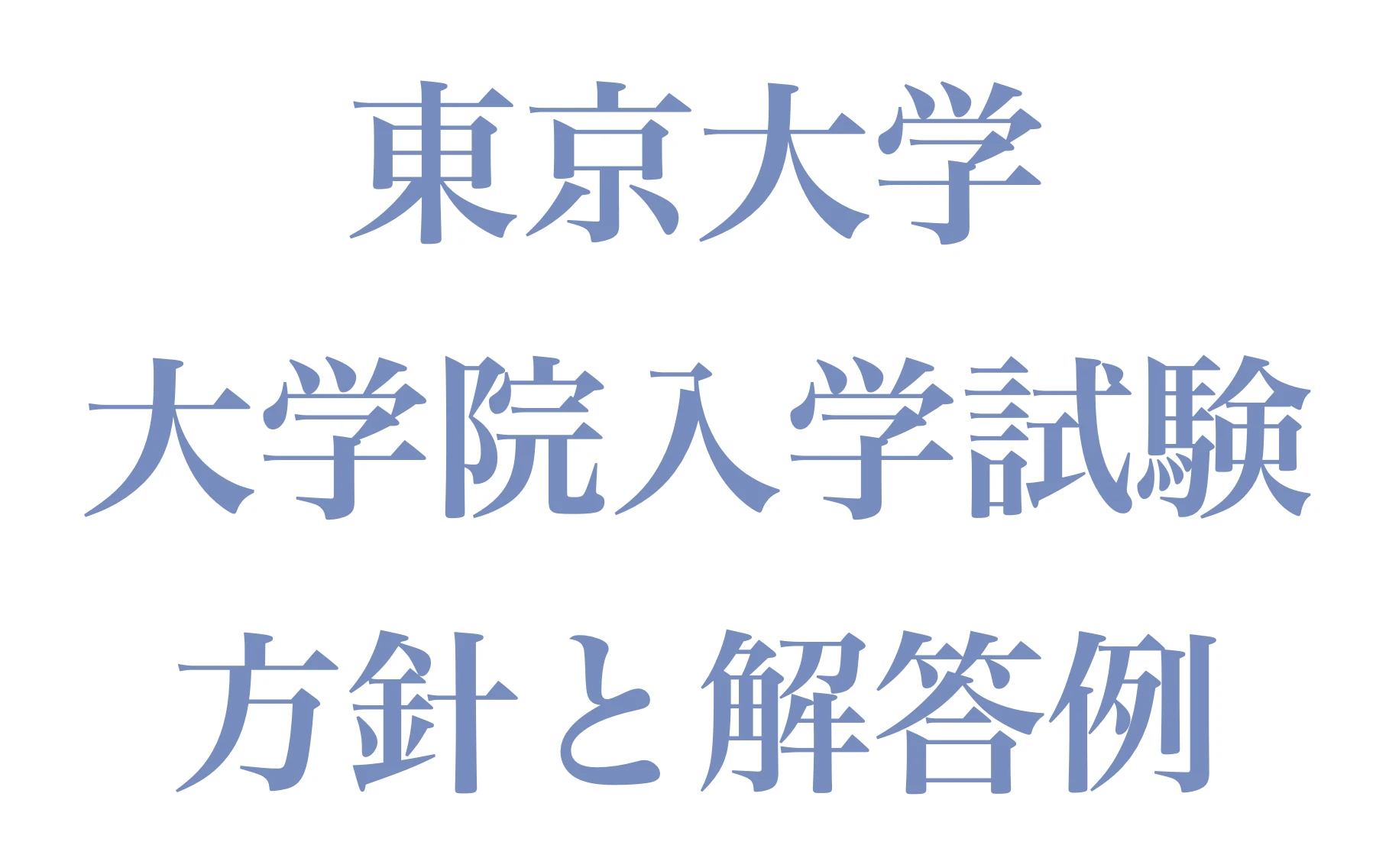


コメント