2025年度の東京大学 数理科学研究科の大学院入試問題の専門科目Bの解答の方針と解答例です.
問題は18題あり,選択して3題を解答します.試験時間は4時間です.この記事では,第9,11,12問について解説しています.
ただし,公式に採点基準などは発表されていないため,本稿の解答が必ずしも正解になるとは限りません.ご注意ください.
また,十分注意して解答を作成していますが,論理の飛躍・誤りが残っている場合があります.
なお,最近の過去問は東京大学の数理科学研究科のホームページから入手できます.
第9問(ルベーグ積分)
$\R$上の実数値ルベーグ可測関数$f$は,任意の$R>0$に対し
\begin{align*}\int_{|x|\le R}|f(x)|\,dx<\infty\end{align*}
を満たすとする.このとき,以下の二つの条件(1)と(2)は同値であることを示せ.ただし,$C_0(\R)$は$\R$上の実数値連続関数で台がコンパクトなもの全体の集合を表すとする.
- $f$は$\R$上でルベーグ可積分である.
- 任意の実数値関数の列$a_n\in C_0(\R)$($n=1,2,\dots$)で任意の$x\in\R$において
\begin{align*}\sup_{n\ge1}|a_n(x)|\le1,\quad\lim_{n\to\infty}a_n(x)=1\end{align*}
を満たすものに対して,
\begin{align*}\limsup_{n\to\infty}\abs{\int_{\R}a_n(x)f(x)\,dx}<\infty\end{align*}
が成り立つ.
局所可積分であるような$f$について,$f$がルベーグ可積分であるための必要十分条件を示す問題です.
解答の方針とポイント
同値であることの証明なので(1)⇒(2)と(2)⇒(1)の両方を示します.(1)⇒(2)の証明はほとんど当たり前で,難しいのは(2)⇒(1)の証明です.
また,(2)⇒(1)の証明でも$f$が非負値関数や非正値関数の場合は簡単です.難しいのは$f$が遠方で正負を行ったり来たりするような関数なので,このような関数についてうまくいくように試行錯誤することが大切です.
(2)⇒(1)の対偶を示す
(2)⇒(1)が成り立つということはこの対偶も成り立つので,$\R$上ルベーグ積分不可能な関数$f$に対して,(2)の$\{a_n\}$の条件と
\begin{align*}\limsup_{n\to\infty}\abs{\int_{\R}a_n(x)f(x)\,dx}=\infty\quad\dots(*)\end{align*}
を満たす関数列$\{a_n\}$をとることができるはずですね.
そこで,どのように関数列$\{a_n\}$をとればよいか,しばらく$f(x)=\frac{\sin{x}}{x}$として方針を考えることにしましょう.
$\frac{\sin{x}}{x}$は任意の$R>0$に対して有界閉区間$[-R,R]$上で連続なので局所可積分の条件
\begin{align*}\int_{|x|\le R}|f(x)|\,dx<\infty\end{align*}
は満たしており,$\int_{\R}\frac{\sin{x}}{x}\,dx$はルベーグ積分不可能です.
広義積分の意味では$\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{x}}{x}\,dx=\frac{\pi}{2}$と積分可能で,ディリクレ積分と呼ばれていることも思い出しておきましょう.
試行錯誤して関数列$\{a_n\}$を構成する(ステップ1)
(2)の$\{a_n\}$の条件を満たす関数列$\{a_n\}$で単純に思い付くものは,$|x|\le n$で値1をとり,$|x|\ge 2n$で値0をとり,$n<|x|<2n$で0と1の間の値をとるような連続関数$a_n$です.
この関数列$\{a_n\}$は,条件
\begin{align*}\sup_{n\ge1}|a_n(x)|\le1,\quad\lim_{n\to\infty}a_n(x)=1\end{align*}
を満たしますが,$f(x)=\frac{\sin{x}}{x}$に対して
\begin{align*}&\abs{\int_{\R}a_n(x)f(x)\,dx}
\\&\le\abs{\int_{-n}^{n}\frac{\sin{x}}{x}\,dx}+\int_{n<|x|<2n}\frac{1}{|x|}\,dx
\\&\le\abs{\int_{-n}^{n}\frac{\sin{x}}{x}\,dx}+2\log{2}
\\&\xrightarrow[]{n\to\infty}\pi+2\log{2}\end{align*}
となり上極限の発散$(*)$は成り立ちません.
試行錯誤して関数列$\{a_n\}$を構成する(ステップ2)
ステップ1で上極限の発散$(*)$が成り立たなかったのは$f(x)=\frac{\sin{x}}{x}$の正成分も負成分も一緒にして考えたことが原因になっています.
つまり,ルベーグ積分は「正成分と負成分をそれぞれ積分して差をとる」と定義されるので,$f$の正成分も負成分も併せて積分するような$a_n$ではうまくいかなかったわけですね.
一方,広義積分は$[-R,R]$上のリーマン積分したものの極限なので,ディリクレ積分
\begin{align*}\int_{0}^{\infty}\frac{\sin{x}}{x}\,dx=\lim_{R\to\infty}\int_{0}^{R}\frac{\sin{x}}{x}\,dx=\frac{\pi}{2}\end{align*}
は$R$を大きくするにつれて正負が打ち消し合って,広義積分としてはうまく収束するわけですね.
そこで,$E=\set{x\in\R}{f(x)>0}$とすると
\begin{align*}\int_{-\infty}^{\infty}\mathbb{I}_{E}(x)f(x)\,dx=\infty\end{align*}
となりますから,これを利用すれば上極限の発散$(*)$が成り立つようにできそうです($\mathbb{I}_{E}$は集合$E$の定義関数).
試行錯誤して関数列$\{a_n\}$を構成する(ステップ3)
ステップ1とステップ2を組み合わせると,
- $|x|\le2n$(原点付近)ではステップ1のように「ベッタリ」1に収束する関数
- $3n\le|x|$(空間遠方)ではステップ2のように$f$の正成分を拾って積分$\abs{\int_{3n\le|x|}a_n(x)f(x)\,dx}$が大きくなる
ような$a_n\in C_0(\R)$を考えると良さそうです.すなわち,
- $|x|\le n$なら$\psi_n(x)=1$で,$|x|\ge 2n$なら$\psi_n(x)=0$が成り立つ関数$\psi_n:\R\to[0,1]$
- $|x|<3n$なら$\phi_n(x)=0$で,$3n\le|x|$で\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\phi_n(x)f(x)\,dx\end{align*}が十分大きくなる関数$\phi_n:\R\to[0,1]$
を$C_0(\R)$で定め,関数$a_n:\R\to\R$を$a_n(x)=\psi_n(x)+\phi_n(x)$と定めると(2)の$\{a_n\}$の条件を満たし,上極限の発散$(*)$を満たすことになりますね.
一般の$f$に対する関数列$\{a_n\}$の構成
以上の$f(x)=\frac{\sin{x}}{x}$の場合の関数列$\{a_n\}$の構成から,一般のルベーグ積分不可能なルベーグ可測関数$f$に対しては,次のように関数列$\{a_n\}$を構成すれば良さそうです.
$f$がルベーグ積分不可能なら,$f$の正成分の積分または$f$の負成分の積分が無限大になっています.どちらでも証明は同様なので,$f$の正成分の積分が無限大になっているとします.
先ほどと同様に,$|x|\le n$なら$\psi_n(x)=1$で,$|x|\ge 2n$なら$\psi_n(x)=0$が成り立つ連続関数$\psi_n:\R\to[0,1]$をとります.$f(x)=\frac{\sin{x}}{x}$の場合は
\begin{align*}\int_{\R}\psi_n(x)f(x)\,dx\end{align*}
は有限の値をとりますが,一般の$f$の場合は絶対値が大きい負の値をとるかもしれません.そこで,この積分の値に対して
\begin{align*}\int_{\R}\phi_n(x)f(x)\,dx\end{align*}
が$f$の正成分を拾って十分大きくなるように,原点から離れた部分に台をもつ関数$\phi_n:\R\to[0,1]$をとる必要があります.
ただし,ルベーグ可測関数$f$は連続関数のような分かりやすい関数とは限らないので,測度の正則性とウリゾーンの補題を用いて$\phi_n$をとります.
解答例
(1)⇒(2)の証明
(1)が成り立つとする.このとき,$\int_{\R}|f(x)|\,dx<\infty$である.
また,任意の$x\in\R$において$\sup\limits_{n\ge1}|a_n(x)|\le1$と$\lim\limits_{n\to\infty}a_n(x)=1$を満たす任意の実数値関数列$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\subset C_0(\R)$をとる.このとき,任意の$n\in\N$に対して
\begin{align*}\abs{\int_{\R}a_n(x)f(x)\,dx}
&\le\int_{\R}|a_n(x)f(x)|\,dx
\\&\le\int_{\R}|f(x)|\,dx<\infty\end{align*}
なので,\begin{align*}\limsup_{n\to\infty}\abs{\int_{\R}a_n(x)f(x)\,dx}<\infty\end{align*}が成り立つ.
(2)⇒(1)の証明
対偶を示す.(1)が成り立たないとする.このとき,$f$の正成分と負成分をそれぞれ$f_+$, $f_-$とすると,$\int_{\R}f_+(x)\,dx=\infty$または$\int_{\R}f_-(x)\,dx=\infty$が成り立つ.
$\int_{\R}f_+(x)\,dx=\infty$が成り立つとする.
[1]実数値関数列$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\subset C_0(\R)$を構成する.
任意に$n\in\{1,2,\dots\}$をとる.$|x|\le 1$なら$\psi(x)=1$が成り立ち,$|x|\ge 2$なら$\psi(x)=0$が成り立つ連続関数$\psi:\R\to[0,1]$をとり,$\psi_n(x)=\psi(\frac{x}{n})$とおく.
$\int_{|x|\ge4n}f_+(x)\,dx=\infty$かつ,任意の$R>0$に対し$\int_{|x|\le R}|f(x)|\,dx<\infty$だから,
\begin{align*}R_n=\inf\set{R>0}{\int_{4n\le|x|\le R}f_+(x)\,dx\ge n+\int_{\R}\psi_n(x)|f(x)|\,dx}\end{align*}
が有限の実数として定まる.$\int_{4n\le|x|\le R}f_+(x)\,dx$は$R$について連続だから,この$\inf$で最小に達する.ルベーグ測度の内正則性より,ある閉集合
\begin{align*}K_n\subset\set{x\in\R}{4n\le|x|\le R_n,f(x)>0}\end{align*}
が存在して,
\begin{align*}\int_{K_n}f_+(x)\,dx=\int_{K_n}f(x)\,dx\ge n-1+\int_{\R}\psi_n(x)|f(x)|\,dx\end{align*}
が成り立つ.さらに,ルベーグ測度の外正則性と$[R_n-1,R_n+1]$上の$f$の可積分性より,ある開集合$U_n\supset K_n$が存在して,$U_n\subset\set{x\in\R}{4n-1\le|x|\le R_n+1}$かつ,
\begin{align*}\int_{U_n\setminus K_n}|f(x)|\,dx<1\end{align*}
が成り立つ.このとき,ウリゾーンの補題より,ある連続関数$\phi_n:\R\to[0,1]$が存在して,$x\in K_n$なら$\phi_n(x)=1$が成り立ち,$x\in U_n^c$なら$\phi_n(x)=0$が成り立つ.
以上のもとで,関数$a_n:\R\to\R$を$a_n(x)=\psi_n(x)+\phi_n(x)$と定める.
[2]$a_n\in C_0(\R)$であり,任意の$x\in\R$において$\sup\limits_{n\ge1}|a_n(x)|\le1$と$\lim\limits_{n\to\infty}a_n(x)=1$が成り立つことを示す.
任意の$n\in\{1,2,\dots\}$に対して,
\begin{align*}\operatorname{supp}a_n=\operatorname{supp}\psi_n\cup\operatorname{supp}\phi_n\subset[-(R_n+1),R_n+1]\end{align*}
だから,$a_n$はコンパクト台をもつ.$\operatorname{supp}\psi_n\cap\operatorname{supp}\phi_n=\emptyset$かつ$|\psi_n(x)|\le1$かつ$|\phi_n(x)|\le1$が成り立つので,
\begin{align*}\sup\limits_{n\ge1}|a_n(x)|=\sup\limits_{n\ge1}(\max\{|\psi_n(x)|,|\phi_n(x)|\})\le1\end{align*}
が成り立つ.
また,ある$N\in\N$が存在して$|x|\le N$となるので,$n>N$なら$|x|\le n$となり
\begin{align*}a_n(x)=\psi_n(x)=1\end{align*}
となり,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n(x)=1$が成り立つ.
[3]$\limsup\limits_{n\to\infty}\abs{\int_{\R}a_n(x)f(x)\,dx}=\infty$を示す.
任意の$n\in\{1,2,\dots\}$に対して,
\begin{align*}&\abs{\int_{\R}a_n(x)f(x)\,dx}
\\&=\abs{\int_{K_n}f(x)\,dx+\int_{U_n\setminus K_n}\phi_n(x)f(x)\,dx+\int_{\R}\psi_n(x)f(x)\,dx}
\\&\ge\int_{K_n}f_+(x)\,dx-\int_{U_n\setminus K_n}|f(x)|\,dx-\int_{\R}\psi_n(x)|f(x)|\,dx
\\&\ge n-2\xrightarrow[]{n\to\infty}\infty\end{align*}
となるから,$\limsup\limits_{n\to\infty}\abs{\int_{\R}a_n(x)f(x)\,dx}=\infty$が成り立つ.
[1]〜[3]より,(2)が成り立たないことが分かった.
一方,$\int_{\R}f_+(x)\,dx<\infty$が成り立つ場合は$\int_{\R}f_-(x)\,dx=\infty$だから,$f_-$に対して同様に$\phi_n$を考えれば,同様に(2)が成り立たない.
第11問(関数解析)
開区間$(-1,1)$上の関数$f(t)=\sqrt{1-t}$に対し,
\begin{align*}f(t)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n t^n\end{align*}
を$f$の$t=0$を中心とするテイラー展開とする.以下の問に答えよ.
- $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}|c_n|<\infty$を示せ.
- $\mathcal{H}$をヒルベルト空間とする.有界線型作用素$A:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$に対し,$\|A\|\le1$ならば,級数$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}c_nA^n$は作用素ノルムに関して収束することを示せ.ただし,$\|A\|$は$A$の作用素ノルムを表す.
- 実数列$x=(x_i)_{i=1}^{\infty}$で$\|x\|_{l^2}^2=\displaystyle\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|^2<\infty$を満たすもの全体をなす実ヒルベルト空間$l^2$を考える.ヒルベルト空間$l^2$上の等長作用素$T:l^2\to l^2$を
\begin{align*}Tx=(0,x_1,x_2,x_3,\dots),\quad x=(x_1,x_2,x_3,\dots)\in l^2\end{align*}
で定め,$B=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}c_nT^n$とする.$l^2$の単位ベクトルの列$\{v_k\}_{k=1}^{\infty}$で
\begin{align*}\lim_{k\to\infty}\|Bv_k\|_{l^2}=0\end{align*}
となる例を一つ与えよ.
メインは(3)で,有界作用素$B$に対して$\lim_{k\to\infty}\|Bv_k\|_{l^2}=0$となる単位ベクトルの列$\{v_k\}$をうまくとる問題です.
解答の方針とポイント
(1)は正項級数の収束判定ですが,基本的なコーシーの判定法・ダランベールの判定法ではうまくいきません.(2)は基本的な議論と(1)を併せて解けます.(3)は(2)の議論をふまえて,本質的には$n$の小さい項が重要であることに気付けるかがポイントです.
ガウスの判定法(正項級数の収束判定)
$c_n$は$f(t)=\sqrt{1-t}$のマクローリン展開の係数なので,$n\ge2$のとき
\begin{align*}|c_n|=\abs{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}}=\frac{(2n-3)!!}{n!2^n}\end{align*}
です.冪と階乗が含まれているので,ダランベールの判定法(ratioテスト)が良さそうですが
\begin{align*}\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}=\frac{2n-1}{2n+2}\xrightarrow[]{n\to\infty}1\end{align*}
なのでうまくいきません.しかし,ダランベールの判定法を精密にした次のガウスの判定法を用いるとうまくいきます.
[ガウスの判定法]正項級数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$に対して,$\delta>0$を用いて
\begin{align*}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1-\frac{k}{n}+O\bra{\frac{1}{n^{1+\delta}}}\quad(n\to\infty)\end{align*}
と表せるとする.このとき,正項級数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$は$k>1$なら収束し,$k\le1$なら発散する.
いまの場合は,$n\ge2$のとき
\begin{align*}\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}=1-\frac{3/2}{n}+\frac{3}{n(2n+2)}\end{align*}
なので,ガウスの判定法より$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}|c_n|<\infty$が得られます.
コーシーの条件
(2)では作用素の級数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nA^n$の作用素ノルムでの収束を示すわけですが,実際の極限まで求める必要はありません.
このような場合には,作用素ノルムについて$\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nA^n$がコーシー列になっていることを示せば良いですね(コーシーの条件).
極限に目星がついていなくても,コーシー列であることは示せる場合も多いです.これがコーシー列の良さなのでした.
任意の$\epsilon>0$に対して,十分大きな$p,q\in\N$($p>q$)をとれば,(1)より
\begin{align*}\nor{\sum_{n=q+1}^{p}c_nA^n}
&\le\sum_{n=q+1}^{p}|c_n|\|A^n\|
\\&\le\sum_{n=q+1}^{p}|c_n|<\epsilon\end{align*}
となるので,これでコーシーの条件を満たすことが分かりますね.
$N$が大きいときの$\sum\limits_{n=N}^{\infty}c_nT^nv_k$は小さい
(3)で示す$\lim\limits_{k\to\infty}\|Bv_k\|_{l^2}=0$について,
\begin{align*}Bv_k=\sum_{n=0}^{\infty}c_nT^nv_k\end{align*}
です.(2)の議論と同様に,任意の$\epsilon>0$に対して,十分大きな$N\in\N$をとれば,$\|T\|=1$と$\|v_k\|_{l^2}$と併せて
\begin{align*}\nor{\sum\limits_{n=N}^{\infty}c_nT^nv_k}_{l^2}\le\sum\limits_{n=N}^{\infty}|c_n|<\epsilon\end{align*}
となります.この評価は$v_k$が単位ベクトルであれば成り立つので,$v_k$の本質的な形は$\lim\limits_{k\to\infty}\nor{\sum\limits_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k}_{l^2}=0$となるようにとればよいことが分かります.
$f(0)=0$より$\sum\limits_{n=N}^{\infty}c_n=0$であることを用いる
$f(0)=0$より$\sum\limits_{n=N}^{\infty}c_n=0$ですから,
\begin{align*}\abs{\sum_{n=0}^{N-1}c_n}=\abs{-\sum_{n=N}^{\infty}c_n}<\epsilon\end{align*}
となることが分かります.$k>N$のとき$v_k$の初項から第$N$項まで全て等しく$r$とすると,
\begin{align*}\sum_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k=(rc_0,r(c_0+c_1),r(c_0+c_1+c_2),\dots)\end{align*}
となり,$\sum\limits_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k$の第$N$項は$r\sum\limits_{n=0}^{N-1}c_n$ですから,この第$N$項の絶対値は$|r|\epsilon$で上から評価できますね.
そこで,$v_k$が$l^2$の単位ベクトルとなるように
\begin{align*}v_k=\frac{1}{\sqrt{k}}(\underbrace{1,1,\dots,1}_{\text{$k$項}},0,0,\dots).\end{align*}
ととれば,$k>N$のとき$\sum\limits_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k$は第$N$項から第$k$項まで$\sum\limits_{n=0}^{N-1}\frac{c_n}{\sqrt{k}}$で一定となり,この第$N$項から第$k$項までの2乗和は
\begin{align*}(k-N+1)\abs{\sum_{n=0}^{N-1}\frac{c_n}{\sqrt{k}}}^2<\bra{1-\frac{N-1}{k}}\epsilon^2\end{align*}
と小さいことが分かります.
また,$k$が十分大きければ,第$N$項から第$k$項まで以外の0でない項は高々$N$項しかない上に$O(k^{-1})$なので,$k$を十分大きくすれば全体が0に収束することが分かります.
解答例
(1)の解答
任意の$n\in\{2,3,4,\dots\}$に対して,
\begin{align*}|c_n|&=\abs{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}}
\\&=\abs{\frac{1}{n!}\times\frac{-1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times\dots\times\frac{2n-3}{2}}
\\&=\frac{(2n-3)!!}{n!2^n}\end{align*}
だから,$n\in\{2,3,4,\dots\}$に対して
\begin{align*}&\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}=\frac{\frac{(2n-1)!!}{(n+1)!2^{n+1}}}{\frac{(2n-3)!!}{n!2^n}}=\frac{2n-1}{2n+2}
\\&=1-\frac{3/2}{n}+\frac{3}{n(2n+2)}
\\&=1-\frac{3/2}{n}+o\bra{\frac{1}{n^{3/2}}}\quad(n\to\infty)\end{align*}
なので,ガウスの判定法より$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}|c_n|<\infty$が成り立つ.
(2)の解答
任意に$\epsilon>0$をとる.(1)より,ある$N\in\N$が存在して,$\sum\limits_{n=N}^{\infty}|c_n|<\epsilon$が成り立つ.よって,$p>q\ge N$を満たす任意の$p,q\in\N$に対して,
\begin{align*}&\nor{\sum_{n=0}^{p}c_nA^n-\sum_{n=0}^{q}c_nA^n}=\nor{\sum_{n=q+1}^{p}c_nA^n}
\\&\le\sum_{n=q+1}^{p}|c_n|\|A\|^n\le\sum_{n=q+1}^{p}|c_n|<\epsilon\end{align*}
となるから,コーシーの条件より級数$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}c_nA^n$は作用素ノルムに関して収束する.
(3)の解答
任意の$k\in\N$に対して,$v_k$を初項から第$k$項まで$\frac{1}{\sqrt{k}}$で,第$k+1$項以降は0である実数列とする:
\begin{align*}v_k=\biggl(\underbrace{\frac{1}{\sqrt{k}},\frac{1}{\sqrt{k}},\dots,\frac{1}{\sqrt{k}}}_{\text{$k$項}},0,0,\dots\biggr).\end{align*}
このとき,列$\{v_k\}$が$l^2$上の列で条件を満たすことを以下で示す.
任意の$k\in\{1,2,\dots\}$に対して,
\begin{align*}\|v_k\|_{l^2}^2=\sum_{n=1}^{k}\abs{\frac{1}{\sqrt{k}}}^2=\sum_{n=1}^{k}\frac{1}{k}=1\end{align*}
なので,各$v_k$は$l^2$上の単位ベクトルである.
任意に$\epsilon>0$をとる.(2)と同じ$N\in\N$をとると,三角不等式より
\begin{align*}\nor{\sum_{n=N}^{\infty}c_nT^nv_k}_{l^2}\le\sum_{n=N}^{\infty}|c_n|\|T^n\|\|v_k\|_{l^2}=\sum_{n=N}^{\infty}|c_n|<\epsilon\end{align*}
が成り立つ.また,(1)よりアーベルの定理が適用できて$\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n=0$が成り立つことに注意すると,
\begin{align*}\abs{\sum_{n=0}^{N-1}c_n}=\abs{-\sum_{n=N}^{\infty}c_n}\le\sum_{n=N}^{\infty}|c_n|<\epsilon\end{align*}
である.$k\ge N$のとき,$\sum\limits_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k$は初項から第$N-1$項まで$\sum\limits_{n=0}^{\ell-1}\frac{c_n}{\sqrt{k}}$で,第$N$項から第$k$項まで$\sum\limits_{n=0}^{N-1}\frac{c_n}{\sqrt{k}}$で,第$k+1$項から第$N+k-1$項まで$\sum\limits_{n=\ell-k}^{N-1}\frac{c_n}{\sqrt{k}}$で,第$N+k$項以降は0なので,$M:=\bra{\sum\limits_{n=0}^{N-1}|c_n|}^2$とおくと,
\begin{align*}&\nor{\sum_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k}_{l^2}^2
\\&=\sum_{\ell=1}^{N-1}\abs{\sum_{n=0}^{\ell-1}\frac{c_n}{\sqrt{k}}}^2
+\sum_{\ell=N}^{k}\abs{\sum_{n=0}^{N-1}\frac{c_n}{\sqrt{k}}}^2
+\sum_{\ell=k+1}^{N+k-1}\abs{\sum_{n=\ell-k}^{N-1}\frac{c_n}{\sqrt{k}}}^2
\\&<\frac{1}{k}\bra{(N-1)M+(k-N+1)\epsilon^2+(N-1)M}
\\&=\frac{2(N-1)M}{k}+\bra{1-\frac{N-1}{k}}\epsilon^2
\xrightarrow[]{k\to\infty}\epsilon^2\end{align*}
である.以上より,
\begin{align*}&\lim_{k\to\infty}\|Bv_k\|_{l^2}
\\&=\lim_{k\to\infty}\bra{\nor{\sum_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k}_{l^2}+\nor{\sum_{n=N}^{\infty}c_nT^nv_k}_{l^2}}
\\&\le\sqrt{\epsilon^2}+\epsilon=2\epsilon\end{align*}
が成り立つから,$\epsilon>0$の任意性と併せて$\lim\limits_{k\to\infty}\|Bv_k\|_{l^2}=0$が従う.
補足($n$が小さいときの$T^nv_k$)
$k$が$N$より十分大きいとき$T^nv_k$($n<N$)と$v_k$は高々$N-1$項ズレているだけなので,$l^2$において$T^nv_k\approx v_k$と思えます.このことに気付けば,
\begin{align*}&\nor{\sum_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k}_{l^2}
\le\nor{\sum_{n=0}^{N-1}c_nv_k}_{l^2}+\nor{\sum_{n=0}^{N-1}c_n(T^n-I)v_k}_{l^2}
\\&\le\abs{\sum_{n=0}^{N-1}c_n}\|v_k\|_{l^2}+\sum_{n=0}^{N-1}|c_n|\|(T^n-I)v_k\|_{l^2}
\\&\le\epsilon+\sum_{n=0}^{N-1}|c_n|\|(T^n-I)v_k\|_{l^2}\end{align*}
と評価して,$(T^n-I)v_k$は初項から第$n$項まで$-\frac{1}{\sqrt{k}}$で,第$k+1$項から第$n+k$項まで$\frac{1}{\sqrt{k}}$で,他の項は全て0であることから,
\begin{align*}\|(T^n-I)v_k\|_{l^2}^2=n\abs{-\frac{1}{\sqrt{k}}}^2+n\abs{\frac{1}{\sqrt{k}}}^2=\frac{2n}{k}\end{align*}
となり,$\lim\limits_{k\to\infty}\nor{\sum\limits_{n=0}^{N-1}c_nT^nv_k}_{l^2}\le\epsilon$を示すこともできます.
第12問(微分方程式)
実数値関数$u\in C^{\infty}(\R\times(0,\infty))$は
\begin{align*}\begin{cases}u_t(x,t)+u(x,t)u_x(x,t)=u_{xxx}(x,t),&(x,t)\in\R\times(0,\infty),\\
u(x+1,t)=u(x,t),&(x,t)\in\R\times(0,\infty)\end{cases}\end{align*}
を満たすとする.次の問に答えよ.
- $t\in(0,\infty)$に対して,$I_1(t)=\displaystyle\int_{0}^{1}u(x,t)^2\,dx$とおく.$I_1(t)$が$t$によらないことを示せ.
- $a\in\R$, $t\in(0,\infty)$に対して,$I_2(t)=\displaystyle\int_{0}^{1}\bra{u_x(x,t)^2+au(x,t)^3}\,dx$とおく.$I_2(t)$が$t$によらないような$a$を1つ求めよ.
- 関数$u$は$\R\times(0,\infty)$上で有界であることを示せ.ただし必要ならばある定数$M\ge0$が存在して任意の$t\in(0,\infty)$に対して
\begin{align*}\max_{x\in[0,1]}u(x,t)^2\le M\int_{0}^{1}\bra{u(x,t)^2+u_x(x,t)^2}\,dx\end{align*}
が成り立つことを使って良い.
偏微分方程式の保存量を用いて,解が有界であることを示す問題です.
解答の方針とポイント
(1), (2)は保存量に関する問題で,(3)はそれらをうまく組み合わせます.
偏微分方程式の保存量の証明
偏微分方程式の解に関する何らかの積分$I(t)$が保存量であることを示す際は,$I'(t)$について微分と積分の順序交換を行い,与えられた微分方程式を用いて$I'(t)=0$を示すのが基本的な手法です.
(1)では微分方程式より$u_t=u_{xxx}-uu_x$であることを用いて
\begin{align*}I’_1(t)&=\int_{0}^{1}2u(x,t)u_t(x,t)\,dx
\\&=2\int_{0}^{1}\bra{u(x,t)u_{xxx}(x,t)-u(x,t)^2u_x(x,t)}\,dx\end{align*}
となり,第2項は単純に積分ができて周期性より0となり,第1項も部分積分と周期性より0となることが分かります.
(2)でも同様に
\begin{align*}I’_2(t)=2\int_{0}^{1}u_xu_{xt}+3a\int_{0}^{1}u^2u_t\end{align*}
とし,微分方程式から$t$偏導関数を置き換えて部分積分と周期性を用いれば,$I’_2(t)=(3a-1)\int_{0}^{1}u_x^3$となるので$a=\frac{1}{3}$のとき$I_2(t)$が保存量となることが分かります.
解の有界性の証明
(3)では
\begin{align*}\max_{x\in[0,1]}u(x,t)^2\le M\int_{0}^{1}\bra{u(x,t)^2+u_x(x,t)^2}\,dx\end{align*}
という不等式が与えられているので,右辺の積分で保存量$I_1$, $I_2$を用いると
\begin{align*}\max_{x\in[0,1]}u(x,t)^2\le M\bra{I_1(t)+I_2(t)+\frac{1}{3}\int_{0}^{1}|u(x,t)|^3\,dx}\end{align*}
が成り立ちます.右辺が$t$によらない形になればそれで終わりでしたが,第3項は$t$によるので$\int_{0}^{1}|u(x,t)|^3\,dx$を$\max\limits_{x\in[0,1]}|u(x,t)|$の2次未満の式で上から評価できれば良いですね.
左辺が$\max\limits_{x\in[0,1]}|u(x,t)|$の2次式なので,それ以上の右辺が$\max\limits_{x\in[0,1]}|u(x,t)|$の2次未満の式であれば,$\max\limits_{x\in[0,1]}|u(x,t)|$は大きくなれませんね.
このように考えると,
\begin{align*}\int_{0}^{1}|u(x,t)|^3\,dx&\le\max_{x\in[0,1]}|u(x,t)|\int_{0}^{1}|u(x,t)|^2\,dx
\\&=\max_{x\in[0,1]}|u(x,t)|I_1(t)\end{align*}
の評価を用いれば良いことが分かりますね.
微分と積分の順序交換
$I’_1(t)$と$I’_2(t)$を求める際の微分と積分の順序交換を用いますが,微分と積分の順序交換を正当化するには次の定理を用いるのが常套手段です.
[微分と積分の順序交換条件]$A$を可測集合,$I$を開区間とする.$A\times I$上の可測関数$f(x,t)$は$t$について偏微分可能で,任意の$t\in I$に対して$f(\cdot,t)$は可積分であるとする.このとき,($t$によらない)ある$A$上の関数$g$が存在して,
- 任意の$t\in I$に対して$\abs{\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)}\le g(x)$ a.e. $x\in A$
- $g$は$A$上可積分:$\int_{A}g(x)\,dx<\infty$
を満たすなら,
\begin{align*}\frac{d}{dt}\int_{A}f(x,t)\,dx=\int_{A}\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,dx\end{align*}
が成り立つ.
この定理を使う際のポイントは
- (ほとんど至るところ)$|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)|\le g(x)$を満たす関数$g$をとる
- $\int_{A}g(x)\,dx<\infty$を満たす
の2つを示すことですね.証明は平均値の定理とルベーグの収束定理を用います.詳しくは以下の記事を参照してください.
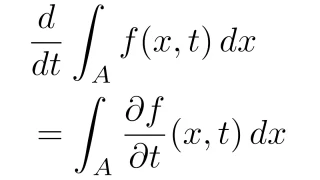
解答例
まずは全ての微分と積分の順序交換可能であるとして形式的に示し,最後に用いた微分と積分の順序交換を正当化する.また,積分$\int_{0}^{1}f(x,t)\,dx$を$\int_{0}^{1}f$と略記する.
$u$の周期性$u(x+1,t)=u(x,t)$の両辺を微分して,$u$の任意の偏導関数も$x$について周期1の周期関数であることに注意する.
(1)の解答
微分方程式より$u_t=u_{xxx}-uu_x$が得られるので,任意の$t\in(0,\infty)$に対して
\begin{align*}I’_1(t)&=\int_{0}^{1}\frac{\partial (u^2)}{\partial t}=\int_{0}^{1}2uu_t
\\&=2\int_{0}^{1}\bra{uu_{xxx}-u^2u_x}\end{align*}
である.部分積分と$u$の周期性を用いて
\begin{align*}\int_{0}^{1}uu_{xxx}&=[uu_{xx}]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}u_xu_{xx}
\\&=-\brc{\frac{1}{2}u_x^2}_{0}^{1}=0\end{align*}
が成り立ち,$u$の周期性を用いて
\begin{align*}\int_{0}^{1}u^2u_x=\brc{\frac{1}{3}u^3}_{0}^{1}=0\end{align*}
を得る.よって,$I’_1(t)=0$が得られ,$I_1(t)$は$t$によらない.
(2)の解答
任意の$t\in(0,\infty)$に対して
\begin{align*}I’_2(t)&=\int_{0}^{1}\frac{\partial\bra{u_x^2+au^3}}{\partial t}
\\&=2\int_{0}^{1}u_xu_{xt}+3a\int_{0}^{1}u^2u_t\end{align*}
である.$I’_2(t)$の第1項について,$u\in C^{\infty}(\R\times(0,\infty))$より$u$の偏導関数は偏微分の順によらないから,微分方程式の両辺を$x$で微分して得られる$u_{xt}=u_{xxxx}-u_x^2-uu_{xx}$より
\begin{align*}\int_{0}^{1}u_xu_{xt}=\int_{0}^{1}\bra{u_xu_{xxxx}-u_x^3-uu_xu_{xx}}\end{align*}
であり,$I’_2(t)$の第2項について,(1)で用いた$u_t=u_{xxx}-uu_x$より
\begin{align*}\int_{0}^{1}u^2u_t=\int_{0}^{1}\bra{u^2u_{xxx}-u^3u_x}\end{align*}
である.部分積分と$u$の周期性を用いて
\begin{align*}\int_{0}^{1}u_xu_{xxxx}
&=[u_xu_{xxx}]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}u_{xx}u_{xxx}
\\&=-\brc{\frac{1}{2}u_{xx}^2}_{0}^{1}=0,
\\\int_{0}^{1}u^2u_{xxx}
&=[u^2u_{xx}]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}2uu_xu_{xx}
\\&=-2\int_{0}^{1}uu_xu_{xx}\end{align*}
となり,$u$の周期性を用いて
\begin{align*}\int_{0}^{1}u^3u_x=\brc{\frac{1}{4}u^4}_{0}^{1}=0\end{align*}
となる.以上をまとめて
\begin{align*}I’_2(t)&=2\int_{0}^{1}\bra{-u_x^3-uu_xu_{xx}}-6a\int_{0}^{1}uu_xu_{xx}
\\&=-2\int_{0}^{1}u_x^3-2(3a+1)\int_{0}^{1}uu_xu_{xx}\end{align*}
となる.さらに,部分積分と$u$の周期性を用いて
\begin{align*}&\int_{0}^{1}uu_xu_{xx}=\frac{1}{2}\int_{0}^{1}u(u_x^2)_x
\\&=\frac{1}{2}\bra{[uu_x^2]_{0}^{1}-\int_{0}^{1}u_x^3}
=-\frac{1}{2}\int_{0}^{1}u_x^3\end{align*}
となるので,
\begin{align*}I’_2(t)=(3a-1)\int_{0}^{1}u_x^3\end{align*}
を得る.よって,$a=\frac{1}{3}$のとき$I’_2(t)=0$となり,$I_2(t)$は$t$によらない.
(3)の解答
(2)の$I_2$を$a=\frac{1}{3}$として用いる.任意の$t\in(0,\infty)$に対して,$N(t)=\max\limits_{x\in[0,1]}|u(x,t)|$とおくと,
\begin{align*}&N(t)^2=\max_{x\in[0,1]}u(x,t)^2\le M\int_{0}^{1}\bra{u^2+u_x^2}
\\&=M\bra{I_1(t)+I_2(t)-\frac{1}{3}\int_{0}^{1}u^3}
\\&\le M\bra{I_1(t)+I_2(t)+\frac{1}{3}\int_{0}^{1}|u|^3}\end{align*}
である.ここで,
\begin{align*}\int_{0}^{1}|u|^3\le N(t)\int_{0}^{1}|u|^2=N(t)I_1(t)\end{align*}
なので,
\begin{align*}&N(t)^2-\frac{MI_1(t)}{3}N(t)\le M(I_1(t)+I_2(t))
\\&\iff\bra{N(t)-\frac{MI_1(t)}{6}}^2\le M(I_1(t)+I_2(t))+\frac{M^2I_1(t)^2}{36}
\\&\Ra N(t)\le \frac{MI_1(t)}{6}+\sqrt{M(I_1(t)+I_2(t))+\frac{M^2I_1(t)^2}{36}}\end{align*}
が成り立つ.右辺は(1), (2)より$t$によらないので$N$は$(0,\infty)$上有界だから,$N$の定め方から$u$は$[0,1]\times(0,\infty)$上有界である.さらに$u$は$x$について周期1の周期関数だから,$u$は$\R\times(0,\infty)$上有界である.
微分と積分の順序交換の正当化
任意に$\delta\in(0,1)$をとる.$u\in C^{\infty}(\R\times(0,\infty))$より,有界閉集合$[0,1]\times[\delta,\frac{1}{\delta}]$上で$u$と$u$の全ての偏導関数は連続だから有界なので,$(u^2)_t$, $\bra{u_x^2+au^3}_t$は有界である.
よって,平均値の定理とルベーグの収束定理より,任意の$t\in[\delta,\frac{1}{\delta}]$に対して
\begin{align*}&I’_1(t)=\frac{d}{dt}\int_{0}^{1}u^2=\int_{0}^{1}(u^2)_t,
\\&I’_2(t)=\frac{d}{dt}\int_{0}^{1}\bra{u_x^2+au^3}=\int_{0}^{1}\bra{u_x^2+au^3}_t\end{align*}
が成り立つ.$\delta>0$の任意性より,$t\in(0,\infty)$上でもこの微分と積分の順序交換が成り立つ.
補足((3)で与えられている不等式の証明)
(3)で与えられている不等式は微分方程式と周期性に関係なく,次のように導かれます.
ある$M>0$が存在して,任意の$f\in C^1(\R)$に対して
\begin{align*}\max_{x\in[0,1]}f(x)^2\le M\int_{0}^{1}\bra{f(x)^2+f'(x)^2}\,dx\end{align*}
が成り立つ.
$f$は有界閉区間$[0,1]$上連続だから,ある$x_0\in[0,1]$で$|f(x)|$は最小値をとる.任意の$x\in[0,1]$に対して,微分積分学の基本定理と併せて
\begin{align*}|f(x)|=\abs{f(x_0)+\int_{x_0}^{x}f'(t)\,dt}\le|f(x_0)|+\|f’\|_{L^1[0,1]}\end{align*}
が成り立つ.$|f(x_0)|\le\|f\|_{L^2[0,1]}$であり,コーシー-シュワルツの不等式より
\begin{align*}\|f’\|_{L^1[0,1]}\le\|1\|_{L^2[0,1]}^{1/2}\|f’\|_{L^2[0,1]}^{1/2}=\|f’\|_{L^2[0,1]}\end{align*}
だから,$\|f\|_{L^\infty[0,1]}\le\|f\|_{L^2[0,1]}+\|f’\|_{L^2[0,1]}$が成り立つ.よって,
\begin{align*}&\max_{x\in[0,1]}f(x)^2=\|f\|_{L^\infty[0,1]}^2\le(\|f\|_{L^2[0,1]}+\|f’\|_{L^2[0,1]})^2
\\&\le2(\|f\|_{L^2[0,1]}^2+\|f’\|_{L^2[0,1]}^2)=\int_{0}^{1}\bra{f(x)^2+f'(x)^2}\,dx\end{align*}
が従う.
この証明の本質は途中の不等式$\|f\|_{L^\infty[0,1]}\le\|f\|_{L^2[0,1]}+\|f’\|_{L^2[0,1]}$です.一般に,関数のノルムを導関数たちの$L^p$ノルムで上から評価する不等式をソボレフ型不等式といい,偏微分方程式論の解析では重要な道具となることが多いです.
参考文献
基礎を固めるために私が実際に使ったオススメの入試問題集を挙げておきます.
詳解と演習大学院入試問題〈数学〉
[海老原円,太田雅人 共著/数理工学社]
理工系の修士課程への大学院入試問題集ですが,基礎〜標準的な問題が広く大学での数学の基礎が復習できる総合問題集として利用することができます.
実際,まえがきにも「単なる入試問題の解説にとどまらず,それを通じて,数学に関する読者の素養の質を高めることにある」と書かれているように,必ずしも大学院入試を受験しない一般の学習者にとっても学びやすい問題集です.また,構成が読みやすいのも個人的には嬉しいポイントです.
第1章 数え上げと整数
第2章 線形代数
第3章 微積分
第4章 微分方程式
第5章 複素解析
第6章 ベクトル解析
第7章 ラプラス変換
第8章 フーリエ変換
第9章 確率
一方で,問題数はそれほど多くないので,多くの問題を解きたい方には次の問題集もオススメです.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|詳解と演習 大学院入試問題(数理工学社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.
演習 大学院入試問題
[姫野俊一,陳啓浩 共著/サイエンス社]
上記の問題集とは対称的に問題数が多く,まえがきに「修士の基礎数学の問題の範囲は,ほぼ本書中に網羅されている」と書かれているように,広い分野から問題が豊富に掲載されています.
全2巻で,
1巻第1編 線形代数
1巻第2編 微分・積分学
1巻第3編 微分方程式
2巻第4編 ラプラス変換,フーリエ変換,特殊関数,変分法
2巻第5編 複素関数論
2巻第6編 確率・統計
が扱われています.
地道にきちんと地に足つけた考え方で解ける問題が多く,確かな「腕力」がつくテキストです.入試では基本問題は確実に解けることが大切なので,その意味で試験への対応力が養われると思います.
なお,私自身は受験生時代に計算力があまり高くなかったので,この本の問題で訓練したのを覚えています.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|演習 大学院入試問題[数学](サイエンス社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.
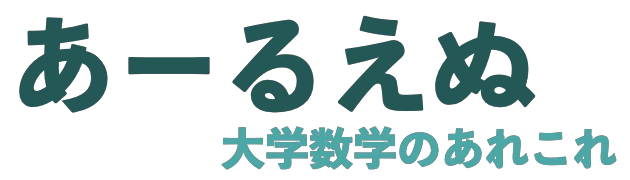
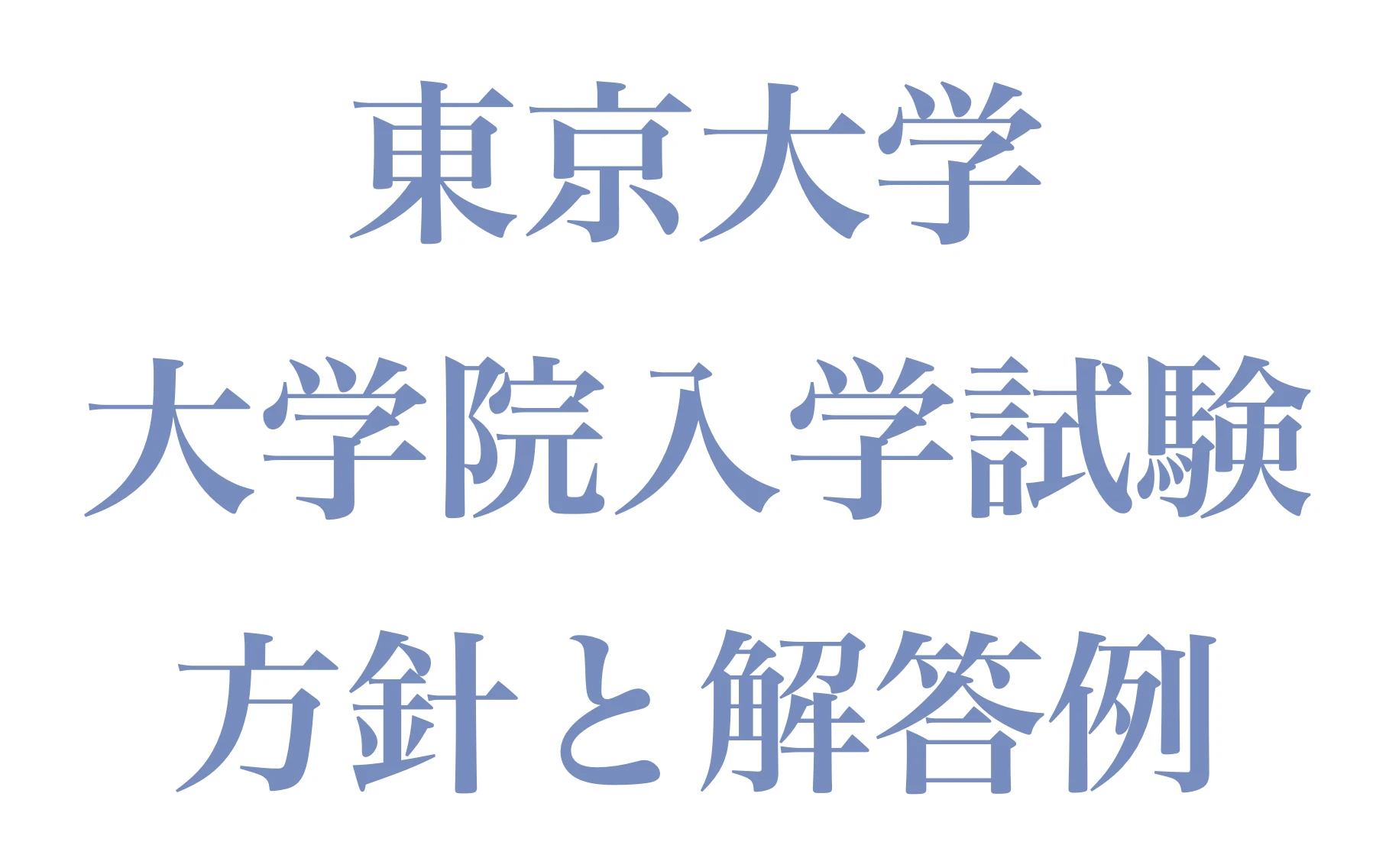


コメント