2016年度の京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻 数学系の大学院入試問題の「基礎科目II」の解答の方針と解答です.
問題は7問あり,数学系志願者は問1~問5の5問を,数理解析系志願者は問1〜問7から5問を選択して解答します.試験時間は3時間です.この記事では,問5まで解答例を掲載しています.
ただし,公式に採点基準などは発表されていないため,本稿の解答が必ずしも正解になるとは限りません.ご注意ください.
また,十分注意して解答を作成していますが,論理の飛躍・誤りが残っている場合があります.
なお,過去問は京都大学の数学教室の過去問題のページから入手できます.
第1問(微分積分学)
次の積分が収束するような実数$\alpha$の範囲を求めよ.
\begin{align*}\iint_{D}\frac{dxdy}{(x^2+y^2)^{\alpha}}\end{align*}
ただし,$D=\set{(x,y)\in\R^2}{-\infty<x<\infty,0<y<1}$とする.
重積分の広義積分が収束するための条件を求める問題です.
解答の方針とポイント
広義積分の収束・発散の判定問題では,積分のどの部分が収束・発散に影響するのかをきちんと分けて考えることが大切です.
2つの意味での広義積分
本問題の重積分は
- 積分領域$D$が有界でない
- 積分領域$D$の境界上の点$(0,0)$で被積分関数が定義されない
という2つの意味での広義積分になっています.
$D$は境界を含まないので本来的にはこの意味でも広義ですが,$(x,y)\neq(0,0)$でない$y=0,1$なる点へ連続拡張できるので収束・発散には影響しません.
そのため,積分領域$D$を
- 原点付近$D\cap\{|x|\le1\}$
- 遠方$D\cap\{|x|\ge1\}$
に分割して,それらがともに収束する条件を求めればよいですね.
それぞれの領域での収束条件
原点付近では$\frac{1}{(x^2+y^2)^{\alpha}}$の増大の程度で収束・発散が変わることが分かります.極座標変換$x=r\cos{\theta}$, $y=r\sin{\theta}$により
\begin{align*}\frac{1}{(x^2+y^2)^{\alpha}}=\frac{1}{r^{2\alpha}}\end{align*}
となることから,$\int_{0}^{1}\frac{dr}{r^{2\alpha-1}}$が収束すればよく(ヤコビアンに注意),この条件は$2\alpha-1<1$ですね.
一方,$D$上の遠方では,$y$は有界なので
\begin{align*}\frac{1}{(x^2+y^2)^{\alpha}}\approx\frac{1}{x^{2\alpha}}\end{align*}
と考えられ,$\frac{1}{x^{2\alpha}}$の減衰の程度で収束・発散が変わることが分かります.よって,$\int_{1}^{\infty}\frac{dx}{x^{2\alpha}}$が収束すればよく,この条件は$2\alpha>1$ですね.
2種類の広義積分$\int_{0}^{1}\frac{1}{x^p}\,dx$, $\int_{1}^{\infty}\frac{1}{x^p}\,dx$の収束・発散の判定は頻出なので,直観的にも当たり前にしておきたいところです.
遠方では$x$の減衰のみで収束・発散が決まる一方,原点付近では$x$, $y$の2次元の増大で収束・発散が決まるので,$2\alpha-1<1$と$2\alpha>1$でズレが生じています.計算上はこの次元のズレがヤコビアンで得られるわけですね.
解答例
集合$E:=(\R\times[0,1])\setminus\{(0,0)\}$とすると,$E\setminus D$は零集合なので問題の広義積分は
\begin{align*}I_{\alpha}:=\iint_{E}\frac{dxdy}{(x^2+y^2)^{\alpha}}\end{align*}
に等しいから,この広義積分$I_{\alpha}$の収束・発散を考えればよい.さらに,
\begin{align*}&E_0:=\set{(x,y)\in E}{x^2+y^2\le1},
\\&E_1:=\set{(x,y)\in E}{x^2+y^2\ge1,|x|\le1},
\\&E_2:=\set{(x,y)\in E}{|x|\ge1}\end{align*}
とおき,
\begin{align*}I_{k,\alpha}:=\iint_{E_k}\frac{dxdy}{(x^2+y^2)^{\alpha}}\quad(k=0,1,2)\end{align*}
とおくと,$I_{\alpha}=I_{0,\alpha}+I_{1,\alpha}+I_{2,\alpha}$である.
$E_1$は有界閉集合で,被積分関数は$E_1$上で連続だから,$I_{1,\alpha}$は積分可能である.よって,$I_{0,\alpha}$, $I_{2,\alpha}$がともに収束する$\alpha\in\R$の範囲を求めればよい.
[1]$I_{0,\alpha}$の収束条件を考える.$n\in\{1,2,\dots\}$に対し
\begin{align*}E_{0,n}:=\set{(x,y)\in E_0}{\frac{1}{n^2}\le x^2+y^2}\end{align*}
とおくと,$E_{0,n}\subset E_{0,n+1}$であり$E_0=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_{0,n}$なので,重積分の広義積分の定義より
\begin{align*}I_{0,\alpha}&=\lim_{n\to\infty}\iint_{E_{0,n}}\frac{dxdy}{(x^2+y^2)^{\alpha}}
\\&=\lim_{n\to\infty}\iint_{[\frac{1}{n},1]\times[0,\pi]}\frac{r}{r^{2\alpha}}\,drd\theta
\\&=\pi\int_{0}^{1}\frac{1}{r^{2\alpha-1}}\,dr\end{align*}
である.ただし,極座標変換$x=r\cos{\theta}$, $y=r\sin{\theta}$を用いた.よって,$I_{0,\alpha}$が収束する必要十分条件は$2\alpha-1<1\iff\alpha<1$である.
[2]$I_{2,\alpha}$の収束条件を考える.$\alpha\le0$のときは$(x,y)\in E_2$なら$\frac{1}{(x^2+y^2)^{\alpha}}\ge1$なので収束しない.よって,$\alpha>0$で考えれば十分である.$n\in\{1,2,\dots\}$に対し
\begin{align*}E_{2,n}:=\set{(x,y)\in E_2}{|x|\le n}\end{align*}
とおくと,$E_{2,n}\subset E_{2,n+1}$であり$E_2=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_{2,n}$なので,重積分の広義積分の定義より
\begin{align*}I_{2,\alpha}=\lim_{n\to\infty}\iint_{E_{2,n}}\frac{dxdy}{(x^2+y^2)^\alpha}\end{align*}
である.$(x,y)\in E_2$のとき$x^{2\alpha}\le(x^2+y^2)^{\alpha}\le 2^\alpha x^{2\alpha}$なので,$I_{2,\alpha}$の収束・発散は
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\iint_{E_{2,n}}\frac{dxdy}{x^{2\alpha}}
&=\lim_{n\to\infty}2\int_{1}^{n}\bra{\int_{0}^{1}\frac{dy}{x^{2\alpha}}}\,dx
\\&=2\int_{1}^{\infty}\frac{dx}{x^{2\alpha}}\end{align*}
の収束・発散に一致する.よって,$I_{2,\alpha}$が収束する必要十分条件は$2\alpha>1\iff\alpha>\frac{1}{2}$である.
[1],[2]より,求める$\alpha$の範囲は$\frac{1}{2}<\alpha<1$である.
第2問(線形代数学)
$A$と$B$を複素3次正方行列とする.$A$の最小多項式は$x^3-1$, $B$の最小多項式は$(x-1)^3$とする.このとき,
\begin{align*}AB\neq BA\end{align*}
となることを示せ.
与えられた最小多項式をもとに,行列の非可換性を証明する問題です.
解答の方針とポイント
否定の証明なので背理法が第一感です.すなわち,$AB=BA$と仮定して矛盾を導きましょう.
最小多項式から分かる行列の性質
ケーリー-ハミルトンの定理より,正方行列$X$の固有多項式$\phi(x)$に対して$\phi(X)=O$が成り立ちます.よって,正方行列$X$を代入して零行列$O$となる多項式は必ず存在し,そのような多項式のうち,次数が最小のものを$X$の最小多項式というのでした.
0は多項式として考える場合,次数を未定義または$-\infty$とすることが多いので,最小多項式にはなり得ません.
最小多項式の次の性質は重要ですね.
複素正方行列$X$の最小多項式$f(x)$に対して,次が成り立つ.
- $f(x)$は$X$の固有多項式を割り切る
- $f(x)$が$k$重根$\lambda$をもつとき,$X$のジョルダン標準形をなす$\lambda$に関するジョルダン細胞の最大次数は$k$である
とくに性質(2)から最小多項式が重根を持てば対角化不可能である.
本問題の3次正方行列$A$, $B$はいずれも3次の最小多項式をもつので,いずれの行列でも最小多項式と固有多項式は一致しますね.また,正方行列$B$のジョルダン標準形は$J_3(1)$と分かりますね.
異なる固有値に属する固有ベクトルは線形独立
$A$の最小多項式(固有多項式)は
\begin{align*}x^3-1=(x-1)(x-\omega)(x-\omega^2)\end{align*}
なので,$A$の固有値は1, $\omega$, $\omega^2$で,いずれも重複度は1です.よって,$A$の固有値1, $\omega$, $\omega^2$に属する固有ベクトルを用意したくなりますね.
$\m{a}_1$, $\m{a}_2$, $\m{a}_3$をそれぞれ$A$の固有値1, $\omega$, $\omega^2$に属する固有ベクトルとしましょう.ここで,もし$AB=BA$が成り立つなら,
\begin{align*}&AB\m{a}_1=BA\m{a}_1=B\m{a}_1,
\\&AB\m{a}_2=BA\m{a}_2=\omega B\m{a}_2,
\\&AB\m{a}_3=BA\m{a}_3=\omega^2 B\m{a}_3\end{align*}
であり,$B$の正則性より$B\m{a}_1$, $B\m{a}_2$, $B\m{a}_3$は零ベクトルでなく$A$の固有ベクトルと分かります.
$A$の固有空間は全て1次元なので$B\m{a}_i$は$\m{a}_i$の定数倍となり$\m{a}_i$は$B$の固有ベクトルとなりますが,これで$B$が線形独立な3個の固有ベクトルをもつことになるので,$B$が対角化不可能であることに矛盾しますね.
解答例
$\omega$を1の原始三乗根とする.$A$は3次正方行列で,$A$の最小多項式が3次式$x^3-1$なので,$A$の固有多項式も
\begin{align*}x^3-1=(x-1)(x-\omega)(x-\omega^2)\end{align*}
である.よって,$A$の固有値は1, $\omega$, $\omega^2$で,いずれも重複度は1である.よって,$\m{a}_1$, $\m{a}_2$, $\m{a}_3$をそれぞれ$A$の固有値1, $\omega$, $\omega^2$に属する固有ベクトルとすると,これらは線形独立である.
また,$B$は3次正方行列で,$B$の最小多項式が$(x-1)^3$なので,$B$の固有多項式も$(x-1)^3$である.よって,$B$は0を固有値にもたないので$B$は正則行列である.
ここで,$AB=BA$が成り立つと仮定する.$A$の任意の固有値$\lambda$に属する固有ベクトル$\m{a}$は
\begin{align*}AB\m{a}=BA\m{a}=\lambda B\m{a}\end{align*}
を満たす.固有ベクトルの定義から$\m{a}\neq0$なので,$B$の正則性と併せて$B\m{a}\neq\m{0}$である.よって,$B\m{a}$は$A$の固有値$\lambda$に属する固有ベクトルである.
$A$の固有空間の次元が全て1であることと併せて,ある$k_i\in\C\setminus\{0\}$が存在して$B\m{a}_i=k_i\m{a}_i$を満たすから,$\m{a}_i$は$B$の固有ベクトルである($i\in\{1,2,3\}$).
一方,$B$の最小多項式$(x-1)^3$は重根をもつから$B$は対角化可能でないので,$B$が線形独立な3個の固有ベクトル$\m{a}_1$, $\m{a}_2$, $\m{a}_3$をもつことは矛盾である.よって,仮定は誤りで$AB\neq BA$が従う.
第3問(複素解析学)
複素関数$f(z)$は$z=0$の近傍で正則な関数で$f(z)e^{f(z)}=z$を満たすとする.以下の問に答えよ.
- 非負整数$n$と十分小さい正数$\varepsilon$に対して次の式が成り立つことを示せ.\begin{align*}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{1}{2\pi i}\int_{C_{\varepsilon}}\frac{1+u}{e^{nu}u^n}\,du.\end{align*}ここで積分路$C_{\varepsilon}$は円周$C_{\varepsilon}=\set{u\in\C}{|u|=\varepsilon}$を正の向きに一周するものとする.
- $f(z)$の$z=0$におけるベキ級数展開を求め,その収束半径を求めよ.
$f(z)e^{f(z)}=z$を満たす0の近傍の正則関数$f$のテイラー展開の収束半径を求める問題です.
解答の方針とポイント
(1)は右辺の積分の分母$e^{nu}u^n=(e^u u)^n$が,$f$の条件$f(z)e^{f(z)}=z$の左辺の$n$乗に見えるかどうかがポイントです.(1)から$f$のテイラー展開が得られるので,(2)は収束半径を求める基本公式から解けます.
正則関数テイラー展開と導関数
目標の積分の式の被積分関数は
\begin{align*}\frac{1+u}{e^{nu}u^n}=\frac{1+u}{(e^u u)^n}\end{align*}
ですから,$z=0$付近で$f(z)e^{f(z)}=z$であることと併せると$u=f(\xi)$の変数変換を思い付きます.この変数変換により
\begin{align*}\int_{C_{\varepsilon}}\frac{1+u}{e^{nu}u^n}\,du
&=\int_{f^{-1}(C_{\varepsilon})}\frac{(1+f(\xi))f'(\xi)}{\xi^n}\,d\xi
\\&=\int_{f^{-1}(C_{\varepsilon})}\frac{f(\xi)}{\xi^{n+1}}\,d\xi\end{align*}
が成り立ちます.ただし,2つ目の等号では$(1+f(\xi))f'(\xi)e^{f(\xi)}=1$, $e^{f(z)}=\xi f(\xi)^{-1}$が成り立つことを使いました.
$f$のテイラー展開(ベキ級数展開)から,$f$の微分係数は積分で
\begin{align*}f^{(n)}(0)=\frac{n!}{2\pi i}\int_{C_\delta}\frac{f(\xi)}{\xi^{n+1}}\,d\xi\end{align*}
と表せますから,これで(1)の等式が証明できますね.
なお,$f(z)e^{f(z)}=z$から$f(0)=0$, $f(0)’=1>0$が得られ,$f$は0のある近傍で双正則で,$\varepsilon$が十分小さければ$z$が$C_{\varepsilon}$上を正の向きに回るとき$f(z)$も0の周りを正方向に1周しますね.
$m$位の極での留数の求め方
$f$のテイラー展開$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$の収束半径は$\lim\limits_{n\to\infty}\abs{\frac{a_{n+1}}{a_n}}$を計算して,逆数をとればよいですね.(1)と留数定理より
\begin{align*}a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{1}{2\pi i}\int_{C_{\varepsilon}}\frac{1+u}{e^{nu}u^n}\,du=\mrm{Res}\bra{\frac{1+u}{e^{nu}u^n},0}\end{align*}
が成り立ち,0は$\frac{1+u}{e^{nu}u^n}$の$n$位の極ですから,
\begin{align*}\mrm{Res}\bra{\frac{1+u}{e^{nu}u^n},0}=\lim_{z\to\alpha}\frac{1}{n!}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\bra{\frac{1+u}{e^{nu}}}\end{align*}
ですね.
点$\alpha$のある除外近傍で正則な複素関数$f$が$\alpha$を$m$位の極としてもつとする.$g(z)=(z-\alpha)^mf(z)$とすると,
\begin{align*}\mathrm{Res}(f,\alpha)=\lim_{z\to\alpha}\frac{g^{(m-1)}(z)}{(m-1)!}\end{align*}
が成り立つ.
解答例
(1)の解答
$f(z)e^{f(z)}=z$に$z=0$を代入すると,$e^{f(0)}\neq0$より$f(0)=0$を得る.また,$f(z)e^{f(z)}=z$の両辺を$z$で微分すると,
\begin{align*}(1+f(z))f'(z)e^{f(z)}=1\end{align*}
となって$z=0$を代入すると,$e^{f(0)}\neq0$と$f(0)=0$より$f'(0)=1>0$を得る.よって,$f$は0のある近傍で双正則で,十分小さい$\varepsilon$が存在して,$f^{-1}(C_{\varepsilon})$は0の周りを正方向に1周する.
よって,$u=f(\xi)$と変数変換すれば,$(1+f(\xi))f'(\xi)=e^{-f(\xi)}=\frac{f(\xi)}{\xi}$なので,
\begin{align*}\frac{1}{2\pi i}\int_{C_{\varepsilon}}\frac{1+u}{e^{nu}u^n}\,du
&=\frac{1}{2\pi i}\int_{f^{-1}(C_{\varepsilon})}\frac{1+f(\xi)}{(e^{f(\xi)}f(\xi))^n}(f'(\xi)\,d\xi)
\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{f^{-1}(C_{\varepsilon})}\frac{(1+f(\xi))f'(\xi)}{\xi^n}\,d\xi
\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{f^{-1}(C_{\varepsilon})}\frac{f(\xi)}{\xi^{n+1}}\,d\xi
=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\end{align*}
を得る.
(2)の解答
(1)の$\varepsilon>0$をとり,複素関数$g_n$を$g_n(u):=\frac{1+u}{e^{nu}u^n}$とおく($n=1,2,\dots$).$g_n$は円周$C_\varepsilon$上で連続で,0を除く$C_\varepsilon$の内部で$g_n$は正則である.0は$g_n$の$n$位の極である.
よって,留数定理と併せて
\begin{align*}\frac{(n-1)!}{2\pi i}\int_{C_{\varepsilon}}\frac{1+u}{e^{nu}u^n}\,du
&=(n-1)!\cdot\mrm{Res}(g_n,0)
\\&=\lim_{u\to0}\bra{(1+u)e^{-nu}}^{(n-1)}\end{align*}
となる.ライプニッツルールと,任意の$k\in\{2,3,\dots\}$に対して$(1+u)^{(k)}=0$であることより,
\begin{align*}&\bra{(1+u)e^{-nu}}^{(n-1)}
=\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k}(1+u)^{(k)}(e^{-nu})^{n-k-1}
\\&=(n-1)\cdot1\cdot(-n)^{n-2}e^{-nu}+1\cdot(1+u)\cdot(-n)^{n-1}e^{-nu}
\\&\xrightarrow[]{u\to0}(n-1)(-n)^{n-2}+(-n)^{n-1}=-(-n)^{n-2}\end{align*}
が成り立つ.よって,(1)と併せて
\begin{align*}f^{(n)}(0)=-n(-n)^{n-2}=(-n)^{n-1}\end{align*}
だから,$f$を0中心のテイラー展開は
\begin{align*}f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-(-n)^{n-2}}{(n-1)!}z^n
=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-n)^{n-1}}{n!}z^n\end{align*}
である.最後に,収束半径は
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\abs{\frac{\frac{(-n-1)^{n}}{(n+1)!}}{\frac{(-n)^{n-1}}{n!}}}
&=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{n}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{n^{n-1}}
\\&=\lim_{n\to\infty}\bra{1+\frac{1}{n}}^{n}\bra{1+\frac{1}{n}}^{-1}
\\&=e\cdot1=e\quad\end{align*}
の逆数の$e^{-1}$である.
第4問(線形代数学)
正則な複素2次正方行列のなす群を$GL_2(\C)$とおく.行列
\begin{align*}A=\pmat{0&-1\\1&1},\quad
B=\pmat{0&1\\1&0}\end{align*}
で生成される$GL_2(\C)$の部分群$G$について,以下の問に答えよ.
- 群$G$の位数を求めよ.
- 群$G$の中心の位数を求めよ.
- 群$G$に含まれる位数2の元の個数を求めよ.
生成される群のいくつかの基本的な性質を求める問題です.
解答の方針とポイント
$G$は2面体群$D_6$と同型ですが,そのことに気付かなくても定義に基づいて考えれば解けます.
生成される部分群の考え方
生成される部分群を考える際は
- 1つの生成元だけからどんな元が生成されるか
- 複数の生成元の関係
が重要になることが多いです.$A$, $B$の冪を実際に計算すると
\begin{align*}A^2=\bmat{-1&-1\\1&0},\quad
A^3=-I,\quad
B^2=I\end{align*}
ですから,$\anb{A}=\{A,A^2,-I_2,-A,-A^2,I_2\}$, $\anb{B}=\{B,I_2\}$となることが分かります.また,$B$は行または列を入れ替える基本変形を引き起こす行列なので,$AB=-BA^2$が成り立つことが分かります.
このことから$\anb{A,B}$の元は全て$\pm B^mA^n$($m=0,1$, $n=0,1,2$)と表すことができ,これらは全て異なるので$G$の元の個数が得られますね.
群の中心
群$G$に対して,集合$\set{g\in G}{\forall h\ hg=gh}$を$G$の中心という.
すなわち,$G$の全ての元と可換な元を全て集めてできる集合を$G$の中心というわけですね.
また,$G$の中心の元$X$は$B$とも可換であることが必要で,$B$を左からかけて行の入れ替え,右からかけて列の入れ替えが起こるので,$X$は少なくとも対称行列でなければなりません.
この時点で$\pm B$, $\pm I$以外が中心に属さないことが分かり,$B$は$A$と非可換なので,$\pm B$は$G$の中心に属しません.よって,中心の元は$\pm I$ですね.
解答例
$I$を2次単位行列とする.
(1)の解答
計算により,
\begin{align*}A^2=\bmat{-1&-1\\1&0},\quad
A^3=-I,\quad
B^2=I\end{align*}
である.「任意の$G$の元に$B$を左からかけることで行が入れ替わり,右からかけることで列が入れ替わる」$\dots(*)$ことに注意すると,$AB=-BA^2$が成り立つことが分かる.
よって,$G$の元は,$AB$の部分を$-BA^2$に置き換えて,$A^3=-I$, $B^2=I$を用いることで,$\pm BA^n$, $\pm A^n$($n=1,2,3$)に限ることが分かる.
これらの中に同じものがないことは,$\pm A$, $\pm A^2$, $\pm I$が等しくなく,かつ行を逆転させた$\pm BA$, $\pm BA^2$, $\pm B$とも異なることが実際の行列を見ることで分かる.
以上より,
\begin{align*}G=\{\pm I,\pm A,\pm A^2,\pm B,\pm BA,\pm BA^2\}\end{align*}
で,$|G|=12$を得る.
(2)の解答
$G$の中心の任意の元$X$は$B$と可換なので,$(*)$に注意すれば$X$は対称行列である.よって,$\pm B$, $\pm I$以外は中心に属さない.
また,$AB\neq BA$なので$\pm B$は中心に属さず,$\pm I$は任意の$G$の元と可換なので中心に属する.
以上より,$G$の中心は$\{\pm I\}$なので,この位数は2である.
(3)の解答
$I$でない元を2乗して$I$になるものの個数を求めれば良い.
- $(-I)^2=I$
- $(\pm A)^2=A^2\neq I$
- $(\pm A^2)^2=A^4\neq I$
- $(\pm B)^2=I$
- $(\pm BA)^2=BABA=B(-BA^2)A=-B^2A^3=I$
- $(\pm BA^2)^2=BA^2BA^2=(-AB)BA^2=-AIA^2=-A^3=I$
だから,$G$に含まれる位数2の元の個数は7である.
第5問(微分幾何学)
3次元微分可能多様体$M=\set{(x,y,z,w)\in\R^4}{xy-z^2=w}$から$\R^3$への写像$f=(f_1,f_2,f_3):M\to\R^3$を
\begin{align*}f(x,y,z,w)=(x+y,z,w)\end{align*}
により定める.以下の問に答えよ.
- $f$の臨界点の集合$C$を求めよ.ただし$p\in M$が$f$の臨界点であるとは,$p$の周りの$M$の座標系$(u_1,u_2,u_3)$に関するヤコビ行列\begin{align*}\bra{\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(p)}_{1\le i,j\le 3}\end{align*}が正則でないことである.
- $C$が$M$の部分多様体になることを証明せよ.
写像$f:M\to\R^3$の臨界点の集合が$M$の部分多様体となることを示す問題です.
解答の方針とポイント
$M$の座標近傍系を実際に定めて,その座標近傍系について議論を進めることで解くことができます.
臨界点を求める
$M$の臨界点を求めるには,(1)の問題文にもあるように座標近傍系を定めてヤコビ行列を計算するのが素朴な方法です.
点$(x,y,z,w)\in M$について$w$は$x,y,z$で一意に表せますから,$\phi:M\to\R^3$を第1成分,第2成分,第3成分への直交射影とすると,$\{(M,\phi)\}$は$M$の座標近傍系となります.
この座標近傍系をもとに実際にヤコビ行列を求め,正則でないような点$(x,y,z,w)\in M$を求めればよいですね.
正則値定理で可微分多様体であることを示す
微分可能部分多様体であることを示す方法としては正則値定理(沈め込み定理)が基本です.
微分可能多様体$M_1$, $M_2$と,写像$f:M_1\to M_2$に対して,$p\in M_1$が$f$の正則点であるとは微分$(df)_p:T_p(M_1)\to T_f(p)(M_2)$が全射であることをいい,正則点でない$M_1$上の点は臨界点というのでした.
$p\in M_1$が$f$の正則点であることと,$\rank{Jf(p)}=\dim{M_2}$が成り立つことと同値なのでした($Jf(p)$は$f$の$p$におけるヤコビ行列).
さらに,臨界点の像を臨界値といい,臨界値でない$M_2$の元を正則値といいますね.
このことを局所座標を用いて言い換えたものが(2)の臨界点の定義です.
正則値の逆像が$\emptyset$または$M_1$上の微分可能部分多様体であることを述べた次の定理を正則値定理(沈め込み定理)といいます.
[正則値定理]$C^s$級微分可能多様体$M_1$, $M_2$と,$C^s$級写像$f:M_1\to M_2$に対して,$f$の正則値$q\in M_2$の逆像$f^{-1}(q)$は$M_1$の$(\dim{M_1}-\dim{M_2})$次元$C^s$級部分多様体である.
(1)で$C=\set{(x,y,z,w)\in M}{x=y}$と求まるので,$g:M\to\R$を
\begin{align*}g(x,y,z,w)=y-x\end{align*}
で定義すると$C=g^{-1}(0)$となりますから,(2)では$0\in\R$が$g$の正則点であることを示せば$g$に正則値定理が適用できますね.
解答例
写像$\phi:M\to\R^3;(x,y,z,w)\mapsto(x,y,z)$を定めると,$\{(M,\phi)\}$は$M$の座標近傍系となり,
\begin{align*}\phi^{-1}:\phi(M)\to M;(u_1,u_2,u_3)\mapsto\bra{u_1,u_2,u_3,u_1u_2-{u_3}^2}\end{align*}
である.以下は全てこの座標近傍系で考える.
(1)の解答
$(M,\phi)$上で$f$は
\begin{align*}\bra{f\circ\phi^{-1}}(u_1,u_2,u_3)=\bra{u_1+u_2,u_3,u_1u_2-{u_3}^2}\end{align*}
となるから,点$\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)\in M$での$f$のヤコビ行列$Jf_{\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)}$は
\begin{align*}|Jf_{\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)}|
&=\vmat{\frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial u_1}&\frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial u_2}&\frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial u_3}\\
\frac{\partial u_3}{\partial u_1}&\frac{\partial u_3}{\partial u_2}&\frac{\partial u_3}{\partial u_3}\\
\frac{\partial(u_1u_2-u_3^2)}{\partial u_1}&\frac{\partial(u_1u_2-u_3^2)}{\partial u_2}&\frac{\partial(u_1u_2-u_3^2)}{\partial u_3}}
\\&=\vmat{1&1&0\\0&0&1\\u_2&u_1&-2u_3}
=u_2-u_1\end{align*}
だから,点$\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)\in M$が$f$の臨界点であるためには
\begin{align*}|Jf_{\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)}|=0
\iff u_1=u_2\end{align*}
あることが必要十分である.よって,
\begin{align*}C&=\set{\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)\in M}{u_1=u_2}
\\&=\set{(x,y,z,w)\in M}{x=y}\end{align*}
である.
(2)の解答
写像$g:M\to\R:(x,y,z,w)\mapsto y-x$を定めると,
\begin{align*}\bra{g\circ\phi^{-1}}(u_1,u_2,u_3)=u_2-u_1\end{align*}
である.よって,点$\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)\in M$での$g$のヤコビ行列$Jg_{\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)}$は
\begin{align*}Jg_{\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)}
=\brc{\frac{\partial(u_2-u_1)}{\partial u_1},\frac{\partial(u_2-u_1)}{\partial u_2},\frac{\partial(u_2-u_1)}{\partial u_3}}
=[-1,1,0]\end{align*}
だから,
\begin{align*}\operatorname{rank}{Jg_{(u_1,u_2,u_3)}}\neq0
\iff\operatorname{rank}{[-1,1,0]}\neq0\end{align*}
なので,点$\phi^{-1}(u_1,u_2,u_3)\in M$は$g$の正則点である.これより,$M$上の任意は$g$の正則点だから,正則値定理より$C=g^{-1}(0)$は$M$の部分多様体である.
参考文献
以下,私も使ったオススメの入試問題集を挙げておきます.
詳解と演習大学院入試問題〈数学〉
[海老原円,太田雅人 共著/数理工学社]
理工系の修士課程への大学院入試問題集ですが,基礎〜標準的な問題が広く大学での数学の基礎が復習できる総合問題集として利用することができます.
実際,まえがきにも「単なる入試問題の解説にとどまらず,それを通じて,数学に関する読者の素養の質を高めることにある」と書かれているように,必ずしも大学院入試を受験しない一般の学習者にとっても学びやすい問題集です.また,構成が読みやすいのも個人的には嬉しいポイントです.
第1章 数え上げと整数
第2章 線形代数
第3章 微積分
第4章 微分方程式
第5章 複素解析
第6章 ベクトル解析
第7章 ラプラス変換
第8章 フーリエ変換
第9章 確率
一方で,問題数はそれほど多くないので,多くの問題を解きたい方には次の問題集もオススメです.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|詳解と演習 大学院入試問題(数理工学社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.
演習 大学院入試問題
[姫野俊一,陳啓浩 共著/サイエンス社]
上記の問題集とは対称的に問題数が多く,まえがきに「修士の基礎数学の問題の範囲は,ほぼ本書中に網羅されている」と書かれているように,広い分野から問題が豊富に掲載されています.
全2巻で,
1巻第1編 線形代数
1巻第2編 微分・積分学
1巻第3編 微分方程式
2巻第4編 ラプラス変換,フーリエ変換,特殊関数,変分法
2巻第5編 複素関数論
2巻第6編 確率・統計
が扱われています.
地道にきちんと地に足つけた考え方で解ける問題が多く,確かな「腕力」がつくテキストです.入試では基本問題は確実に解けることが大切なので,その意味で試験への対応力が養われると思います.
なお,私自身は受験生時代に計算力があまり高くなかったので,この本の問題で訓練したのを覚えています.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|演習 大学院入試問題[数学](サイエンス社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.

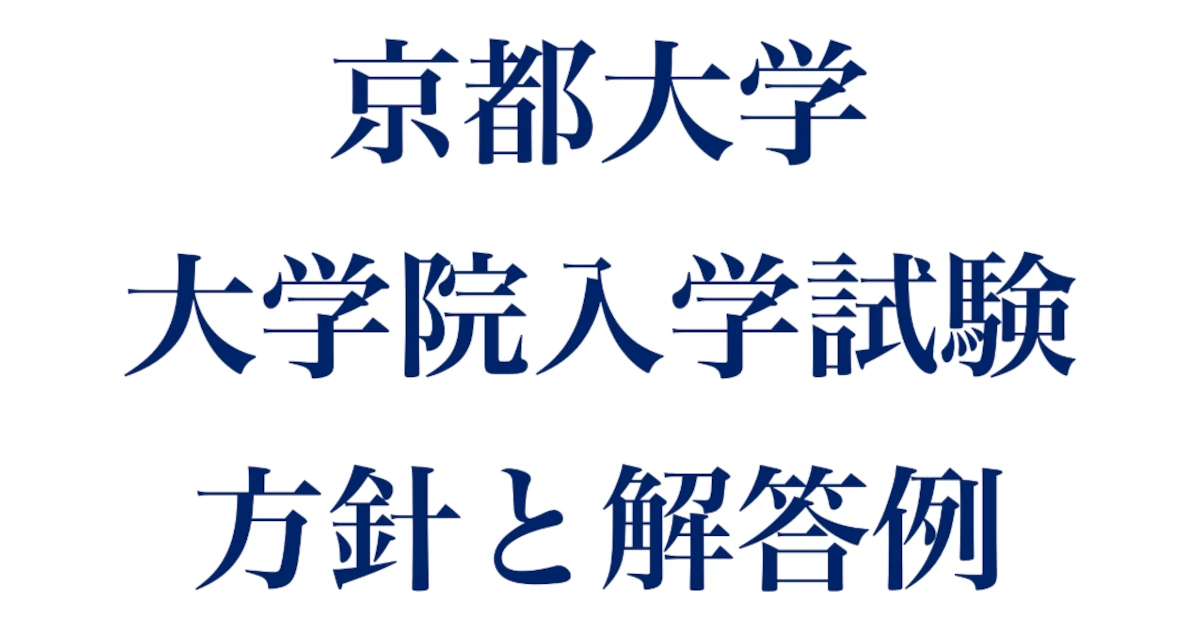


コメント