2017年度の京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻 数学系の大学院入試問題の「基礎科目」の解答の方針と解答です.
問題は7問あり,数学系志願者は問1~問6の6問を,数理解析系志願者は
- 問1〜問5の5問
- 問6,問7から1問
の計6問を解答します.試験時間は3時間30分です.この記事では,問7まで解答例を掲載しています.
ただし,公式に採点基準などは発表されていないため,本稿の解答が必ずしも正解になるとは限りません.ご注意ください.
また,十分注意して解答を作成していますが,論理の飛躍・誤りが残っている場合があります.
なお,過去問は京都大学の数学教室の過去問題のページから入手できます.
第1問(微分積分学)
次の重積分を求めよ.
\begin{align*}\iint_{D}e^{-\max\{x^2,y^2\}}\,dxdy\end{align*}
ここで,$D=\set{(x,y)\in\R^2}{0\le x\le1,0\le y\le1}$とする.
基本的な重積分の計算問題です.
解答の方針とポイント
被積分関数の$\max\{x^2,y^2\}$の部分をどう扱うかがポイントです.一般に$a,b\in\R$に対して$\max\{a,b\}$は$a$, $b$の小さくない方の値を意味しますから,
\begin{align*}\max\{a,b\}=\begin{cases}a&(a\ge b)\\a&(a<b)\end{cases}\end{align*}
となりますね.
本問の積分領域$D$上で$x$, $y$はともに正ですから,$(x,y)\in D$に対して
\begin{align*}\max\{x^2,y^2\}=\begin{cases}x^2&(x\ge y)\\y^2&(x<y)\end{cases}\end{align*}
となるので,積分領域$D$を$x\ge y$の部分と$x\le y$の部分に分けて計算すれば良いですね.
$|x|$が被積分関数にあれば,$|x|=\begin{cases}x,&x\ge0,\\-x,&x<0\end{cases}$より,$x\ge0$の部分と$x\le 0$の部分に分けて積分するのと同じ方針ですね.
解答例
$D_1=\set{(x,y)\in D}{x\ge y}$, $D_2=\set{(x,y)\in D}{x\le y}$とする.$D_1\cap D_2$は零集合で,$D_1\cup D_2=D$である.
\begin{align*}&\iint_{D}e^{-\max\{x^2,y^2\}}\,dxdy
\\&=\iint_{D_1}e^{-x^2}\,dxdy+\iint_{D_2}e^{-y^2}\,dxdy
\\&=\int_{0}^{1}\bra{\int_{0}^{x}e^{-x^2}\,dy}\,dx+\int_{0}^{1}\bra{\int_{0}^{y}e^{-y^2}\,dx}\,dy
\\&=2\int_{0}^{1}\bra{\int_{0}^{x}e^{-x^2}\,dy}\,dx=\int_{0}^{1}2xe^{-x^2}\,dx
\\&=\brc{-e^{-x^2}}_{0}^{1}
=1-e^{-1}\end{align*}
を得る.
第2問(線形代数学)
実行列
\begin{align*}A=\pmat{1&-2&-1&1&0\\-2&5&3&-2&1\\1&1&2&0&-1\\5&0&5&3&2}\end{align*}
について,以下の問に答えよ.
- 連立1次方程式\begin{align*}A\pmat{x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5}=\pmat{0\\0\\0\\0}\end{align*}の解を全て求めよ.
- 連立1次方程式\begin{align*}A\pmat{x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5}=\pmat{0\\-1\\1\\c}\end{align*}が解を持つような実数$c$を全て求めよ.
連立1次方程式が解をもつ条件に関する問題です.
解答の方針とポイント
連立1次方程式$A\m{x}=\m{c}$は加減法により解くことができますが,加減法による式変形は拡大係数行列$[A,\m{c}]$の行基本変形による簡約化と本質的に同じですね.
この拡大係数行列$[A,\m{c}]$の行基本変形による簡約化による連立1次方程式の解法を掃き出し法と言いますね.
本問の(1)は掃き出し法を用いて解くことができます.
また,掃き出し法をもとにすると,次のように連立1次方程式が解を持つための必要十分条件が得られるのでした.
$m\times n$行列$A$と$m$次列ベクトル$\m{c}$に対し,次は同値である.
- $\rank{A}=\rank{[A,\m{c}]}$
- $\m{x}\in\R^n$の連立1次方程式$A\m{x}=\m{c}$は解をもつ
本問の(2)はこの定理を用いることで解くことができます.
解答例
(1)の解答
掃き出し法により求める.斉次連立1次方程式だから係数行列$A$は行基本変形により
\begin{align*}A&\to\bmat{1&-2&-1&1&0\\0&1&1&0&1\\0&3&3&-1&-1\\0&10&10&-2&2}
\\&\to\bmat{1&0&1&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&-1&-4\\0&0&0&-2&-8}
\to\bmat{1&0&1&0&-2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&4\\0&0&0&0&0}\end{align*}
と変形できるから,解は
\begin{align*}\bmat{x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5}=\bmat{-t+2s\\-t-s\\t\\-4s\\s}\quad(t,s\in\R)\end{align*}
となる.
(2)の解答
解を持つための必要十分条件は,
\begin{align*}\operatorname{rank}\brc{A,\bmat{0\\-1\\1\\c}}
=\operatorname{rank}A\end{align*}
である.(1)から$\operatorname{rank}A=3$で,
\begin{align*}3=&\operatorname{rank}\brc{A,\bmat{0\\-1\\1\\c}}
\\=&\operatorname{rank}\bmat{1&-2&-1&1&0&0\\0&1&1&0&1&-1\\0&3&3&-1&-1&1\\0&10&10&-2&2&c}
\\=&\operatorname{rank}\bmat{1&0&1&1&2&-2\\0&1&1&0&1&-1\\0&0&0&-1&-4&4\\0&0&0&-2&-8&c+10}
\\=&\operatorname{rank}\bmat{1&0&1&0&-2&2\\0&1&1&0&1&-1\\0&0&0&-1&-4&4\\0&0&0&0&0&c+2}\end{align*}
である.よって,求める実数$c$は$c+2=0\iff c=-2$である.
第3問(線形代数学)
$m$, $n$を正の整数とし,$A$を複素$(n,m)$行列,$B$を複素$(m,n)$行列とする.複素数$\lambda\neq0$について,以下の問に答えよ.
- $\lambda$が$BA$の固有値ならば,$\lambda$は$AB$の固有値でもあることを示せ.
- $\C^m$, $\C^n$の部分空間$V$, $W$をそれぞれ
- $V=\set{\m{x}\in\C^m}{\text{ある正の整数$k$に対して$(BA-\lambda I_m)^k \m{x}=\m{0}$が成り立つ}}$
- $W=\set{\m{y}\in\C^n}{\text{ある正の整数$l$に対して$(AB-\lambda I_n)^l\m{y}=\m{0}$が成り立つ}}$
で定める.ただし,$I_m$, $I_n$は単位行列,$\m{0}$は零ベクトルを表す.このとき,$\dim{V}=\dim{W}$であることを示せ.
$AB$の固有値と$BA$の固有値が等しいことを示し,$BA$, $BA$それぞれの広義固有空間$V$, $W$の次元が等しいことを示す問題ですね.
解答の方針とポイント
一般に複素$n$次正方行列$X$の固有値$\lambda$に対して,$\C^n$の部分空間
\begin{align*}\widetilde{W}_{X}(\lambda):=\bigcup_{i=1}^{\infty}\Ker{(X-\lambda I_n)^i}\end{align*}
を$X$の固有値$\lambda$に対する広義固有空間といいます.
本問の$V$は$m$次正方行列$BA$の広義固有空間,$W$は$n$次正方行列$AB$の広義固有空間となっていますから,本問の(ii)は$AB$の広義固有空間と$BA$の広義固有空間の次元が等しいことを示す問題と言えますね.
固有値と固有ベクトル
本問の(i)で$\lambda$が$AB$の固有値であることを示すには,$AB\m{q}=\lambda\m{q}$となる$\m{q}\in\C^m\setminus\{\m{0}\}$が存在することを示すことになります.
この$\m{q}$を$BA$の固有値$\lambda$に属する固有ベクトルといいますね.
$\lambda$が$BA$の固有値という仮定から,$\m{p}\in\C^m\setminus\{\m{0}\}$が存在して$BA\m{p}=\lambda\m{p}$が成り立ちます.
この仮定を使おうとすると,$AB$の固有ベクトルは$\m{q}=A\m{p}$と取れそうだと予想できますね.
ただし,このとき$A\m{p}\neq\m{0}$の証明を忘れないように注意してください.
次元が等しいことの証明
一般に同じ体上の線形空間$V$, $W$に対して,単射$f:V\to W$が存在するとき,$\dim{V}\le\dim{W}$が成り立ちます.
よって,本問の(ii)では単射$V\to W$と単射$W\to V$が存在することを示せば良いですね.
その際,(i)の議論を参考にして$(AB-\lambda I_n)^{k}A=A(BA-\lambda I_m)^{k}$を示し,$v\in V$に対し$Av\in W$が成り立つことを証明することがポイントとなります.
この行列$A$を左からかける写像$V\to W$が実は単射になっており,$\dim{V}\le\dim{W}$が成り立ちます.
なお,線形写像$f$が単射であるための必要十分条件が$\Ker{f}=\{\m{0}\}$であることは当たり前にしておきましょう.
$V$と$W$は対称なので,同様に逆の不等号$\dim{W}\le\dim{V}$も得られます.
解答例
(1)の解答
$BA$の固有値$\lambda$に属する固有ベクトルの1つを$\m{p}$とすると,
\begin{align*}BA\m{p}=\lambda\m{p}\end{align*}
である.もし$A\m{p}=\m{0}$なら$\lambda\m{p}=\m{0}$だから,$\lambda\neq0$と併せて$\m{p}=0$となって$\m{p}$が固有ベクトル(したがって$\m{p}\neq0$)であることに矛盾するから,$A\m{p}\neq\m{0}$である.また,
\begin{align*}AB(A\m{p})=A(BA\m{p})=A(\lambda\m{p})=\lambda(A\m{p})\end{align*}
となるから,$AB$は固有値$\lambda$をもつ.
(2)の解答
$\m{v}\in V$とすると,ある正の整数$k$が存在して$(BA-\lambda I_m)^k \m{v}=\m{0}$を満たす.$AB$と$-\lambda I_n$は可換だから,
\begin{align*}&(AB-\lambda I_n)^k A\m{v}
\\&=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-\lambda)^{k-i}(AB)^i A\m{v}
\\&=A\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-\lambda)^{k-i}(BA)^i \m{v}
\\&=A(BA-\lambda I_m)^k \m{v}=\m{0}\end{align*}
となり$A\m{v}\in W$が成り立つ.よって,線形写像$f:V\to W;\m{v}\mapsto A\m{v}$が定義できる.
ここで,$f$が単射であることを示す.$\m{v}\in\operatorname{Ker}f$なら
\begin{align*}\m{0}&=(BA-\lambda I_m)^k \m{v}
\\&=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-\lambda)^{k-i}(BA)^i\m{v}
\\&=\sum_{i=1}^{k}\binom{k}{i}(-\lambda)^{k-i}(BA)^{i-1}B\m{0}+(-\lambda)^k \m{v}
\\&=(-\lambda)^k \m{v}\end{align*}
だから,$\lambda\neq0$と併せて$\m{v}=\m{0}$が成り立つ.よって,$\operatorname{Ker}f=\{\m{0}\}$だから$f$は単射なので,$\dim{V}\le\dim{W}$が成り立つ.
$V$, $W$は対称なので$\dim{W}\le\dim{V}$も成り立つから,$\dim{V}=\dim{W}$が従う.
第4問(微分積分学)
$f$を$I=\set{x\in\R}{x\ge0}$上の実数値連続関数とする.正の整数$n$に対し,$I$上の関数$f_n$を
\begin{align*}f_n(x)=f(x+n)\end{align*}
で定める.関数列$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$が$I$上で一様収束するとき,以下の問に答えよ.
- $I$上の関数$g$を\begin{align*}g(x)=\lim_{n\to\infty}f_n(x)\end{align*}で定める.このとき$g$は$I$上で一様連続であることを示せ.
- $f$は$I$上で一様連続であることを示せ.
$f$をちょうど正整数だけ平行移動してできる関数列$\{f_n\}$が一様収束するなら,$f$が一様連続であることを示す問題です.
解答の方針とポイント
$f$を$n\in\N$だけ平行移動してできる関数$f$が一様収束していることから,$x$が大きいところでの$f(x)$の形状が予想できるかがポイントです.
関数$f$の遠方での形と極限関数$g$の性質
各正の整数$n$に対して,$y=f_n(x)$のグラフは$y=f(x)$を$n$だけ負方向に平行移動してできるグラフの$x\ge0$の部分ですね.
関数列$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$が$I=[0,\infty)$上で一様収束することから,$n,m\in\N$が十分大きければ2つの関数$f_m$, $f_n$はほとんど等しくなっています.
このことから関数$f$は十分遠方でほとんど周期1の関数のようになっており,関数列$\{f_n\}$の極限関数$g$は周期1の周期関数だと予想できます.
$X$を集合,$a\in\R$, $p>0$とする.関数$f:[a,\infty)\to X$が周期$p$の周期関数であるとは,任意の$x\ge a$に対して$g(x)=g(x+a)$が成り立つことをいう.
極限関数$g$が周期1の周期関数であるとは,任意の$x\in I$に対して$g(x+1)=g(x)$が成り立つことで,これは$g=\lim\limits_{n\to\infty}f_n$から得られますね.
一様収束と一様連続の性質
極限関数$g$が周期1の周期関数であることが分かれば,$|x-y|<1$を満たす$x,y\in I$に対して,ある$k\in\{0,1,2,\dots\}$が存在して
\begin{align*}x-k,y-k\in[0,2]\end{align*}
となりますから,結局$g$が区間$[0,2]$で一様連続であることを示せば$I=[0,\infty)$上で一様連続であることが従いますね.
ここで,次の2つの定理は重要なので当たり前にしておきましょう.
集合$A$上の実数値連続関数列$\{f_n\}$が極限関数$g$に一様収束するとき,$g$は$A$上連続である.
[ハイネ-カントールの定理]コンパクト集合$A$上の実数値連続関数は$A$上一様連続である.
いま極限関数$g$は$I$上の実数値連続関数$\{f_n\}$の一様収束極限なので$g$は$I$上連続で,有界閉区間$[0,2]$はコンパクト集合(ハイネ-ボレルの定理)ですから,上の2つの定理より$g$は$[0,2]$上一様連続であると分かりますね.
$f$の一様連続性
(1)より,$x$が十分大きいなら$f(x)$は周期関数$g(x)$に近い関数になっているはずです.
そのため,ある十分大きな$N\in\N$が存在して,$f$は$[N,\infty)$上で$g$と比較して一様連続であることが成り立ちそうですね.
一方,$f$は$[0,N+1]$上で連続ですから,(1)で用いたハイネ-カントールの定理より$f$は$[0,N+1]$上で一様連続と分かります.
遠方の区間$[N,\infty)$上と有限区間$[0,N]$上のそれぞれで$f$が一様連続であるだけでは,$x<N<y$の場合の議論が少々必要になり面倒です.そのため,区間$[N,\infty)$, $[0,N+1]$で少しオーバーラップさせています.
解答例
(1)の解答
任意に$\epsilon>0$をとる.任意の$x\in I$に対して,
\begin{align*}g(x+1)&=\lim_{n\to\infty}f_n(x+1)=\lim_{n\to\infty}f(x+1+n)
\\&=\lim_{n\to\infty}f_{n+1}(x)=g(x)\end{align*}
だから,関数$g$は周期1の周期関数である.
関数$f$の連続性から各$f_n$も連続で,関数列$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$は$I$上で$g$に一様収束するから$g$は$I$上連続である.したがって,$g$は有界閉区間$[0,2]\subset I$上でも連続だから,$g$は$[0,2]$上一様連続である.
すなわち,ある$\delta\in(0,1)$が存在して,$x,y\in[0,2]$が$|x-y|<\delta$を満たすなら,$|g(x)-g(y)|<\epsilon$が成り立つ.
よって,$|x-y|<\delta$を満たす任意の$x,y\in I$に対して,$k=\lfloor\max\{x,y\}\rfloor$とおくと$x-k,y-k\in[0,2]$だから,$g$の周期性と併せて
\begin{align*}|g(x)-g(y)|=|g(x-k)-g(y-k)|<\epsilon\end{align*}
が成り立つ.よって,$g$は$I$上一様連続である.
(2)の解答
任意に$\epsilon>0$をとる.仮定より関数列$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$は$I$上で$g$に一様収束する.すなわち,ある$N\in\N$が存在して,$n\ge N$なら
\begin{align*}\sup_{x\in I}|f_n(x)-g(x)|<\frac{\epsilon}{3}\end{align*}
が成り立つ.
[1]$[N,\infty)$上の$f$の一様連続性を示す.
(1)より,ある$\delta\in(0,1)$が存在して,$x,y\in I$が$|x-y|<\delta$を満たすなら$|g(x)-g(y)|<\frac{\epsilon}{3}$が成り立つ.よって,$x,y\in[N,\infty)$が$|x-y|<\delta$を満たせば,
\begin{align*}|f(x)-f(y)|&=|f_N(x-N)-f_N(y-N)|
\\&\le|f_N(x-N)-g(x-N)|
\\&\quad+|g(x-N)-g(y-N)|
\\&\quad+|g(y-N)-f_N(y-N)|
\\&<3\cdot\frac{\epsilon}{3}=\epsilon\end{align*}
が従う.
[2]$[0,N+1]$上の$f$の一様連続性を示す.
$f$は有界閉集合$[0,N+1]$上で連続だから,$f$は$[0,N+1]$上一様連続である.すなわち,ある$\delta’\in(0,1)$が存在して,$x,y\in[0,N+1]$が$|x-y|<\delta’$を満たすなら$|f(x)-f(y)|<\epsilon$が成り立つ.
[1],[2]より,$x,y\in I$が$|x-y|<\min\{\delta,\delta’\}$を満たすなら,$|f(x)-f(y)|<\epsilon$が成り立つ.よって,$f$は$I$上一様連続である.
第5問(微分方程式)
$p$を正の実数とし,$f(t)$を$\R$上の実数値連続関数で
\begin{align*}\int_{0}^{\infty}|f(t)|\,dt<\infty\end{align*}
を満たすものとする.このとき$\R$上の常微分方程式
\begin{align*}\od{x}{t}=-px+f(t)\end{align*}
の任意の解$x(t)$に対し$\lim\limits_{t\to\infty}x(t)=0$が成り立つことを示せ.
1階線形常微分方程式の$x$によらない項$f(t)$が$[0,\infty)$上絶対可積分のとき,解が0に収束することを示す問題です.
解答の方針とポイント
与えられた常微分方程式は1階線形なので解くことができ,直接計算して$\lim\limits_{t\to\infty}x(t)=0$を証明することができます.
1階線形常微分方程式の解法
$\od{dx}{dt}+P(t)x=Q(t)$の形の常微分方程式を1階線形常微分方程式といいます.
この常微分方程式は$x$の係数の$P(t)$の原始関数のひとつを$R(t)$をとり,両辺に$e^{R(t)}$をかけると
\begin{align*}&e^{R(t)}\od{x}{t}+e^{R(t)}P(t)x=e^{R(t)}Q(t)
\\&\iff\od{}{t}(e^{R(t)}x)=e^{R(t)}Q(t)\end{align*}
と左辺をまとめることができます.よって,両辺を積分して整理すれば
\begin{align*}x=x(c)+e^{-R(t)}\int_{c}^{t} e^{R(s)}Q(s)\,ds\end{align*}
と解くことができます.
可積分関数の遠方での積分
実際に本問の方程式を解くと,解は
\begin{align*}x(t)=e^{-pt}x(0)+\int_{0}^{t}e^{p(s-t)}f(s)\,ds\end{align*}
となります.この第1項が0に収束することはすぐに分かるので,あとは第2項が0に収束することを示せば良いですね.
広義積分の定義
\begin{align*}\int_{0}^{\infty}|f(t)|\,dt=\lim_{R\to\infty}\int_{0}^{R}|f(t)|\,dt\end{align*}
から,任意の$\epsilon>0$に対して,十分大きな$R>0$が存在して$\int_{R}^{\infty}|f(t)|\,dt<\epsilon$が成り立ちます.$0\le s\le t$のとき$e^{p(s-t)}\le1$なので,$t>R$のとき遠方$[R,t)$での積分は
\begin{align*}\abs{\int_{R}^{t}e^{p(s-t)}f(s)\,ds}\le\int_{R}^{\infty}|f(s)|\,ds<\epsilon\end{align*}
と小さいことが分かります.一方,有界区間$[0,R]$上での積分も
\begin{align*}\abs{\int_{0}^{R}e^{p(s-t)}f(s)\,ds}\le e^{p(R-t)}\int_{0}^{\infty}|f(s)|\,ds\end{align*}
と評価すれば,$t\to\infty$で0に収束することが分かりますね.
解答例
与えられた常微分方程式は
\begin{align*}&\frac{dx}{dt}=-px+f(t)
\\&\iff e^{pt}\bra{\od{x}{t}+px}=e^{pt}f(t)
\\&\iff\od{}{t}\bra{e^{pt}x}=e^{pt}f(t)
\\&\iff e^{pt}x(t)-e^{p0}x(0)=\int_{0}^{t}e^{ps}f(s)\,ds
\\&\iff x(t)=e^{-pt}x(0)+e^{-pt}\int_{0}^{t}e^{ps}f(s)\,ds\end{align*}
と解ける.$p>0$より$\lim\limits_{t\to\infty}e^{-pt}x(0)=0$だから,あとは第2項が0に収束することを示せばよい.
任意に$\epsilon>0$をとる.$C:=\dint_{0}^{\infty}|f(t)|\,dt$が収束するから,ある$R>0$が存在して,
\begin{align*}\int_{R}^{\infty}|f(t)|\,dt=\int_{0}^{\infty}|f(t)|\,dt-\int_{0}^{R}|f(t)|\,dt<\epsilon\end{align*}
が成り立つ.よって,$t>R$のとき
\begin{align*}&\abs{\int_{0}^{t}e^{p(s-t)}f(s)\,ds}
\\&\le\int_{0}^{R}e^{p(s-t)}|f(s)|\,ds+\int_{R}^{t}e^{p(s-t)}|f(s)|\,ds
\\&\le\int_{0}^{R}e^{p(R-t)}|f(s)|\,ds+\int_{R}^{t}|f(s)|\,ds
\\&<Ce^{p(R-t)}+\epsilon
\xrightarrow[]{t\to\infty}\epsilon\end{align*}
が成り立つ.よって,$\epsilon$の任意性と併せて
\begin{align*}\limsup_{t\to\infty}\int_{0}^{t}e^{p(s-t)}f(s)\,ds=0\end{align*}
が成り立つ.したがって,
\begin{align*}\lim_{t\to\infty}\int_{0}^{t}e^{p(s-t)}f(s)\,ds=0\end{align*}
を得る.以上より$\lim\limits_{t\to\infty}x(t)=0$が従う.
$\int_{0}^{\infty}|f(t)|\,dt<\infty$であっても$\lim\limits_{t\to\infty}f(t)=0$が成り立つとは限らないことには注意してください.
第6問(位相空間論)
$X$, $Y$を位相空間とし,直積集合$X\times Y$を積位相によって位相空間とみなす.写像$f:X\times Y\to Y$を$f(x,y)=y$で定める.$X$がコンパクトならば,$X\times Y$の任意の閉集合$Z$に対し,$f(Z)$は$Y$の閉集合であることを示せ.
積位相空間$X\times Y$上の第2成分への射影$f$が閉写像であることを示す問題ですね.
解答の方針とポイント
「$X$の開被覆がとれれば,うまく$X$の有限個の開集合がとれて,それらの共通部分は開集合」という,コンパクト性を用いた頻出の議論により証明できます.
一般の位相空間上の閉集合
一般の位相空間上の閉集合の定義は様々考えられますが,次のように定義することが多いですね.
位相空間上の閉集合とは,開集合の補集合で表せる集合をいう.
距離空間上では極限や距離を用いて定義することも多いですが,一般の位相空間では距離が定義されているとは限らないことに注意してください.
よって,$f(Z)$は$Y$の閉集合であることを示すには,$Y\setminus f(Z)$が位相空間$Y$上の開集合であることを示せばよいですね.
そのために,任意の$p\in Y\setminus f(Z)$に対して,$Y$における$p$の開近傍で$f(Z)$と共通部分を持たないものが存在することを示しましょう.
コンパクト集合の定義
閉集合$Z\subset X\times Y$と$p\in Y\setminus f(Z)$を考えます.このとき,$p$の開近傍で$f(Z)$と共通部分をもたないものを構成すれば良いですね.
このとき,任意の$x\in X$に対して$(x,p)\notin Z$で,$(X\times Y)\setminus Z$は開なので,積位相の定義より$Z$と共通部分を持たない$(x,p)$の開近傍$U_x\times V_x$が存在します.ただし,$U_x$は$x\in X$の開近傍,$V_x$は$p\in Y$の開近傍です.
このような$U_x\times V_x$を全ての$x$で考えて$V_x$の共通部分$\bigcup\limits_{x\in X}V_x$をとると,$V$は$Z$と共通部分をもたなくなりますが,$\bigcup\limits_{x\in X}V_x$は無限個の開集合の共通部部分なので開集合ではない可能性があります.
そこで,$X$のコンパクト性を使いましょう.
位相空間$X$上の集合$A$がコンパクトであるとは,$A$の任意の開被覆から$A$の有限被覆がとれることをいう.
すなわち,$A\subset\bigcup_{\lambda\in\Lambda}A_\lambda$なる任意の開集合族$\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$に対して,ある$\{A_n\}_{n=1}^{m}\subset\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$が存在して$A\subset\bigcup_{n=1}^{m}A_n$となることをいう.
$X=\bigcup_{x\in X}U_x$なので,$X$のコンパクト性から有限個の$x_1,\dots,x_n\in X$が存在して$X=\bigcup_{k=1}^{n}U_{x_k}$となります.このとき,$V=\bigcap_{k=1}^{n}V_{x_k}$は有限個の開集合の共通部分だから開となります.
よって,あとはこの$V$が$f(Z)$と共通部分をもたない$p$の開近傍になっていることを示せば良いですね.
解答例
$Y\setminus f(Z)$が$Y$の開集合であることを示せばよい.そのために,任意の$p\in Y\setminus f(Z)$に対して,$Y$における$p$の開近傍$V$が存在して,$V\cap f(Z)=\emptyset$が成り立つことを示す.
[1]$Y$における$p$の開近傍$V$を構成する.
もし$(x,p)\in Z$を満たす$x\in X$が存在するなら$p=f(x,p)\in f(Z)$となって$p\notin f(Z)$に矛盾するから,任意の$x\in X$に対して$(x,p)\notin Z$である.また,$Z$は閉だから,$(X\times Y)\setminus Z$は開である.
よって,積位相の定義より,各$x\in X$に対して,$x\in X$のある開近傍$U_x$と$p\in Y$のある開近傍$V_x$が存在して,$U_x\times V_x$は$(x,p)\in X\times Y$の開近傍となり,$(U_x\times V_x)\cap Z=\emptyset$が成り立つ.
各$x\in X$に対して$x\in U_x$だから$X=\bigcup_{x\in X}U_x$なので,$\{U_x\}_{x\in X}$は$X$の開被覆である.$X$はコンパクトだから,有限個の$x_1,\dots,x_n\in X$が存在して,$X=\bigcup_{k=1}^{n}U_{x_k}$が成り立つ.このとき,
\begin{align*}V:=\bigcap_{k=1}^{n}V_{x_k}\end{align*}
は有限個の開集合の共通部分だから開であり,任意の$k\in\{1,\dots,n\}$に対して$p\in V_{x_k}$だから$p\in V$である.よって,$V$は$Y$における$p$の開近傍である.
[2]$V\cap f(Z)=\emptyset$であることを示す.
任意に$q\in f(Z)$をとる.$f$の定義から,ある$r\in X$が存在して$(r,q)\in Z$が成り立つ.
また,$\{U_{x_k}\}_{k=1}^{n}$は$X$の被覆だから,ある$K\in\{1,\dots,n\}$が存在して$r\in U_{x_K}$となる.このとき,$(U_{x_K}\times V_{x_K})\cap Z=\emptyset$だから,$q\notin V_{x_K}$が成り立つ.
よって,$q\notin \bigcap_{k=1}^{n}V_{x_k}=V$だから,$V\cap f(Z)=\emptyset$が従う.
第7問(位相空間論)
$n$を正の整数とし,$\R^n$の2点$x=(x_1,\dots,x_n)$, $y=(y_1,\dots,y_n)$の距離$d(x,y)$を
\begin{align*}d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\dots+(x_n-y_n)^2}\end{align*}
と定める.$\R^n$の空でない部分集合$A$に対し,関数$f:\R^n\to\R$を
\begin{align*}f(x)=\inf_{z\in A}d(x,z)\end{align*}
で定めるとき,$\R^n$の任意の2点$x$, $y$に対して$|f(x)-f(y)|\le d(x,y)$が成り立つことを示せ.
$f(x)$を「集合$A$と点$x$の距離」といいます.示す不等式$|f(x)-f(y)|\le d(x,y)$は「『集合$A$と点$x$の距離』と『集合$A$と点$y$の距離』の差は『点$x$と点$y$の距離』以下」という意味ですから,この意味で$|f(x)-f(y)|\le d(x,y)$は三角不等式の拡張と考えることができます.
解答の方針とポイント
まずは$f(x)=d(x,z_x)$, $f(y)=d(y,z_y)$を満たす$z_x,z_y\in A$が存在する場合を考えてみます.
$x$, $y$は対称なので$d(x,z_x)\ge d(y,z_y)$の場合を考えればよく,このとき示すべき式は
\begin{align*}d(x,z_x)-d(y,z_y)\le d(x,y)\end{align*}
となりますね.$z_x$は$d(x,z_x)=\min\limits_{z\in A}d(x,z)$を満たすので,$d(x,z_x)\le d(x,z_y)$ですから
\begin{align*}d(x,z_x)-d(y,z_y)&=(d(x,z_x)-d(x,z_y))+(d(x,z_y)-d(y,z_y))
\\&\le d(x,z_y)-d(y,z_y)\le d(x,y)\end{align*}
と示すことができます.
実際には,$f(x)=d(x,z_x)$, $f(y)=d(y,z_y)$を満たす$z_x,z_y\in A$が存在するとは限りませんが,$f$が$\inf$で定義されていることから$f(x)\approx d(x,z_x)$となる$z_x\in X$は存在します.よって,三角不等式
\begin{align*}&|f(x)-f(y)|
\\&\le|f(x)-d(x,z_x)|+|d(x,z_x)-d(y,z_y)|+|f(y)-d(y,z_y)|\end{align*}
と上の議論(を少し修正したもの)を併せれば,解くことができますね.
解答例
任意に$x,y\in\R^n$をとる.任意に$\epsilon>0$をとる.$f$の定義(下限の性質)から,ある$z_x,z_y\in A$が存在して
\begin{align*}d(x,z_x)-f(x)<\epsilon,\quad
d(y,z_y)-f(y)<\epsilon\end{align*}
が成り立つから,
\begin{align*}|f(x)-f(y)|&\le|f(x)-d(x,z_x)|+|d(x,z_x)-d(y,z_y)|+|f(y)-d(y,z_y)|
\\&<|d(x,z_x)-d(y,z_y)|+2\epsilon\end{align*}
となる.ここで,$d(x,z_x)\ge d(y,z_y)$のとき,
\begin{align*}&|d(x,z_x)-d(y,z_y)|
\\&=(d(x,z_x)-d(x,z_y))+(d(x,z_y)-d(y,z_y))
\\&\le(d(x,z_x)-f(x))+(d(x,z_y)-d(y,z_y))
\\&<\epsilon+d(x,y)\end{align*}
であり,同様に$d(x,z_x)\le d(y,z_y)$のとき,
\begin{align*}&|d(x,z_x)-d(y,z_y)|
\\&=(d(y,z_y)-d(y,z_x))+(d(y,z_x)-d(x,z_x))
\\&\le(d(y,z_y)-f(y))+(d(y,z_x)-d(x,z_x))
\\&<\epsilon+d(x,y)\end{align*}
である.よって,$|f(x)-f(y)|<d(x,y)+3\epsilon$なので,$\epsilon>0$の任意性から$|f(x)-f(y)|\le d(x,y)$が従う.
この問題の不等式を用いることで,距離空間が正規空間(第1分離公理と第4分離公理を満たす位相空間)であることが証明できます.例えば,「集合・位相入門」(松坂和夫著・岩波書店)の第6章§2を参照してください.
参考文献
以下,私も使ったオススメの入試問題集を挙げておきます.
詳解と演習大学院入試問題〈数学〉
[海老原円,太田雅人 共著/数理工学社]
理工系の修士課程への大学院入試問題集ですが,基礎〜標準的な問題が広く大学での数学の基礎が復習できる総合問題集として利用することができます.
実際,まえがきにも「単なる入試問題の解説にとどまらず,それを通じて,数学に関する読者の素養の質を高めることにある」と書かれているように,必ずしも大学院入試を受験しない一般の学習者にとっても学びやすい問題集です.また,構成が読みやすいのも個人的には嬉しいポイントです.
第1章 数え上げと整数
第2章 線形代数
第3章 微積分
第4章 微分方程式
第5章 複素解析
第6章 ベクトル解析
第7章 ラプラス変換
第8章 フーリエ変換
第9章 確率
一方で,問題数はそれほど多くないので,多くの問題を解きたい方には次の問題集もオススメです.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|詳解と演習 大学院入試問題(数理工学社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.
演習 大学院入試問題
[姫野俊一,陳啓浩 共著/サイエンス社]
上記の問題集とは対称的に問題数が多く,まえがきに「修士の基礎数学の問題の範囲は,ほぼ本書中に網羅されている」と書かれているように,広い分野から問題が豊富に掲載されています.
全2巻で,
1巻第1編 線形代数
1巻第2編 微分・積分学
1巻第3編 微分方程式
2巻第4編 ラプラス変換,フーリエ変換,特殊関数,変分法
2巻第5編 複素関数論
2巻第6編 確率・統計
が扱われています.
地道にきちんと地に足つけた考え方で解ける問題が多く,確かな「腕力」がつくテキストです.入試では基本問題は確実に解けることが大切なので,その意味で試験への対応力が養われると思います.
なお,私自身は受験生時代に計算力があまり高くなかったので,この本の問題で訓練したのを覚えています.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|演習 大学院入試問題[数学](サイエンス社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.

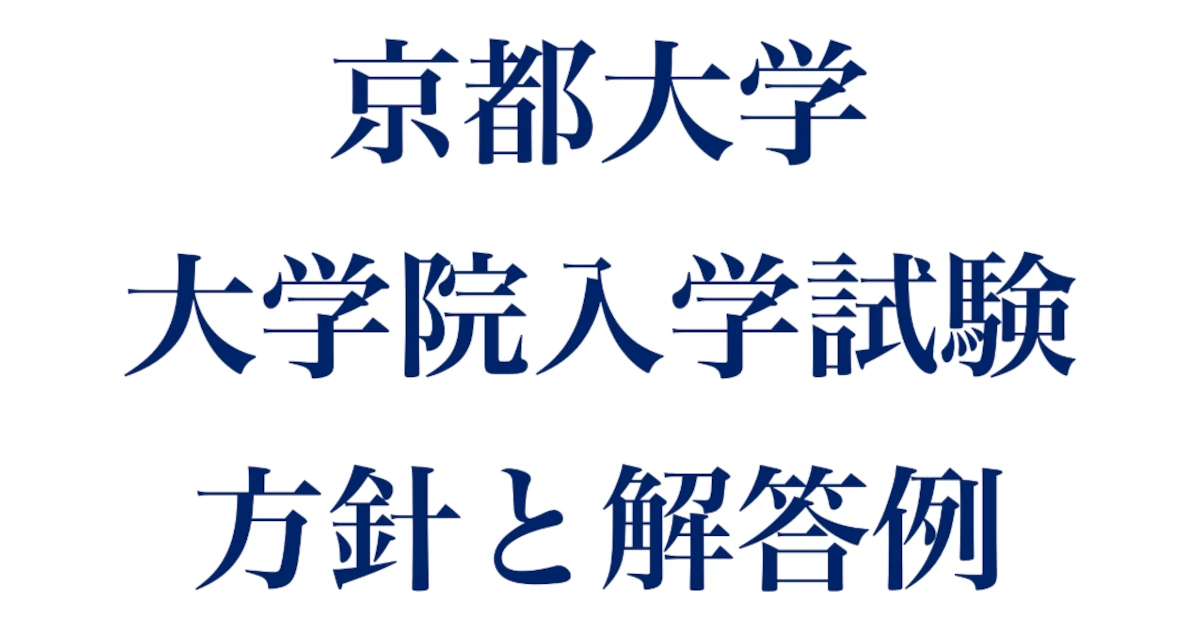


コメント