2015年度の京都大学 理学研究科 数学・数理解析専攻の大学院入試問題の専門科目では,全12題あり
- 数学系は第1問〜第10問から
- 数理解析系は第1問〜第12問から
2題を選択して解答します.試験時間は3時間です.この記事では,第6,7問(解析系)について,解答の方針から解説し解答例を掲載しています.
ただし,公式に採点基準などは発表されていないため,本稿の解答が必ずしも正解になるとは限りません.ご注意ください.
また,十分注意して解答を作成していますが,論理の飛躍・誤りが残っている場合があります.
なお,過去問は京都大学のホームページから入手できます.
第6問(測度論)
$(X,\mathcal{F},\mu)$を測度空間,$f_n$($n\in\N$)と$f$をその上の可測関数とし,次の(a)と(b)を仮定する.
- (a)全ての$x$で$\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$,
- (b)$\sup\limits_{n\in\N}\|f_n\|_2<\infty$.
このとき,以下を示せ.
- $\|f\|_2<\infty$.
- $\mu(X)=1$ならば,任意の$p\in[1,2)$に対し$\lim\limits_{n\to\infty}\|f_n-f\|_p=0$.
ただし,$p\in[1,\infty)$と可測関数$g$に対し$\|g\|_p=\bra{\dint_{X}|g(x)|^p\,d\mu(x)}^{1/p}$とする.
メインは(2)で極限と積分の順序交換ができればよいですね.
解答の方針とポイント
(2)では$p<2$なので,仮定の$f_n\in L^2(X)$との可積分性の差をうまく使いましょう.
ファトゥの補題で極限関数$f$の積分を上から評価する
関数$f$は関数列$\{f_n\}$の極限関数なので,$\|f\|_2$の評価をするには関数列$\{f_n\}$の性質を使うしかありません.
いまは各$n\in\N$に対して,$f_n\in L^2(X)$なのでファトゥの補題から$\|f\|_2\le\liminf\limits_{n\to\infty}\|f_n\|_2$と評価できますね.
[ファトゥの補題]測度空間$(X,\mathcal{F},\mu)$において,可測集合$A$上の非負値可測関数列$\{f_n\}$に対して,
\begin{align*}\int_{A}\liminf_{n\to\infty}f_n(x)\,d\mu(x)\le\liminf_{n\to\infty}\int_{A}f_n(x)\,d\mu(x)\end{align*}
が成り立つ.
ルベーグの収束定理を用いて極限と積分の順序交換を保証する
(2)では,確率空間$(X,\mathcal{F},\mu)$上で
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{X}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)=0\end{align*}
を示すわけですが,条件(a)の各点収束$\lim\limits_{n\to\infty}f_n=f$が成り立っているので,極限と積分の順序交換可能できる示せば良いですね.
極限と積分の順序交換可能であることを保証するにはルベーグの収束定理を用いるのが常套手段ですね.
[ルベーグの収束定理]測度空間$(X,\mathcal{F},\mu)$において,可測集合$A$と,$A$上の可測関数列$\{f_n\}_{n\in\N}$を考える.
を満たせば$\{f_n\}$は項別積分可能である:
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{A}f_n(x)\,d\mu(x)=\int_{A}\lim_{n\to\infty}f_n(x)\,d\mu(x).\end{align*}
しかし,被積分関数$|f_n(x)-f(x)|^p$を$n$によらず一様に上から抑える関数$g$をとるのは難しそうです.つまり,$|f_n-f|$が大きい部分がルベーグの収束定理が使えない原因なので,
- $|f_n-f|$が大きい部分の積分
- $|f_n-f|$が小さい部分の積分
に分けて,前者は一様な$f_n$の2乗可積分性の条件(b)を用いて,後者はルベーグの収束定理を用いて,いずれも0に収束することが言えそうです.
なお,前者については,任意の$\lambda>0$に対して,$p<2$より
\begin{align*}&\int_{\{|f_n-f|>\lambda\}}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)
\\&\le\int_{\{|f_n-f|>\lambda\}}\lambda^{p-2}|f_n(x)-f(x)|^2\,d\mu(x)
\\&\le\lambda^{p-2}\|f_n-f\|_2^2\end{align*}
となるので,条件(b)と併せて
\begin{align*}\lim_{\lambda\to\infty}\sup_{n\in\N}\int_{\{|f_n-f|>\lambda\}}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)=0\end{align*}
と示せば良いですね.
この論法はヴィタリの収束定理の証明と本質的に同じです.これについては解答のあとの補足を参照してください.
解答例
$A\subset X$に対して$\mathbb{I}_A:X\to\R$を$A$の定義関数とする.すなわち,
\begin{align*}\mathbb{I}_A(x)=\begin{cases}1,&x\in A,\\0,&x\notin A\end{cases}\end{align*}
とする.
(1)の解答
ファトゥの補題と仮定(b)より
\begin{align*}\|f\|_2^2&=\int_{X}\abs{\lim_{n\to\infty}f_n(x)}^2\,d\mu(x)
\\&=\int_{X}\liminf_{n\to\infty}|f_n(x)|^2\,d\mu(x)
\\&\le\liminf_{n\to\infty}\|f_n\|_2^2\le\sup_{n\in\N}\|f_n\|_2^2<\infty\end{align*}
が従う.よって,$\|f\|_2<\infty$を得る.
(2)の解答
任意に$\epsilon>0$をとる.$p<2$より,任意の$\lambda>0$に対して
\begin{align*}&\int_{\{|f_n-f|>\lambda\}}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)
\\&=\int_{\{|f_n-f|>\lambda\}}|f_n(x)-f(x)|^{p-2}|f_n(x)-f(x)|^2\,d\mu(x)
\\&\le\int_{\{|f_n-f|>\lambda\}}\lambda^{p-2}|f_n(x)-f(x)|^2\,d\mu(x)
\\&\le\lambda^{p-2}\int_{X}|f_n(x)-f(x)|^2\,d\mu(x)
=\lambda^{p-2}\|f_n-f\|_2^2\end{align*}
が成り立つ.よって,ミンコフスキーの不等式,(1),仮定(b)を併せて
\begin{align*}&\lim_{\lambda\to\infty}\sup_{n\in\N}\int_{\{|f_n-f|>\lambda\}}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)
\\&\le\lim_{\lambda\to\infty}\lambda^{p-2}\sup_{n\in\N}\|f_n-f\|_2^2
\\&\le\lim_{\lambda\to\infty}\lambda^{p-2}\sup_{n\in\N}(\|f_n\|_2+\|f\|_2)^2=0\end{align*}
を得る.これより,ある$R>0$が存在して,
\begin{align*}\sup_{n\in\N}\int_{\{|f_n-f|>R\}}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)<\epsilon\end{align*}
が成り立つ.
一方,$n\in\N$として
- 仮定$(a)$より,$X$上で$\lim\limits_{n\to\infty}|f_n-f|^p\mathbb{I}_{\{|f_n-f|\le R\}}=0$
- $X$上で$|f_n-f|^p\mathbb{I}_{\{|f_n-f|\le R\}}\le R^p$
- $\mu(X)=1$より,$\dint_{X}R^p\,d\mu(x)=R^p\mu(X)=R^p<\infty$
が成り立つから,ルベーグの収束定理が適用できて
\begin{align*}&\lim_{n\to\infty}\int_{\{|f_n-f|\le R\}}|f_n(x)-f(x)|^{p}\,d\mu(x)
\\&=\lim_{n\to\infty}\int_{X}|f_n(x)-f(x)|^{p}\mathbb{I}_{\{|f_n-f|\le R\}}(x)\,d\mu(x)=0\end{align*}
が成り立つ.
以上より,
\begin{align*}\|f_n-f\|_p^p
&=\int_{\{|f_n-f|\le R\}}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)
\\&\qquad+\int_{\{|f_n-f|>R\}}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)
\\&\le\int_{\{|f_n-f|\le R\}}|f_n(x)-f(x)|^p\,d\mu(x)+\epsilon
\\&\xrightarrow[]{n\to\infty}\epsilon\end{align*}
が成り立つ.$\epsilon$の任意性より
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\|f_n-f\|_{p}^{p}=0\iff\lim_{n\to\infty}\|f_n-f\|_p=0\end{align*}
を得る.
補足(一様可積分性とヴィタリの収束定理)
いまの解答は一様可積分とヴィタリの収束定理に深く関係しています.
有限測度空間$(X,\mathcal{F},\mu)$上の実数値可測関数列$\{f_n\}$が一様可積分であるとは
\begin{align*}\lim_{\lambda\to\infty}\sup_{n\in\N}\int_{\{|f_n|\ge\lambda\}}|f_n(x)|\,d\mu(x)=0\end{align*}
が成り立つことをいう.
[ヴィタリの収束定理]有限測度空間$(X,\mathcal{F},\mu)$上の一様可積分な実数値可測関数列$\{f_n\}$が関数$f$に概収束するとき,$f$は可積分で
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{X}|f_n(x)-f(x)|\,d\mu(x)=0\end{align*}
が成り立つ.
このヴィタリの収束定理の証明では,上の解答例と同様に
- $|f_n|$が大きい部分の積分
- $|f_n|$が小さい部分の積分
に分けて,前者は$\{f_n\}_{n\in\N}$の一様可積分性を用いて,後者はルベーグの収束定理を用いて,いずれも0に収束することを示します.
したがって,上の解答は本質的に「$\{|f_n-f|^p\}$の一様可積分性を示してヴィタリの収束定理を用いた」のと同じことをしているわけですね.
そのため,$\{|f_n-f|^p\}$の一様可積分性を示したあと,ヴィタリの収束定理より$\lim\limits_{n\to\infty}\|f_n-f\|_p^p=0$が成り立つとしても,数学的には正しい解答です.
第7問(関数解析学)
任意の$f\in L^2(\R)$と$x\in\R$に対し
\begin{align*}Tf(x)=\int_{0}^{\infty}\brb{\int_{x-t}^{x+t}f(s)\,ds}\frac{e^{-t}}{t}\,dt\end{align*}
と定める.このとき,以下の問に答えよ.
- $T$は$L^2(\R)$から$L^2(\R)$への作用素として定義でき,有界であることを示せ.
- $T$は$L^2(\R)$から$L^2([0,1])$への作用素としてコンパクトであることを示せ.
メインは(2)で作用素$T$のコンパクト性を示す問題です.
解答の方針とポイント1
(1)と(2)の違いは作用素$T$の終集合です.終集合が$L^2(\R)$のときは有界性までしか示せませんが,終集合が$L^2([0,1])$のときは$T$はコンパクトであることまで示すことができます.
(積分形の)ミンコフスキーの不等式
積分区間に変数$x$が入っていると扱いにくいことも多いので,(1)では$Tf$の$s$に関する積分で$\tilde{s}=x-s$と置き換え,そのあと$L^{2}(\R)$ノルムを考えると
\begin{align*}\|Tf\|_{L^2(\R)}=\bra{\int_{\R}\abs{\int_{0}^{\infty}\brb{\int_{-t}^{t}f(x-\tilde{s})\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^{2}\,dx}^{1/2}\end{align*}
となります.$f\in L^2(\R)$なので$|f|^2$の積分を作り出したいところです.そこで,(積分形の)ミンコフスキーの不等式を繰り返し使うことで,
\begin{align*}\|Tf\|_{L^2(\R)}\le\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{-t}^{t}\bra{\int_{\R}\abs{f(x-\tilde{s})}^{2}\,dx}^{1/2}\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}\,dt\end{align*}
と評価でき,$f\in L^{2}(\R)$からこの$L^2(\R)$ノルムは有限ですね.
[ミンコフスキーの不等式]$A_1,A_2\subset\R$を可測集合とし,$1\le q\le p$とする.$A_1\times A_2$上の可測関数$f$がほとんど全ての$y\in A_2$に対して$f(\cdot,y)\in L^p(A_1)$であり,$(\int_{A_1}|f(x,\cdot)|^p\,dx)^{1/p}\in L^q(\R)$が成り立てば,
\begin{align*}\bra{\int_{A_1}\bra{\int_{A_2}|f(x,y)|^q\,dy}^{p/q}\,dx}^{1/p}
\le\bra{\int_{A_2}\bra{\int_{A_1}|f(x,y)|^p\,dx}^{q/p}\,dy}^{1/q}\end{align*}
が成り立つ.
ヒルベルト空間上の線形作用素がコンパクトであるための十分条件
ヒルベルト空間上の線形作用素がコンパクトであることを示すには次の定理が便利です.
ヒルベルト空間$\mathcal{H}$, $\mathcal{H}’$上の線形作用素$T:\mathcal{H}\to\mathcal{H}’$を考える.0に弱収束する任意の$\mathcal{H}$上の列$\{f_n\}$に対して,$\mathcal{H}’$上の列$\{Tf_n\}$が0に強収束するとき,$T$はコンパクト作用素である.
回帰的バナッハ空間$X$からバナッハ空間$Y$への線形作用素$X\to Y$に対しても同様の定理が成り立ちます.
そこで,(2)では0に弱収束する任意の$\mathcal{H}$上の列$\{f_n\}$をとり,
\begin{align*}\|Tf_n\|_{L^2([0,1])}=\bra{\int_{0}^{1}\abs{\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{x-t}^{x+t}f_n(s)\,ds}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^2\,dx}^{1/2}\end{align*}
が0に収束することを示せば良いですね.
ヒルベルト空間上の弱収束
一般のノルム空間における弱収束は次で定義されるのでした.
ノルム空間$X$上の点列$\{f_n\}_{n\in\N}$が$f\in\mathcal{H}$に弱収束するとは,任意の$g\in X^*$に対して$\lim\limits_{n\to\infty}g(f_n)=g(f)$が成り立つことをいう.
リースの表現定理より,ヒルベルト空間上の点列が弱収束するための必要十分条件は次のようになりますね.
ヒルベルト空間$\mathcal{H}$上の点列$\{f_n\}_{n\in\N}$と$f\in\mathcal{H}$に対して,次は同値である.
- $\{f_n\}_{n\in\N}$が$f$に弱収束
- 任意の$g\in\mathcal{H}$に対して$\lim\limits_{n\to\infty}\anb{f_n,g}=\anb{f,g}$
いま$\{f_n\}$が0へ弱収束するので,任意の$g\in L^2([0,1])$に対して$\lim\limits_{n\to\infty}\anb{f_n,g}_{L^2(\R)}=0$が成り立ちます.よって,
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{x-t}^{x+t}f_n(s)\,ds=\anb{f_n,\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\xrightarrow[]{n\to\infty}0\end{align*}
ですから,
\begin{align*}&\lim_{n\to\infty}\|Tf_n\|_{L^2([0,1])}
\\&=\lim_{n\to\infty}\bra{\int_{0}^{1}\abs{\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{x-t}^{x+t}f_n(s)\,ds}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^2\,dx}^{1/2}\end{align*}
で極限と積分の順序交換が(2回)できれば0に収束しますね.よって,ルベーグの収束定理を(2回)用いれば極限が求められます.
ルベーグの収束定理については,上で解説した第6問の考え方とポイントを参照してください.
解答例1
$A\subset\R$に対して$\mathbb{I}_A:\R\to\R$を$A$の定義関数とする:
\begin{align*}\mathbb{I}_A(x)=\begin{cases}1,&x\in A,\\0,&x\notin A.\end{cases}\end{align*}
(1)の解答
積分の線形性から$T$は線形作用素である.任意に$f\in L^{2}(\R)$をとる.$\tilde{s}=x-s$とおくと
\begin{align*}Tf(x)&=\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{-t}^{t}f(x-\tilde{s})\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}\,dt\end{align*}
なので,ミンコフスキーの不等式を繰り返し用いて
\begin{align*}&\|Tf\|_{L^2(\R)}=\bra{\int_{\R}|Tf(x)|^{2}\,dx}^{1/2}
\\&=\bra{\int_{\R}\abs{\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{-t}^{t}f(x-\tilde{s})\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^{2}\,dx}^{1/2}
\\&\le\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{\R}\abs{\bra{\int_{-t}^{t}f(x-\tilde{s})\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}}^{2}\,dx}^{1/2}\,dt
\\&=\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{\R}\abs{\int_{-t}^{t}f(x-\tilde{s})\,d\tilde{s}}^{2}\,dx}^{1/2}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&\le\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{-t}^{t}\bra{\int_{\R}\abs{f(x-\tilde{s})}^{2}\,dx}^{1/2}\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&=\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{-t}^{t}\|f\|\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&=2\|f\|\int_{0}^{\infty}e^{-t}\,dt=2\|f\|<\infty\end{align*}
が成り立つ.よって,$T$は$L^2(\R)$から$L^2(\R)$への作用素として定義でき,有界である.
(2)の解答
積分の線形性から$T$は線形作用素で,(1)と同様にして$T$は$L^2(\R)$から$L^2([0,1])$への作用素として定義できる.
0に弱収束する$L^2(\R)$上の列$\{f_n\}_{n\in\N}$を任意にとる.弱収束列は有界だから,ある$M>0$が存在して任意の$n\in\N$に対し$\|f_n\|_{L^2(\R)}\le M$が成り立つ.
\begin{align*}&\|Tf_n\|_{L^2([0,1])}=\bra{\int_{0}^{1}|Tf_n(x)|^2\,dx}^{1/2}
\\&=\bra{\int_{0}^{1}\abs{\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{x-t}^{x+t}f_n(s)\,ds}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^2\,dx}^{1/2}
\\&=\bra{\int_{0}^{1}\abs{\int_{0}^{\infty}\anb{f_n,\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^2\,dx}^{1/2}\end{align*}
である.任意の$x\in[0,1]$に対して
- $\{f_n\}_{n\in\N}$は0に弱収束するから,任意の$t>0$に対して,$\lim\limits_{n\to\infty}\anb{f_n,\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\dfrac{e^{-t}}{t}=0$
- コーシー-シュワルツの不等式より,任意の$t>0$に対して,
\begin{align*}\abs{\anb{f_n,\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\frac{e^{-t}}{t}}&\le\|f_n\|_{L^2(\R)}\nor{\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\frac{e^{-t}}{t}
\\&\le M\cdot\sqrt{2t}\cdot\frac{e^{-t}}{t}\le\frac{\sqrt{2}Me^{-t}}{\sqrt{t}}\end{align*} - $\dint_{0}^{\infty}\dfrac{\sqrt{2}Me^{-t}}{\sqrt{t}}\,dt=\sqrt{2}M\Gamma\bra{\frac{1}{2}}<\infty$
が成り立つから,ルベーグの収束定理より
\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\abs{\int_{0}^{\infty}\anb{f_n,\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^2=0\end{align*}
が成り立つ.さらに,
\begin{align*}&\abs{\int_{0}^{\infty}\anb{f_n,\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^2
\\&\le\bra{\sqrt{2}M\Gamma\bra{\frac{1}{2}}}^2
=2M^2\Gamma\bra{\frac{1}{2}}^2\end{align*}
であり,$\dint_{0}^{1}2M^2\Gamma\bra{\dfrac{1}{2}}^2\,dx=2M^2\Gamma\bra{\frac{1}{2}}^2<\infty$が成り立つから,再びルベーグの収束定理より
\begin{align*}&\lim_{n\to\infty}\|Tf_n\|_{L^2([0,1])}
\\&=\lim_{n\to\infty}\bra{\int_{0}^{1}\abs{\int_{0}^{\infty}\anb{f_n,\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}^2\,dx}^{1/2}=0\end{align*}
である.すなわち,$L^{2}([0,1])$上で$\{Tf_n\}$が0に強収束することが分かったから,$\mathcal{D}(T)=L^2(\R)$がヒルベルト空間(回帰的バナッハ空間)であることと併せて$T$はコンパクトである.
解答の方針とポイント2
(1)はヤングの不等式を用いて,(2)はアスコリ-アルツェラの定理を用いて解くこともできます.
ヤングの不等式
積分区間に変数$x$が入っていると扱いにくいことも多いので,$Tf$の$s$に関する積分で$\tilde{s}=x-s$と置き換えることで
\begin{align*}Tf(x)&=\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{-t}^{t}f(x-\tilde{s})\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&=\int_{\R}\bra{\int_{|\tilde{s}|}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}|f(x-\tilde{s})|\,d\tilde{s}\end{align*}
となり,これは関数$g(x):=\int_{|x|}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}\,dt$と$|f|$の合成積です.よって,ヤングの不等式より
\begin{align*}\|Tf\|_{L^2(\R)}\le\|f\|_{L^2(\R)}\|g\|_{L^1(\R)}\end{align*}
となるので,あとは$\|g\|_{L^1(\R)}<\infty$を示せば良いですね.
[ヤングの不等式]$p,q,r\in[1,\infty]$は$\frac{1}{r}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-1$を満たすとする.$f\in L^p(\R^n)$, $g\in L^q(\R^n)$に対して,$f*g\in L^r(\R^n)$であり
\begin{align*}\|f*g\|_{L^r(\R^n)}\le\|f\|_{L^p(\R^n)}\|g\|_{L^q(\R^n)}\end{align*}
が成り立つ.
アスコリ-アルツェラの定理で一様収束部分列を捕まえる
(2)ではコンパクト作用素の定義通り$L^2([0,1])$の任意の有界列$\{f_n\}_n$に対して,$L^2([0,1])$上で収束する$\{Tf_n\}_n$の部分列が存在することを示しましょう.
バナッハ空間$X$からバナッハ空間$Y$への線形作用素$T$がコンパクト作用素であるとは,$\mathcal{D}(T)=X$を満たし,$X$上の任意の有界点列$\{f_n\}_{n\in\N}$に対して,$Y$上の点列$\{Tf_n\}_{n\in\N}$が収束部分列をもつことをいう.
(2)では各$Tf_n$をコンパクト集合$[0,1]$上の関数とみなし,$\{Tf_n\}_{n\in\N}$の$L^2([0,1])$での収束部分列の存在を示すので,次のアスコリ-アルツェラの定理が思い付きます.
[アスコリ-アルツェラの定理]コンパクト距離空間$(X,d)$上の関数列$\{f_n\}_{n\in\N}$が$X$上で一様有界かつ同程度連続なら,$\{f_n\}_{n\in\N}$は$X$上一様収束する部分列をもつ.ただし,関数列$\{f_n\}$について
- $X$上一様有界であるとは,ある$M>0$が存在して,任意の$x\in X$に対して$\sup\limits_{n\in\N}|f_n(x)|\le M$が成り立つこと
- $X$上同程度連続であるとは,任意の$\epsilon>0$に対して,ある$\delta>0$が存在して,$d(x,x’)<\delta$を満たす任意の$x,x’\in X$に対して$\sup\limits_{n\in\N}|f_n(x)-f_n(x’)|\le\epsilon$が成り立つこと
をいう.
すなわち,$\{Tf_n\}_{n\in\N}$が一様有界かつ同程度連続であることを示すことができれば,一様収束する部分列$\{Tf_{n(k)}\}_{k\in\N}$が存在します.このとき,$\{T_{n(k)}\}_{k\in\N}$も同程度連続だから各$T_{n(k)}$も連続なので,一様収束極限$g$も連続となります.
よって,コンパクト集合$[0,1]$上で$g$は有界なので$g\in L^{2}([0,1])$が成り立ち,$\{Tf_n\}_{n\in\N}$が収束部分列をもつことが分かりますね.
解答例2
(1)の解答
積分の線形性から$T$は線形作用素である.任意に$f\in L^{2}(\R)$をとる.$\tilde{s}=x-s$とおくと,トネリの定理より
\begin{align*}|Tf(x)|
&\le\int^{\infty}_{0}\bra{\int_{-t}^{t}\abs{f(x-\tilde{s})}\,d\tilde{s}}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&=\int_{\R}\bra{\int_{|\tilde{s}|}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}|f(x-\tilde{s})|\,d\tilde{s}\end{align*}
が成り立つ.よって,$g(x)=\int_{|x|}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}\,dt$とおくと,ヤングの不等式($\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{1}-1$)より
\begin{align*}\|Tf\|_{L^2(\R)}\le\nor{g*|f|}_{L^2(\R)}\le\|f\|_{L^2(\R)}\|g\|_{L^1(\R)}\end{align*}
が成り立つ.さらに,再びトネリの定理より
\begin{align*}\|g|_{L^1(\R)}&=\int_{\R}\bra{\int_{|x|}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}\,dt}\,dx
\\&=\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{-t}^{t}\,dx}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&=\int_{0}^{\infty}2e^{-t}\,dt=2\end{align*}
なので,$\|Tf\|\le2\|f\|<\infty$となる.よって,$T$は$L^2(\R)$から$L^2(\R)$への有界作用素として定義できる.
(2)の解答
積分の線形性から$T$は線形作用素で,(1)と同様にして$T$は$L^2(\R)$から$L^2([0,1])$への作用素として定義できる.
$L^{2}(\R)$上の有界列$\{f_n\}_{n\in\N}$を任意にとり,$M>0$は任意の$n\in\N$に対して$\|f_n\|_{L^2(\R)}\le M$を満たすとする.
[1]任意の$n\in\N$, $x\in[0,1]$に対して,
\begin{align*}\int_{x-t}^{x+t}|f_n(s)|\,ds&=\int_{\R}|f_n(s)|\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}(s)\,ds
\\&\le\|f_n\|_{L^2(\R)}\nor{\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}}_{L^2(\R)}\le M\sqrt{2t}\end{align*}
なので,
\begin{align*}|Tf_n(x)|&\le\int_{0}^{\infty}\bra{\int_{x-t}^{x+t}|f_n(s)|\,ds}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&\le\sqrt{2}M\int_{0}^{\infty}\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\,dt
=\sqrt{2}M\Gamma\bra{\frac{1}{2}}<\infty\end{align*}
が成り立つ.よって,$\{Tf_n\}_{n\in\N}$は$[0,1]$上一様有界である.
[2]任意に$\epsilon>0$をとり,$0<x-x'<\epsilon$を満たす$x,x’\in[0,1]$を任意にとる.任意の$t\in[0,\infty)$に対して,
\begin{align*}&\abs{\int_{x-t}^{x+t}f_n(s)\,ds-\int_{x’-t}^{x’+t}f_n(s)\,ds}
\\&=\abs{\int_{x’+t}^{x+t}f_n(s)\,ds-\int_{x’-t}^{x-t}f_n(s)\,ds}
\\&\le\int_{x’+t}^{x+t}|f_n(s)|\,ds+\int_{x’-t}^{x-t}|f_n(s)|\,ds
\\&\le\|\mathbb{I}_{[x’+t,x+t]}\|_{L^2(\R)}\|f_n\|_{L^2(\R)}+\|\mathbb{I}_{[x’-t,x-t]}\|_{L^2(\R)}\|f_n\|_{L^2(\R)}
\\&\le2M\sqrt{x-x’}<2M\sqrt{\epsilon}\end{align*}
が成り立ち,
\begin{align*}&\abs{\int_{x-t}^{x+t}f_n(s)\,ds-\int_{x’-t}^{x’+t}f_n(s)\,ds}
\\&\le\int_{x-t}^{x+t}|f_n(s)|\,ds+\int_{x’-t}^{x’+t}|f_n(s)|\,ds
\\&\le\|\mathbb{I}_{[x-t,x+t]}\|_{L^2(\R)}\|f_n\|_{L^2(\R)}+\|\mathbb{I}_{[x’-t,x’+t]}\|_{L^2(\R)}\|f_n\|_{L^2(\R)}
\\&\le2\sqrt{2}M\sqrt{t}\end{align*}
が成り立つ.よって,$n\in\N$によらず
\begin{align*}&\abs{Tf_n(x)-Tf_n(x’)}
\\&\le\int_{0}^{\infty}\abs{\int_{x-t}^{x+t}f_n(s)\,ds-\int_{x’-t}^{x’+t}f_n(s)\,ds}^{1/2}
\\&\qquad\times\abs{\int_{x-t}^{x+t}f_n(s)\,ds-\int_{x’-t}^{x’+t}f_n(s)\,ds}^{1/2}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&\le\int_{0}^{\infty}\bra{2M\sqrt{\epsilon}}^{1/2}\bra{2\sqrt{2}M\sqrt{t}}^{1/2}\frac{e^{-t}}{t}\,dt
\\&=2^{5/4}M\epsilon^{1/4}\int_{0}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t^{3/4}}\,dt
=2^{5/4}M\Gamma\bra{\frac{1}{4}}\epsilon^{1/4}\end{align*}
が成り立つから,$\{Tf_n\}_{n\in\N}$は$[0,1]$上同程度連続である.
[1],[2]と$[0,1]$がコンパクトであることを併せて,アスコリ-アルツェラの定理より$[0,1]$上で一様収束する$\{Tf_n\}_{n\in\N}$の部分列$\{Tf_{n(k)}\}_{k\in\N}$が存在する.
[2]より各$k\in\N$に対して$Tf_{n(k)}$は$[0,1]$上で連続だから,$\{Tf_{n(k)}\}_{k\in\N}$の一様収束極限$g$も$[0,1]$上で連続である.よって,$g\in L^2([0,1])$なので,$L^2([0,1])$上で$\{Tf_{n(k)}\}_{k\in\N}$が収束することが分かったから,$T$はコンパクトである.
参考文献
以下,私も使ったオススメの入試問題集を挙げておきます.
詳解と演習大学院入試問題〈数学〉
[海老原円,太田雅人 共著/数理工学社]
理工系の修士課程への大学院入試問題集ですが,基礎〜標準的な問題が広く大学での数学の基礎が復習できる総合問題集として利用することができます.
実際,まえがきにも「単なる入試問題の解説にとどまらず,それを通じて,数学に関する読者の素養の質を高めることにある」と書かれているように,必ずしも大学院入試を受験しない一般の学習者にとっても学びやすい問題集です.また,構成が読みやすいのも個人的には嬉しいポイントです.
第1章 数え上げと整数
第2章 線形代数
第3章 微積分
第4章 微分方程式
第5章 複素解析
第6章 ベクトル解析
第7章 ラプラス変換
第8章 フーリエ変換
第9章 確率
一方で,問題数はそれほど多くないので,多くの問題を解きたい方には次の問題集もオススメです.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|詳解と演習 大学院入試問題(数理工学社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.
演習 大学院入試問題
[姫野俊一,陳啓浩 共著/サイエンス社]
上記の問題集とは対称的に問題数が多く,まえがきに「修士の基礎数学の問題の範囲は,ほぼ本書中に網羅されている」と書かれているように,広い分野から問題が豊富に掲載されています.
全2巻で,
1巻第1編 線形代数
1巻第2編 微分・積分学
1巻第3編 微分方程式
2巻第4編 ラプラス変換,フーリエ変換,特殊関数,変分法
2巻第5編 複素関数論
2巻第6編 確率・統計
が扱われています.
地道にきちんと地に足つけた考え方で解ける問題が多く,確かな「腕力」がつくテキストです.入試では基本問題は確実に解けることが大切なので,その意味で試験への対応力が養われると思います.
なお,私自身は受験生時代に計算力があまり高くなかったので,この本の問題で訓練したのを覚えています.
なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.
【オススメの問題集|演習 大学院入試問題[数学](サイエンス社)】
本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.
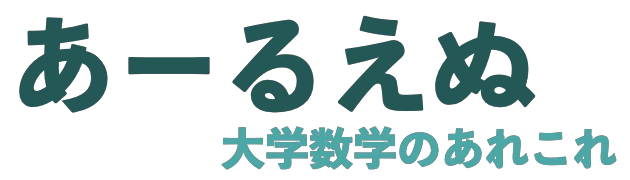
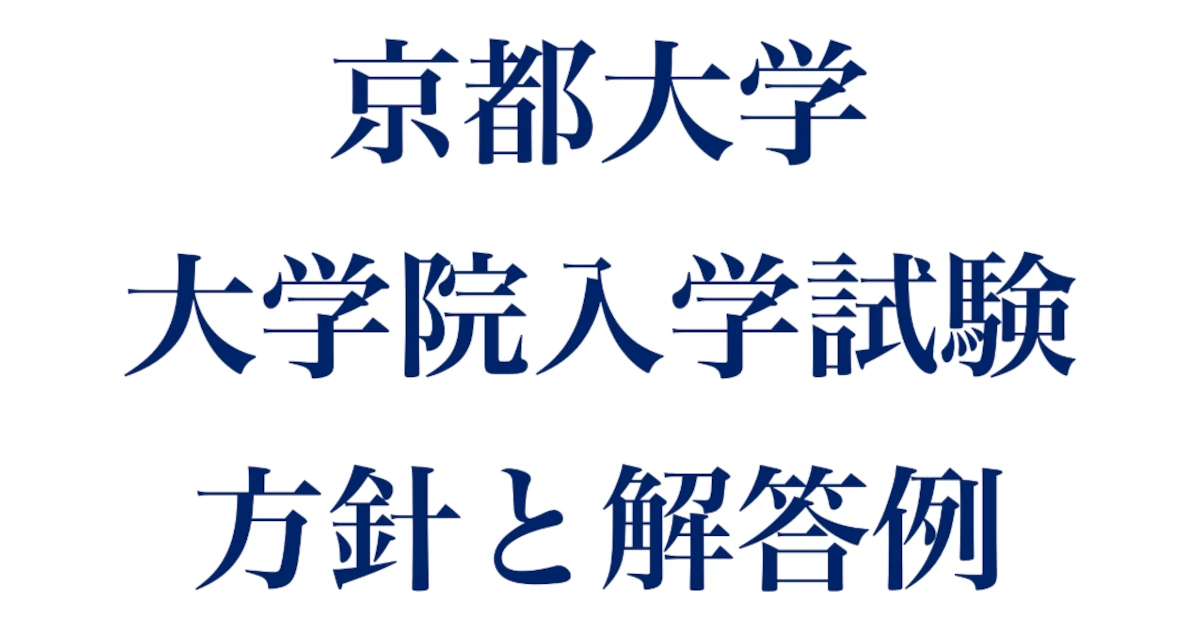


コメント